     |
| index > 年次大会 > 第10回大会 |
|||||||||
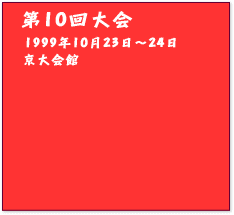 第10回大会記念企画: 私の教育学研究と教育目標・評価学会 公開シンポジウム: 総合学習はどんな子どもを育てるか −和光鶴川小学校と 奈良女子大学附属小学校に聞く− |
|||||||||
|
|||||||||
 |
|||||||||
本企画ではまず,次のようなお話を中内先生からうかがった(文中敬称略)。 今日は,歴史的,社会学的,心理学的な研究につきない教育学とはどういう学問かについて話したい。 ここでいう教育学とは,大学の教育学だけでなく,親たちが伝承し築き上げてきた民衆教育学(folk pedagogy)をも指している。 いつか教育原論をまとめてみたいと考えたが,最近になってまとめることができた(『新・教育原論』)。 本学会は,この書物に託した願いと関わっている。 1954年に卒論として「技術と人間形成」を書いた。 心血をそそいだが,教授会では評価が低かった。 教育はアガペの愛だと教えられたが,それだけではそれで終わってしまうと感じた。 むしろ教育学研究は“愛”の形の工夫の優劣・適否,構想力の背後にある判断力の質に関わっていると考えた(cf. カントの『判断力批判』)。 このような考えの背景には,幼児期に実に大人には知恵があるなと思いつつ育ったこと,30代半ばまで中学生を教えた経験,三木清の構想の論理,戸坂潤,三枝博音,マンフォードの技術の捉え方などから受けた影響がある。デューイや教育心理学がはやっている中で,肩身が狭い教育社会学の論文として書いた。 構想力には,三木によると,呪術(神話),芸術,技術,制度がある。 教育を芸術として捉えたのは,『国家に於ける文化と教育』を書き,形成的自覚を論じた木村素衛である。 教育を技術として捉えたもののひとつは師範学校だったが,師範学校は技術を歪な形で実現した。 技術は,パトスとロゴスの統一物。ところが師範学校の技術の世界は,パドスを無にしてしまう。 教育は,広い意味での技術を子どもに身に付けさせることであり,教育学は技術学のひとつである。 教育を制度として捉えたのは,吉田熊次を代表とする東大の学派。 官房学という点では組めないが,教育学は哲学ではないと篠原助市を批判した点は理解できる。 50年代の革命的な空気に影響されて,social order, cultural order, technological order のうち social order,すなわち制度としての人づくりをやりたいと考えた。 修士課程では上京して,勝田守一,大田堯の指導を受けた。 清水義弘,海後宗臣などの数量的実証主義にもひかれたが,肌に合わず結局勝田に戻った。 勝田の「研究集会というもの」を受け継ぎつつ,治者の制度学をどう乗り越えるかという問題意識から,城戸幡太郎,波多野完治,国分一太郎といった民間教育運動関係者と出会った。 当時の院生の学風には,先生にひっついて学会に寄り添うタイプ,政党や組合運動に没頭するタイプ,民間運動に身を投じた教師の実践の理論化を目指すタイプがあった。 第三のタイプは,日本人の日常生活から日本の資料を使って理論を作るもの。学会に認知させたいと考えたが,当時は下手物扱いだった。 その後成蹊学園の事務員や教員を勤めたり,教科研で右翼から脅されたりしながら機関誌の編集の実務をやったりした。 民間教育研究運動には,生活を強調するものと,技術革新を強調するものがあり,技術革新を強調するものには数教協のような「現代化」を推し進めるものがあった。 卒論で考えたことを具体化しようと思って,『学力と評価の理論』,『教材と教具の理論』,『指導過程と学習形態の理論』の三部作をまとめた。 一方,学位論文の方は,生活を強調する生活綴方について書いた。 さらに,どこにも属さず人づくりの実践をしている教師や親たちとの出会いを通して,匿名の技と術の世界にも気付かされた。これが教育の社会史的研究につながっている。 さて,本学会と関わりが深い全国到達度評価研究会は,私にとっては,目標研究と評価研究が不離一体であるとし,教育を制作(ポイエシス)として捉える『学力と評価の理論』の立場と密接な関わりを持っている。 つまり,教育を技として捉え,構想力を問題にする。 京都数教協の堀井洋子から評価研究会への誘いを受け,そこで中原克巳,遠藤光男と出会った。 ブルーム研究をしていた稲葉研究室と密接なつながりを持ちつつ,1979年,到達度評価研究会が設立された。 本学会を発案したのは中原であったが,発足には大麻南,村越邦男などが協力した。 最後に,本学会の今後あるべき姿として,次の二点を述べておきたい。 ひとつは,folk pedagogyを吸収し,学びながら,教育学の再編成を目指すという点である。 もうひとつは,課題研究を大切にして欲しいということである。 中内先生のお話に引き続き,質疑応答が行われた。 まず,「社会史研究から見たときの教育学研究の意義は何か」,「到達度評価が,生活綴方の正当な嫡子であるとはどういうことか」,「< 教育>を超える次元にたち現れてくるものとは何か」といった質問が出された。 中内先生は,これらの問いはつながっていると答え,「到達度評価と生活綴方は,形成的評価を大事にする点で共通している。しかし生活綴方は,non-programな人づくりの方法であり,歴史的存在としての教育(目標を設定し,プログラム化し,実施するもの)とは,異なっている」,「豊かな民衆の生活経験の世界に気付いたのが,綴方教師たちであった」,「教育=過程説が日本で優勢なのは,神道が日本社会の基層をなしているからではないか」と語った。 これに対し,「生活綴方は,教育ではないという理由がよく分からない。書かせることで自覚させるという点では,やはり形成そのものではないのではないか」という疑問が出されたが,中内先生は,「教育ではないが人間形成のひとつの方法であるといえる。書かせる行為は,形成に立地して人づくりの技に肉薄するその取っ掛かりではあるが,生活綴方がめざすところはあくまで<形成>過程のもっている陶冶力の開発であって,その点で教育とは異なる」と返答した。 その他,「教師の専門性の中心に構想力が位置づくのはわかるが,人間を対象とすることの特殊性から,思う通りに進まないのが実感であり,不可知論に陥りがちだが…」との質問に対しては,「その通り。実際斉藤喜博は,教育は虚しいと言った。しかしまあ,そう言わずに,できなくてもともと,でもできるように…という姿勢で」という返答であった。 さらに「逆に,『教育で何でもできる』という世論に限定を加えるべきではないか」との意見が出されたが,これに対しては河原尚武氏が,「だからこそ,中内先生は,教育を狭く深く捉えているのだろう」と引き取った。 最後に,「子どもの発達と社会の要請をつなぐものとしての教科の組織論が問題になるのではないか」との意見に対しては,「教科は制作説の典型だが,日本の学校の教科は輸入品である。教科のなかった寺子屋と,明治期に成立した小学校との非連続性を強調する必要がある」との方向性が示された。 |
|||||||||
 |
|||||||||
文責:西 岡 加名恵 (鳴門教育大学) |
|||||||||