     |
| ndex > 年次大会 > 第11回大会 |
||
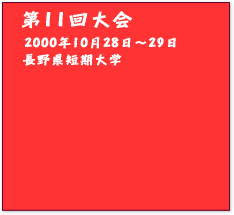 課題研究B: 自己評価のあり方を探る 課題研究C: 「学力の国際比較」とはどういうことか? IEA調査報告の検討その1 |
||
| 「真正の評価(authentic assessment)論」における 「自己評価(self-assessment)」のあり方について 田 中 耕 治 (京都大学) ポートフォリオによって育成される学力とは何か 加 納 寛 子 (岐阜北高等学校) ポートフォリオを用いた指導と評価 -ポートフォリオ検討会に焦点をあてて- 西岡 加名恵 (鳴門教育大学) 司会: 岸 本 実(滋賀大学) |
||
課題研究Bは,指導過程グループより,次の3つの報告を受け,ポートフォリオを一つの焦点として自己評価のあり方を探ることを課題とするものであった。 まず,「『真正の評価(authentic assessment)』論における『自己評価(self-assessment)』のあり方について」という田中耕治会員の報告は,ポートフォリオ評価法を基礎づけている「真性の評価」論について,その特徴,それが提起する自己評価のあり方,そして,その課題と問題点について考察を深めるものであった。 報告の内容は,①assessment論にあるevaluationのとらえなおしの契機,②「真正性」の定義と活動主義に陥る危険性,③ポートフォリオを基礎づける「フィードバック」による子どもたちの「自己評価」から「理解」へという方法原理,④stakeholderからみた教育評価のポリティックスと子どもの参加の問題という4点から構成された。 この報告をめぐる討議では,「真正性」として追及されていることと,日本で「習熟」ということで追求してきたこととの,違いや関係,stakeholderという点について,教育的価値を公共的なものとして共有するプロセスを,どう再構築していくのか,などが主に論議された。 次に,「ポートフォリオによって育成される学力とは何か」という加納寛子会員の報告では,高校数学における学びのプロセスを視覚化するという意義を持つポートフォリオ実践について,「活動中のポートフォリオ」と「永久保存版ポートフォリオ」のつくり方とその関係,評価課題例など,具体的に示された。 また,ポートフォリオを導入しなかったクラスとの比較に基いて,ポートフォリオによって育成される学力についての分析が行われた。 そして,知識の構築過程を視覚化するポートフォリオを振り返ることにより,次のようなサイクルができることが強調された。 すなわち,生徒は自己の学習成果を自己評価することにより,メタ認知能力が育ち,モニタリングとコントロールが習慣化し,自己効力感(Sel-efficacy)が高まる。 それが生徒の自信につながり主体的に問題解決するようになるというサイクルである。 こうしたサイクルを通して自ら学ぶ力を基礎学力として位置づけることが重要であり,ポートフォリオがそれを可能にすることが指摘された。 この報告に対して,ポートフォリオ実践の具体的な進め方ついて質疑の中で深められるとともに,これまで自覚されていないポートフォリオ的行為の位置づけなどが,論議された。 西岡加名恵会員からの「ポートフォリオを用いた指導と評価―ポートフォリオ検討会に焦点をあてて―」という報告は,まず,長期にわたる継続性を持つことなどポートフォリオの原則を六点に整理した。そして,ポートフォリオ検討会(conference)の具体的事例を検討し,①教師が主導するタイプ,②子どもと教師の相互作用により展開するタイプ,③子どもが主導するタイプという,3つのタイプに分類する。 これらの三つのタイプは,「基準準拠型ポートフォリオ」「基準創出型ポートフォリオ」「最良作品集ポートフォリオ」にほぼ対応するものであり,目的に応じて多様な対話のあり方があり得るが,そこでの指導には次のような共通性があることも示された。 それは,子どもの生み出しだ作品の文脈に即して評価が行われること,その評価では子どもの文化が最大限受容されることであり,そして,教師の想定した評価基準の影響と,対話を通してのその基準の修正ということである。 このような指導の全体を通して子どもの学習の主体性が強化され,自己評価が促され,教育評価への子どもの参加の可能性が開かれることが報告では強調された。 この報告をめぐっては,発達段階とポートフォリオ,学習活動とポートフォリオ検討会の時間の調整の問題など,具体的な課題が議論された。 全体を通して,3つの報告の焦点が明確であり,重なりあう点も多く,しかも,フロアからの発言の問題意識も鮮明であったために,討論も活発に展開された。 議論は,ポートフォリオと到達度評価をはじめとするこれまでの日本の教育評価実践との関係,子どもの自己評価と評価の多元性,そこにおける政治性の問題を主軸に深められ,現在,総合学習の評価法として注目を集めているポートフォリオの具体的な可能性と課題,そのゆくえについての見通しやイメージを共有していくことのできる有意義な課題研究であったといえるであろう。 |
||
文責:岸 本 実 (滋賀大学) |
||