     |
| ndex > 年次大会 > 第13回大会 |
||
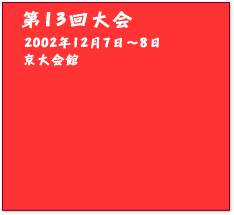 課題研究1: 現代の高校教育において リアリティのある目標づくりとは 課題研究2: 学力論争をどうとらえるか 公開シンポジウム: 評価基準をどう設定すればよいのか |
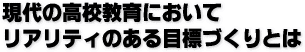 |
|
1.新しいタイプの高校における共通教養の検討 ――商業教育の立場から―― 森 脇 一 郎 (神戸市立六甲アイランド高等学校) |
||
2.探究活動を取り入れた「考える」高校数学授業の試み 片 岡 啓 (上宮高等学校) |
||
3.歴史の見方・考え方(思考力)と到達度評価 松 村 啓 一 (京都府立洛東高等学校) |
||
司会:柏 木 正 (大阪経済大学) |
||
本報告のまとめと課題は以下のとおりである。 |
||
高等学校における教育課程の編成を考える理念として,「国民的共通教養の完成段階」という考え方がある。 しかし,高等学校の学習指導要領の変遷と近年の高校教育政策を見る限り,この理念は掘り崩されてきた。今日,現実の多様化した高校と高校生を前にしてどのような学力を育てることをリアリティのある目標として構想していけばよいのだろうか。 このような問題意識で,3人の高校教員による授業実践報告をもとにした提案が行なわれた。 森脇一郎氏の報告は,普通科の高校と商業科の高校が統合されて新設された,普通科総合選択制とよばれる「新しいタイプの高校」における,商業教育の教育内容・授業づくりを題材として,高校教育における教科教育の目標をどのように構想していくのかという報告であった。 まず,高校教育における商業教育の置かれている現状が報告された。本来,専門教育として職業準備教育の意味を持つのが高校における商業教育であった。 しかし,近年の高卒者の就職率低下という現実の下で,この位置づけは閉塞状況にあるといってよい。 森脇氏の勤務先の「新しいタイプの高校」では,ほとんどの高校生は大学進学をめざし,学校として受験指導も当然強調される。 このような普通科の高校で商業教育を担当する教員として,「職業教育としての商業教育ではなく国民的共通教養に関わる教育という観点」から,高校における商業教育の新たな内容づくりが取り組まれた。 具体的には,「神戸の経済」という学校設定科目における授業実践が報告された。 この「神戸の経済」という科目では,前期に神戸という地域に関して,産業の歴史と現代の都市づくりの諸課題に関する講義形式の授業を受けた後に,生徒は夏休みの宿題として自分で一つテーマを選び,レポートをまとめる。 後期は,研究論文の書き方や発表の仕方についての講義を受けた後に,生徒は各自,自分のテーマについて,問題意識や問題の背景,今後の調査研究の方法等について発表する。 学年末には約1カ月かけて生徒は研究テーマに関する論文をまとめる。 森脇氏によれば,この科目は,商業教育の基盤にある経済学を,「世の中の問題を考えていく学問」としてとらえ,高校生に一種の「研究者ゴッコ」に取り組ませることによって,新たな高校商業科の目標づくりを目ざしたものである。 例えば,神戸空港問題の調査・研究に取り組んだ生徒の発表では,「地域に与える経済効果」に関して,明石海峡大橋の場合をふまえて,「経済予測をそのまま鵜呑みにはできない」とか,成田空港や関西国際空港の先例を基に,「勤務条件のよくない仕事が増えるだけではないか」という考察が展開された。 このような取り組みによって,「現実生活上の諸現象に注目し,それを調査・研究することを通じて,そこに含まれる原理的・原則的・一般的要素や法則を抽出する研究方法」(帰納的研究方法)を生徒に身に付けさせたいと森脇氏はまとめられた。 片岡啓氏の報告は,ほとんどの生徒が大学進学を目ざす私立高校において,探究活動を取り入れた「考える」高校数学授業づくりに取り組んだものであった。 数学教育で「探究活動」を取り入れるといった場合,物理現象や経済活動など現実の数字を取り入れて,これを数学的に立式し,解析するという方法が主流である。しかし,このアプローチは時間がかかるという難点をもつ。 片岡氏の場合は,高校数学の教科書の単元にそった「普段の授業」に付加する形で,数学の理論的な内容を大切にした探究活動を位置づけるという形でとりくまれたものである。 例えば,「指数関数」の単元に付加する形で,「指数関数の威力を知る」ための探究学習として,指数関数と二次関数を比較し,両関数の交点を,いろいろな場合に関して求めてみるという課題を位置づける。 また,「微分法の応用」の単元に付加する形で,「いろいろな関数作り」を探究学習として行なう。これは,それまでに学習した関数を複数組み合わせて,教科書や問題集にのっていない関数を自分で作り,その変化を表現してみるという課題である。 このような数学の授業では,教具としてグラフ電卓が用いられる。手計算では通常行なわない値でのグラフづくりや多数の例の具体的な表示を行ない,そのことによって,試行錯誤をし,仮説・予測の検証を生徒に試みさせることがねらいである。 片岡氏によれば,このようなアプローチは,授業時間数の制約に対応できるという面もあるが,「考える力を育てる道筋が,日常の授業から遠く離れたところにあるのではない」ことを示す意味を持つということであった。 松村啓一氏の報告は,高校の日本史の授業において,「歴史的な思考力」を,「到達目標(評価規準)」として具体化しようとした試みである。 授業実践例として,三内丸山遺跡の墓,副葬品から「縄文時代は平等な社会ではない」という説について考察させる授業と,弥生時代の吉野ヶ里遺跡の「首なし人骨」の解釈を考えさせる授業が紹介された。 このようなテーマの授業によって,生徒に「歴史的な思考力」が身についているのかを評価するために,松村氏によって,次のようなレポート課題が考案された。 テーマ1「次の2つの説の考え方に違いがある。その違いを説明せよ。①三内丸山遺跡の墓,副葬品→縄文時代は平等な社会ではない。②弥生時代=戦争の時代→首なし人骨=戦争の犠牲者」 テーマ2「テーマ1を参考にして,歴史のある説が『定説』になるためには,考え方とデータの使い方のどんな点に注意する必要があるのか述べよ」 テーマ1の課題は,「個別の事実から一般的な事実を引き出す考え方と,一般的な事実から個別の事実を説明する考え方の違いが説明できる」という到達目標に対応する。 テーマ2の課題は,「①個別の事実から性急に一般的事実を引き出したり,一般的事実を個別の事実に性急にあてはめることの問題点を説明できる。②できるだけ多くの事実(データ)を使って矛盾なく説明できた時に『定説』になることを説明できる」という到達目標に対応する。 松村氏によれば,このような課題に即して,ほぼ到達目標を達成したと判断できる生徒は,大学進学を目ざすクラスにおいて約3分の1ほどであったということである。 さて,以上の3つの授業実践報告と参加者から出された質問,意見をもとに,私見もまじえて研究課題をまとめると,以下のような点があげられる。 ① 高校教育の授業改革で強調されている「考える力」を,さらに教科教育の目標論として理論化,明確化していくという課題。 ~森脇氏の例では,「帰納的研究方法」の習得が目標として重視され,「生徒による調査・研究を重視する活動的な学習形態の場合,生徒が身に付けるべき知識や技能というレベルでの具体的な到達目標は,学習が進行していく中で,生まれてくるのではないかと考えている」(森脇氏)という意見が出された。 確かに生徒の選択した各自の研究テーマに即した具体的な事実,データ,その収集方法などの目標は,生徒の調査・研究の進行とともに具体化する側面が強い。 しかし,「神戸の経済」の前半の講義内容に含まれている経済学の諸概念,カテゴリーを,後半の生徒の調査・研究の中でどのように活用させ,深めさせていくかという視点からの到達目標の設定も合わせて理論化されていく必要がある。 例えば,「経済効果」というカテゴリーで,集めたデータをまとめていくためには,生徒にどのような知識・理解が必要になるのかを,事前に到達目標として明確にしていくことも課題となるだろう。 片岡氏の「考える高校数学授業の試み」において付加的に取り入れられている「探究活動」の課題は,「関心を持って考える」「学んだことの理解を深める」という位置づけがされている。 この点をさらに,「試行錯誤をし,仮説・予測の検証を生徒に試みさせる」ことは,目標論として,いかなる数学的思考を生徒に求めるもので,「普段の授業」での到達目標とどのような関係にあるのかという観点から,整理していくことが課題となる。 松村氏の「歴史的な思考力」の目標設定と評価方法に関しては,参加者から,「生徒のメタ認知を評価している問題なので難しいのではないか」「『歴史的な思考』を『技能』という言葉で整理して,授業目標を設定することの理由は何か」という意見・質問が出された。 この問題は,以下のような課題として考えられるのではないだろうか。 歴史教育における演繹的思考,帰納的思考を歴史の様々な主題の具体的な内容に即して,生徒に実行・訓練させる到達目標を複数設定するレベルと,それらの思考形態を,歴史研究の方法として生徒に一般化させ,自分自身の思考プロセスを反省,検討させる目標を設定するレベルの2つの層で,年間のカリキュラムを構想することが課題となるだろう。 ② 教科教育における「考える力」の目標の具体化を考えるために,教育課程での位置づけや大学入試制度との関係を考えるという課題。 ~3つの実践報告に関して,「『受験』と『探究』との折り合いをどのようにつけているのか」という質問が参加者から出された。森脇氏からは,「神戸の経済」のような生徒が自分で取り組んだ研究をレポートにまとめるという学習の成果は,近年各大学で導入・実施されてきているAO入試の形態では,評価されるケースが増えてきているという回答があった。 片岡氏からは,「普段の授業」時間を大幅に削らない形で,「探究学習」を位置づけているので,大学入試との矛盾は少ないことと,「探究学習」に取り組むことが大学入試にストレートに役立つという関係ではないが,そのような課題に取り組むことによって「考える力」が身についた生徒が,大学に進学してほしいと思っているという回答があった。 松村氏からは,勤務校の生徒で日本史を大学入試のために必要な科目として勉強している者は少ないが,センター入試として受験する生徒,小論文形態の日本史の入試を受ける生徒に対しては,それぞれ補習という形で指導しているという回答があった。 このように3つの実践は,大学入試制度との関係で矛盾が少ない形態で実践が進められていることがわかる。 課題は,その高校としての教育目標づくりの論議が教師集団として行なわれているか,そして,学校の教育課程の全体計画の中で,それぞれの教科の「考える力」の授業がどのような関連をもって位置づくのかということである。 実際には,多くの高校では,教科の枠を越えて教育目標の具体化を論議するような体制がつくられていることは少ない。 しかし,3氏の実践報告を聞いて,それぞれ教科としての独自性はあるが,教育目標としての共通性も非常に感じさせる内容であった。 そのことは,例えば,演繹的思考,帰納的思考,研究の方法といった目標の具体化を,それぞれの教科の独自性と相互関連を見通して進めていくという課題を提起している。 ③ 「考える力」という教育目標の実現に不可欠な,生徒の学ぶ意欲の育成という課題に学校としてどのように取り組んでいくかという課題。 ~例えば,松村氏の実践は,勤務校のⅡ類クラスという大学進学中心のクラスでのみ行なわれた。 松村氏によれば,必ずしも大学進学を目ざさない生徒のいるクラスにおいても,かつて同様の課題について「考えさせる授業」を試みたことがあるが,他の生徒の考えた説を写して,自分で考えようとしない生徒もいたため,その後断念したということである。 また,最近では,評定で2を取るだけで満足して,それ以上努力しようとしない高校生も多いという事実も,松村氏からは紹介された。 3氏の実践はいずれも大学進学を目ざす生徒集団を対象としたものであった。 「考える力」という教育目標は,すべての高校生に対するものであるはずである。勉強を諦めている高校生に対して,どのような形態の授業実践が有効であるのかは,引き続きこのテーマの研究の大きな課題となる。 |
||
| 文責: 鋒 山 泰 弘(追手門学院大学) | ||