     |
| ndex > 年次大会 > 第13回大会 |
|||||||||
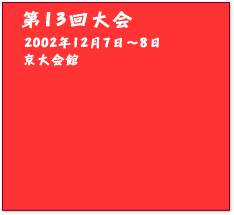 課題研究1: 現代の高校教育において リアリティのある目標づくりとは 課題研究2: 学力論争をどうとらえるか 公開シンポジウム: 評価基準をどう設定すればよいのか |
|||||||||
|
|||||||||
1999年以降、幅広い人々を取り込んで展開されてきた「学力論争」(いわゆる「学力低下論争」)をどうとらえるかについて、3つの異なる立場(歴史的・教育方法学・教育社会学)から報告がなされました。 まず、八木会員が、「起点・背景・歴史的経緯からみた今回の学力『論争』の位置と課題」と題して、歴史的な議論を踏まえた報告を行ないました。 そして、「教育課程の構造」や発達論の視座から、今回の「学力論争」をとらえることの重要性について言及しました。 まず、今回の学力論争において、「学力」という言葉がさまざな意味をもって使われていることに言及しました。 たとえば、 ①簡単に測定できる知識や理解が挙げられました。 その上で、井ノ口淳三会員の次のような言葉をひき、「学力」という言葉を捉える上での基本的姿勢を提示しました。 「同じ『学力』という言葉を使いつつ、それぞれの主張が誰に対して何を求めたものであるのかが明らかになれば、教育改善の手がかりを得ることは可能であろう」。そこで、「学力」を論じる際に、「なぜ、誰が、何を、どのように」論じているのかという観点を踏まえて、どういう枠組みにつなげていく必要があるかを判断することの重要性が述べられました。 その後、今回の学力論争は、新学習指導要領の制定・実施に端を発するものであることに触れたうえで、実際には「学力競争」(旧学力)と「ゆとり」(新学力)とに親和性が見られることが指摘されました。 ここでは、苅谷剛彦らがいわゆる「旧学力」と「新学力」の双方を重視する立場に立脚しているとしたうえで、八木会員自身は、「旧学力」と「新学力」のどちらも大切だというのみでは不十分であり、むしろ、どちらも教育的発達の検討を要するということを主張した。「学力競争」と「ゆとり」はどちらも必ずしも矛盾しない親和性があって、両者の対立が本質的なものかどうかは疑わしいとされた。 その根拠として4つのことが挙げられました。 ①教育課程審議会での三浦朱門の言葉 です。 そのうえで、こうした一見二極分裂ないし矛盾しあうものの親和性や同居は、実践史的な経緯からみると、「学力競争」の歴史的発生と「童心主義」が同根のものであった事実と重なっているのではないかとの見解が提出されました。 その後、戦後の学力論争史を、①戦後初期の青木誠四郎らに代表される論争、②1960年代の勝田守一の論、③1975年の坂元忠芳・藤岡信勝の論争によって概観し、今回の学力論争と驚くほど類似した論点が存在することが述べられました。 そして、実践レベルではどうなっているのかについて、実践史に学びながら検討することの重要性が提起されました。 そのうえで、教育課程の構造に位置づけて議論しあうことの重要性が強調されました。 なかでも、「教育的発達の視点を踏まえた教育課程の整理・精選・再編成の重要性」が提起されました。 そして、こうした視座を具体化したものとして、八木会員と中内敏夫会員の手による「教育課程の構造表」が示されました。 次に、山崎会員から「人格論・指導論を視野に入れた学力論議を」と題して、教育方法学的な視座から報告がなされました。 山崎会員は、まず、現在の学力論争には人格論や指導論が欠けていることに言及した上で、より具体的な授業づくりの課題をふたつ指摘しました。 ①意味や理屈の抜け落ちた学習と、その結果としての「日本型高学力」状況を克服することそして、こうしたふたつの課題を克服するためには、①と②を別々に追究するのではなく、①を通して②を実現させていくことの重要性が説かれました。 すなわち、わかるということ(知識・理解)を通して楽しい授業(関心・意欲・態度)を創造していくべきだという主張であり、「学力の形成」と「人格の形成」を一元的に捉える主張でもあります。 その後、山崎会員は、現在の「学力」論争がこのような授業づくりの課題に応えるものになっているかという観点から、以下の3つを指摘しました。 ①高得点者層のレベルダウンがとりざたされていることです。 これらの問題を指摘した上で、山崎会員は、「学力の形成」と「人格の形成」を一元的に把握した指導論を提起しました。 その際、「技術知」と「思想知」を対比させ、「思想知」形成を促すことの重要性が説かれました。「技術知」とは「道具としての知、所有者であるはずの〈私〉とは別のもの」であるのに対し、「思想知」は「〈私〉の人格の中心にあって、〈私〉の生き方を支えたり、ゆがめたりするもの。絶えず〈私〉に反映するような知のあり方」として位置づけられました。 そして、「思想知」の形成を促すためには、以下の2つの視座が必要であると述べられました。 すなわち、 ①学習指導要領に従った単なる目標分析ではなく、学力の内容にまで立ち入った論議の必要性。その際、1970年代の鈴木正気による自主教育運動と、中内敏夫の「目標づくりの組織論」における「地域住民運動」とに、示唆が含まれていることが指摘された。との提起がなされました。 その後、久冨会員が、「『学力問題』の質的側面と階層性―教育社会学グループ調査の提起するものの検討―」と題して、教育社会学の立場からの見解を提起しました。 久冨会員は、東京大学の苅谷剛彦らが行なった近年の学力調査を取り上げ、それに関する問題点を指摘しました。 苅谷らの調査を取り上げた理由は、4つあるといいます。 第一に、今回の学力低下論争における苅谷らの「活躍」があること、第二に、学力低下を指摘し、その要因には「ゆとり教育」政策があることを主張している点では他の論者と重なる部分があるとした上で、第三に、家庭学習時間の減少等、実証的なデータを素材に議論を立て、「階層間格差拡大」を指摘してきたという独自性、さらに第四に、苅谷が独自の「学業達成調査」の実施結果報告を行なっているという点です。 これらを踏まえた上で、報告においては、まず苅谷らが2002年に発表した調査報告について詳述されました。 苅谷らの調査の特質として、次の3点が挙げられました。第一に、80年代に行なわれた調査とよく似た「国語」「算数・数学」の問題で「基礎学力測定テスト」を実施して、過去との比較によって「学力低下」をデータ的に明らかにしたということ、第二に、学力テストと生活質問紙調査を同時に実施することで、生活的背景(通塾や文化的階層、親の学歴)から学力テストの平均点の格差の問題を追究していること、第三には、子どもへの質問とクラス担任への質問紙調査によって「子どもの学習達成と教師の教育のやり方」の相互関連を分析しているということです。 その後、こうした苅谷らの一連の結果報告に見るいくつかの問題点が指摘されました。 第一に、1990年代の教育政策を「ゆとり教育」という一つのスローガンのもとに捉え、それが日本の学校教育の日常を構成しているというやや一面的な現実把握を前提としており、したがって「ゆとり教育」政策が「学力低下」を生み出したという仮説を実証することにのみ力点が置かれているということです。 一方、久冨会員は、1990年代とはどのような時代であったのかについて、長期不況のなかの「動揺・混迷」の時代という観点から考察することの重要性を提起しました。 第二に、1980年代の学力テストを用いる際に、「学力とは何か」「基礎学力とは何か」についての議論を等閑視しているということが指摘されました。 それは、すなわち、個々のテスト問題がどういう学力を反映させたものなのかということを顧みずに、結論づけることはできないのではないか、という主張でもありました。いま求められている学力とはどのようなものなのか、どう測定されうるのか、という「学力問題」の質的側面を考慮すべきことに久冨会員は言及しました。 第三に、先述したような単純すぎる政策・現実把握に対応して、苅谷らは80年代をB.バーンステインのいう「見えるペダゴジー(子どもにとって目標が明示されているような実践)」として位置づけ、それを階層間格差縮小の方法として推奨するという単純化された結論が導き出されていることを指摘しました。 これに対して、久冨会員は、80年代の日本における教育の特質を苅谷とは異なる見方で洗い出しました。 すなわち、80年代の日本の教育はバーンステインのいうところの「見えるペダゴジー」の典型と言えるのかということが問題提起された上で、むしろ、「社会的基盤の統制部分」での競争的関係が過度に強く、それによって「学校知識の構成・意味づけ」が影響され、父母や子どもたちに対しても競争的意味づけを与える時代であったのではないかという見解が提出されました。 そして最後に、こうした「日本的状況」の分析を抜きに、「ペダゴジーと階層」を一般論で語ることはできないのではないかということが指摘されました。 以上の3人の報告を受けての討論では、近年の学力調査における問題のひとつひとつは子どものどのような能力を測っているのか、学力調査をどう構成するかは何を目標とするかに深くかかわっているのではないか、さらに目標づくりに際しては発達段階に応じてどのような教科が重要となると考えるのかなどが論点となりました。 これらの問題に対して早急な結論が得られたとはいえませんが、「学力低下」という言葉は、過去との比較をもとに述べられるものである一方、それを現在求められている学力との比較によって検討しなければならないところに「学力論争(学力低下論争)」の困難さが存在するということが浮き彫りになりました。 このことは、学力調査における「問題づくり」から吟味していかなければならないということを意味しており、それはさらに「目標づくり」や「教科の構造」を再検討することと深く結びついているということが鮮明になったものと思われます。 |
|||||||||
| 文責:谷 川 とみ子 (京都大学大学院) |
|||||||||