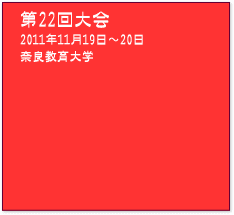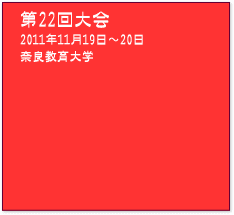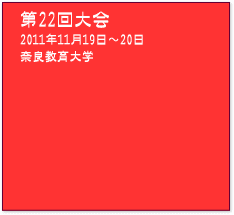
�ۑ茤���P�F
�@����ڕW�E�]���Ǝw���̌���Ɖۑ�
�ۑ茤���Q�F
�@���t����ɂ�����ڕW�ƕ]���̉ۑ�ƓW�]
���J�V���|�W�E���F
�@�V�w�K�w���v�̂ɂ�����
�@�@�@�@�@�@�@����]���͂ǂ��ς�邩 |


�@����ڕW�E�]���Ǝw���̌���Ɖۑ�
�@�@�\���ȋ���̗��ꂩ��\ |
| �i��E�R�[�f�B�l�[�^�[�F |
�x�@ �@�N�@�v�i�R����w�j�C�c�@�� �k�@���i���s��w�j |
| �ҁF |
�@�� �p�@�^�i�_�ˏ������q�w�@��w�j
�u�Z���E���w����̗��ꂩ��v�@
�߁@�c�@�ց@�q�i���S���q��w�j
�u�ƒ�ȋ���̗��ꂩ��̎�̖���N�v�@
���@�� �@�@���i������w�j
�u���p����̗��ꂩ��\�w���`�V�сx�Ɓw�ӏ܁x�̕]������Ԃ̉ۑ�\�v |

�@
�u�ڕW�ɏ��������]���v���w���v�^�ɓ��������10�N�ɂȂ낤�Ƃ��Ă��錻�݁C�]�����w���̉��P�ɂǂ̂悤�ɐ������Ă������Ƃ������Ƃ��C���炽�߂Ė���Ă��܂��B�{�ۑ茤���́C�]�����w���̉��P�ɐ�������̓I�Ȏ肾�Ăɂ��āC���ȋ���̗��ꂩ�猟�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Đݒ肳��܂����B
�@���̖ړI�̂��ƁC�܂��Έ�p�^������C�u�Z���E���w����̗��ꂩ��v�C1990�N��ȍ~�̋���ڕW�E�]���_�̓W�J��f�`���C�ŋߐ����Ă���ۑ�Ƃ�������z���邽�߂̕���ɂ��Ę_���܂����B�Έ����ɂ��C���ł�90�N��ȍ~�C���Ƃ̌`������]���̔ώG������莋����Ă������̂́C����炪�ŋ߂ɂ����Ă���������Ȃ��\��������Ƃ����܂��B���Ƃ���90�N��ɂ́u�V�����w�͊ρv�̂Ȃ��Ŗ������^�̎��Ƃ����ڂ𗁂т����C�ۑ�Ƃ��āC���Ƃ̌`���i���c�������͉���������グ�i�W�c�����j���܂Ƃ߁j���Ȃ��邾���ɂƂǂ܂�C�T�O�`�����s�\���ɂȂ�X��������܂����B�܂��C�������^�̎��Ƃɂ�����]���ɂ��ẮC�q�ǂ��̔�����s���̊ώ@�����ƂɁu���w�I�ȍl�����v��]������ꍇ���������߁C�����ł́C�w���ƕ]�����������ȏ�ԂŁC�w���̕]���������������ł���Ƃ̎w�E���Ȃ���܂����B�ŋ߂́u�m���Ȋw�́v���d�����铮���̂Ȃ��ł́C�V���ȓW�J�Ƃ��āC�@���ꊈ���̏[���C�A�Z���E���w���������E�ɂ����Ďg�������C�B�u�w�K�����ƕ]���̈�̉��v�Ȃǂ�������悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B����ɑ��āC�Έ����́C�Z���E���w�ɂ�����iPISA�^�j�lj�͂̈琬�Ɏ��Ƃ��⏬�������_�C�u�w�K�����̕]���������v��u�w�K�ւ̏]���I�Ȏ�̐��Ǝ��ȐӔC�v���Ăэ��݂��˂Ȃ��Ƃ����_����_�Ƃ��ċ����܂����B���Ƃ̌`������]���̔ώG���Ɋׂ�Ȃ����߂ɁC�Έ����́C�u�l�������Ƃ��ĕۏႷ�ׂ��v�w�͂Ƃ����l�������N����ƂƂ��ɁC���ȓ��e�̋ᖡ�����ڕW�̂�������l���Ă������Ƃ��s���ł���C�]�����w���ɐ������Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��ƂȂ̂������炽�߂Ė₤�Ă����K�v�����邱�Ƃ��N���܂����B
�@���ɁC�ߓc�֎q������C�����{��k�Ђ̂Ȃ��ŋ���̂������₢�Ȃ������Ƃ̏d�v�����w�E������ŁC�u�ƒ�ȋ���̗��ꂩ��̎�̖���N�v���s���܂����B�܂��C�w�K�w���v�̖̂ڕW���ǂ̂悤�ɍl���Ă������ɂ��āC�ƒ�Ȃɂ����Ắu�����҂̈琬�v�Ƃ������_���d�v�ł���C�w�K���e�Ƃ��āu�q�g�v�u���m�v�u�R�g�v���܂݂����̂ł��邱�ƁC����ɉƒ�Ȃ͂��������ߑ�w�Z�̐��i�Ƃ͈قȂ鑤�ʂ�L���邱�Ƃ��l���ɓ����K�v������ƒߓc����͎w�E���܂����B�Ƃ��ɁC�ߔN�̉ƒ�ȋ���ł́C��b�I�Ȓm���E�Z�\�̊w�K�Ɩ������w�K�Ƃ�����̕���������Ƃ��C�]���ɂ��ẮC�y�[�p�[�e�X�g��ϓ_���߂���i�]���C���\�E���|�[�g�Ȃǂ��s���Ă��邱�Ƃ��ӂ܂�����ŁC�ߔN�́u�^���̕]���v�_�ɂ��Ẳۑ肪�w�E����܂����B���Ƃ��C�u�^���̕]���v�_�ɂ�����u���A�����v�́u����v�i�����̎v�l�j��v�����Ă��邪�C�ƒ�Ȃɂ����ẮC�q�ǂ��ɂƂ��Ă̈Ӗ��C��������C���Y�e�[�}�̎q�ǂ��ɂƂ��Ă̏d�v���ɏœ_�����Ă�Ƃ����_�ɈႢ������̂ł͂Ȃ����B�ߓc����ɂ��C��l�ЂƂ�̎q�ǂ������������Ă�����ʼn��l�̂�����i���Ƃ��C���ː����߂����̖����ǂ����邩�Ȃǁj�C�����Ă�����ŏd�v�ȉۑ��I�ԂƂ����_���ƒ�ȋ���ɂ����Ă͏d������Ă����Ƃ����킯�ł��B�܂��C�ߔN��N����Ă���p�t�H�[�}���X�]���ɂ��ẮC���̊w�K�ߒ��̓����Ƃ��Ďw�E�����u�n���I�͕�ɂ��p�t�H�[�}���X�̗����I���B�v�Ƃ������ƂƁu�ړI�ӎ��I�ɑΏې��E�ɓ���������v�Ƃ������ƂƂ͂ǂ̂悤�ȊW�ɂ���̂��C�܂��q�ǂ������́u���ȕ]���v�Ƌ��t���쐬����u���[�u���b�N�v�͂ǂ̂悤�ȊW�ɂ���̂��C�ƒ�Ȃɂ�����p�t�H�[�}���X�ۑ�Ƃ͈�̂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��Ȃǂɂ��Ďw�E���Ȃ���܂����B����܂łɁu�w�K�̋������v�Ɓu�����̕]���v��͍����铮�������������Ƃ܂���ƁC�u���݁E�����̕]���̂�����Ɓv�������ɂ��肾���Ă����̂��C���̂��Ƃ��ۑ�ɂȂ��Ă���ƒߓc����͎咣���܂����B
�@���̌�C����������C�u���p����̗��ꂩ��\�w���`�V�сx�Ɓw�ӏ܁x�̕]������Ԃ̉ۑ�\�v�Ƃ����e�[�}�ŁC�}��H��Ȃɂ�����u�w���ƕ]���̈�̉��v�̂�����ɂ��Ę_���܂����B�܂��C�w�Z����ɂ�������Ԃɂ��Č��y���Ȃ���܂����B��̓I�ɂ́C���ˎs�̌������w�Z10�Z�ɂ����ċ���60����Ώۂɏ��������g���s�����A���P�[�g�����̌��ʂ�������܂����B�}��H��Ȃ́u���Ƃ̎��g�݂₷���v�ɂ��Ắu�����炩���g�݂ɂ����v�Ƃ�����41���ɂ̂ڂ�ƂƂ��ɁC�}��H��́u�]���̓���v�ɂ��Ắu����Ȃ��v�Ƃ������O���ł��������Ƃ����炩�ɂ���܂����B�Ƃ�킯�C�]���̊ϓ_�i�u�S�E�ӗ~�E�ԓx�v�u���z�ƍ\�z�̔\�́v�u�n���I�Z�\�v�u�ӏ܁v�j�̂�����ԓ�����̂��ƁC�u�ӏ܁v�������鋳����48���ɏ�����Ƃ����܂��B�܂��C���e�i�u���`�V�сv�u�G�◧�̂ŕ\�킷�v�u�ӏ܁v�u���ʎ����v�j�Ɋւ��ẮC�]��������Ȃ��̂Ƃ��āu�ӏ܁v�i43���j��u���`�V�сv�i30���j����������ꍇ�̑������Ƃ����炩�ɂ���܂����B�u�w���ƕ]���̈�̉��v�ɂ��ẮC�u�����v�u�悭�v���g��ł���Ɠ�����l��21���ł���C�u���ΓI�ɂ́C�ϋɓI�Ɏ��g�܂�Ă���ł͂Ȃ��v�Ƃ���܂����B�Ƃ�킯�C�u�����I�]���v�̎��{�ɔ�ׂāC�u�f�f�I�]���v�u�`���I�]���v�̎��{���͒Ⴍ�C�u���e�I�ɕs�\���ł���v���Ƃ��w�E����܂����B�]��������ł���Ɓu�w���ƕ]���̈�̉��v�����������邱�Ƃ͖��炩�ł���C�Ƃ��Ɂu�ӏ܁v�́u�w�����@����ѕ]�����@�v�̍\�z���u�ً}�̉ۑ�v�ƂȂ��Ă���ƁC�������͏q�ׂ܂����B���p�Ƃ͎�ϓI�E�l�I�Ȃ��̂ł���Ƃ���������������̂́C�ߋ��ɒ~�ς��ꂽ�\���Z�@�ȂǂɊw�тȂ��甭�W���Ă������̂ł����邱�Ƃ��l������ƁC�\���̎��I�Ȓ��g�̈Ⴂ�𖾂炩�ɂ��Ă������Ƃ����߂���Ə������͎w�E���܂����B
�@�ȏ�̔��\���ӂ܂��āC���^�������s���܂����B�܂��C���������w�K�w���v�̂Ɏ������ڕW���ǂ̂悤�ɂƂ炦��̂��C�ᔻ�I�ɖ₢�Ȃ������Ƃ��d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����_���߂����Ĉӌ����o����܂����B�܂��C�]���Ɋւ��ẮC�u�^���̕]���v�_�ɂ����鉿�l�̂���ۑ�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��Ȃǂɂ��ċc�_���W�J����܂����B����ɁC�ڕW�Ɋւ���āC�u�l�������Ƃ��Ă̊w�͕ۏ�v�Ƃ������_����݂�ƁC����������Љ�Ɗ֘A�̎ア���̂̈����͂ǂ��Ȃ�̂��C�\����������ɋ���������ǂ��l����̂��Ƃ������_�ɂ��Ă��c�_���Ȃ���܂����B��̓I�Ȋw�͂̒��g�ɂ��āC���ȓ��e���ӂ܂��Ė₢�Ȃ����Ă������Ƃ̕K�v�������炽�߂ĕ�������ƂȂ�C�ڕW�ƕ]���̂�������߂��锒�M�����c�_���W�J���ꂽ�Q���Ԃł����B�@ |
���ӁF�@��@���@�Ƃݎq
�i���s�����w�j |
|
|