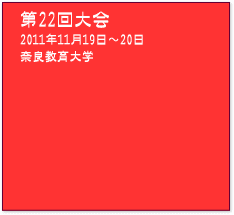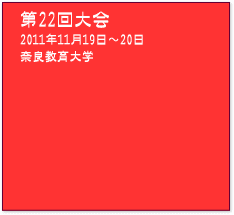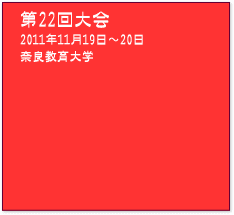
課題研究1:
教育目標・評価と指導の現状と課題
課題研究2:
教師教育における目標と評価の課題と展望
公開シンポジウム:
新学習指導要領において
教育評価はどう変わるか |


新学習指導要領において教育評価はどう変わるか
|
| 司会・コーディネーター: |
狩 野 浩 二(十文字学園女子大学)
赤 沢 早 人(奈良教育大学) |
| 報告者: |
西 岡 加名恵(京都大学)
「『目標に準拠した評価』の充実をどう図るか」
田 中 容 子(京都府立園部高等学校)
「生徒の学習意欲を引き出す授業
――パフォーマンス評価を生かして――」
植 松 利 晴(奈良市富雄第三小中学校)
「小学校における評価の実際と課題
――社会科の学習指導と評価の在り方――」 |
|
|
|
|

学習指導要領の改訂に対応して新しい児童・生徒指導要録が作成されることを受けて,学校現場での教育評価がどのように変わるのか。とりわけ,新しく提案された「学習評価」やパフォーマンス評価という考え方によって,児童・生徒の学習の過程と結果の「何」が評価されようとしているのか。本シンポジウムは,これらの問いを理論と実践の両側面から検討し,教育評価の現状・課題・展望について考えることを趣旨として開催されました。まず,赤沢早人会員から上述の趣旨が説明された後,3人の報告者から報告がありました。
西岡加名恵会員からは,「『目標に準拠した評価』の充実をどう図るか」と題して,現在の変化に関する理論的な整理と,今後の発展に向けた提案がなされました。まず,新学習指導要領で習得・活用・態度という3要素の学力像が示された背景にある,国内外での様々な新しい能力概念や,学習研究の発展が説明されました。それを踏まえて,知識や技能は,バラバラなものとして習得されるだけでは不十分であり,互いに関連付けられ構造化される形で深く理解され,自分のものとして現実世界で使いこなせる必要があると指摘されました。このような学力観の転換を反映して,知識・技能を活用するための思考力・判断力・表現力が強調されており,これらの力を保障するための有効な評価法としてパフォーマンス評価が紹介されました。パフォーマンス評価は,広い意味では客観テスト式以外の評価方法を指し,より狭義には,知識や技能をリアルな文脈で使いこなすことを求めるパフォーマンス課題を指します。そしてその課題は,教科を貫く「包括的な問い」に対応するものです。このパフォーマンス評価で用いるスタンダードについて,評価の比較可能性やカリキュラム適合性を高める,質の良いスタンダードを作るために,教室や学校を超えた公共の議論の重要性が主張されました。スタンダード開発を進め,各教科でパフォーマンス課題を位置づければ,<新しい能力>として求められるような力の大半は保障していけるだろうという提案でした。ただし,価値観,行動,汎用スキルと言ったものの育成は学力評価論の枠に収まらないものとして指摘され,今後の研究課題とされました。
田中容子会員からは,具体的なパフォーマンス課題の事例として,京都府立園部高等学校英語科の実践が紹介されました。園部高校英語科では,各学年末までに生徒に育てたい力の質的内容を教育目標として共有し,それをもとに個々の教員が自分なりの授業を工夫するスタイルをとっていました。「生徒の学習意欲を引き出す授業―パフォーマンス評価を生かして―」というタイトルにあるように,田中会員が実践したパフォーマンス課題は,学校・クラス内の生徒の意欲差と学力差を乗り越えて全員が参加し学習するために効力を発揮していました。例えば,ある物語をクラス全員で分担し,自分が分担した個所について英語を熟読して絵に描き,その絵を持って語るといった,協働が必要なパフォーマンス課題がありました。各生徒は,自分が休めばクラス全体の読書会がなりたたないため参加するようになったとのことです。中学校の時に学習に困難を抱えていた生徒が,高校の教科書を使って回復できたという報告でした。また,学習への意欲が極端に低かった生徒たちが,習った英語を使ってさまざまなパフォーマンス課題を重ねて,読み取った物語を自分なりの英語で綴りなおす力を身につけていく姿が,実際の授業場面の映像を交えながら紹介されました。
植松利晴氏からは,「小学校における評価の実際と課題―社会科の学習指導と評価の在り方―」として,目標に準拠した評価の充実を図るために必要となる工夫と改善として,次の3点が提起されました。それは第一に「評価規準の設定と活用」です。日常の評価場面で本当に生かせるルーブリックをつくるために教師間で議論を行ったことが,教師が子どもを見とる目を育て,児童には学習内容や自分の状況への自覚を促したことが報告されました。第二に「言語活動の充実と評価場面の設定」です。指導要領を受けて言語活動を重視する際,評価する言語活動を「学習問題を設定する場面」「社会的意味を考える場面」,「指導に生かす評価場面」「記録に残す評価場面」といった場面設定で焦点化したそうです。そして第三に「授業改善に生かす工夫」です。単元構造図を書くことで,学習する事実の社会的意味を教師が認識し,指導場面に生かす取り組みが紹介されました。
以上の報告の後,フロアからの質問と応答がなされました。
西岡会員には,指導要録の4観点を学力評価計画の3次元モデルに位置付けてよいのかという質問,観点別評価の重みづけの方法への質問,校長会からの提案は実践への強制力になってしまわないかという危惧が出されました。その答えとしては,次のような指摘がなされました。4観点については,とくに関心・意欲・態度に関して,指導要録改訂について議論したワーキンググループの中でも反対したが,現実には残ったので,その枠の中で実行可能な方法を考えている。重みづけは,教師の理想とされている重みづけについてアンケートで調べて平均値に近い数値をとった。校長会が持つ強制力は否定できないだろうが,教育委員会が主体ではないことには注意しておきたい。なるべく双方向の議論を重ねながら作成しようとしている点に意義がある。西岡会員としては,数値ではなく,具体的に評定3の生徒に求められる学力とはどういうものなのかといった,より実質的な議論をすべきだと考えているという応答がなされました。
田中会員に対しては,ルーブリックの最低レベル1も肯定的な文章で書かれているのが良いという指摘,一般的なアチーブメントテストとパフォーマンス課題との関連についての質問,グループでの共同学習を英語の目標としてはどう位置付けているのかという質問,そして授業に参加しない生徒に対してどのような指導をするのかという質問がありました。これらへの答えとして,まず,ルーブリックは生徒にも提示し,教師と生徒が共有する指標であるという説明がありました。ルーブリックを明示することは,生徒のモチベーション向上にもなるそうです。また,パフォーマンス評価は純然な評価として用いるのではなく,教師が援助する学習活動として用いているということでした。共同で学び合う力については,評価の記述語の中に位置づけるのではなく,グループ作業が必要なように授業を作っているという説明がありました。これは,参加しない生徒に対する対応という最後の質問への答えでもありました。例えば,1人1文担当するときも,4人グループで考えさせるといったことです。あくまでも目標は,英語の力を伸ばすことであり,そのために有効な手立てとして共同での学習を多く取り入れているそうです。
植松氏には,社会科の取り組みが小中学校全体の取り組みにどのように関連しているのかという質問がありました。それについては,他教科との連携という横のつながり,他学年との関連という縦のつながりを考えていることが説明されました。とくに,幼稚園児との関わる中で子どもの遊びの中にある科学的な認識や表現に気付いた経験を基に,それを潰さず育み,「思考力・判断力・表現力」につなげていきたいと話されました。
また,全体に関わる問いとして,目標設定に関する議論,基礎の学び方についての質問がありました。西岡会員は,パフォーマンス評価と知識を測る筆記テストを組み合わせる必要があること,応用に取り組むことによって基礎を学ぶ意義がわかることを強調されました。田中会員は,パフォーマンス課題の中に英語の文法的目標を入れ,具体的な作業の中で習熟の深まりがあること,また,入学時には英語学習入門期にありがちなつまずきを生徒全員に克服させることを重視していると説明がありました。植松氏も基礎的な学習の重要性に同意し,子どもの学ぶ意欲を高めるために学ぶ意義を実感させること,また,学び方を学ぶ場づくりに取り組んでいると報告がありました。
他には,現場でパフォーマンス評価を少しずつ実践しているという参加者からの質問がありました。パフォーマンス評価は見えない学力を可視化したり,総合的な力を見るものだったり,子どもの力を把握し,改善に仕えるものだったりすると思っていたが,今日の話を聞いていると,観点別評価の4観点で評定をつけやすくする方法の1つのように聞こえて,少し残念な気持ちになったという意見でした。これに対して西岡会員は,評価や成績づけは必要であり,それを真正面から受け止めてどう取り組んでいくかを考える必要もあると応答されました。評価を軸にすることで,授業改善につながるという点に注目してほしいとのことでした。ただし,学力評価に関する議論の限界も認識しておく必要があり,生徒の価値観を成績に入れてはならないことに言及されました。それは,前日の課題研究において鶴田敦子会員が「社会を変革する力こそをつけるべきではないか」という発言をされたことに対する応答でもあり,社会を直接的に変革しようとする行動力までは,学力の範疇に入れないという立場をとっているという表明でした。
最後に,狩野浩二会員から,本シンポジウムのまとめがありました。かつての問題解決学習のよさと系統学習,それぞれのよさを思い出して昇華させる必要性が話されました。また,パフォーマンス評価については,かつて勝田守一が示した学力モデルにおいて,認識の能力と,表現・感応の能力が位置づけられたことを思い出す必要があるだろうと提起されました。つまり,表現することは子どもの心を開放することであり,豊かな実践提案からそれを改めて感じたということでした。 |
|
|