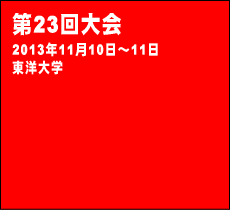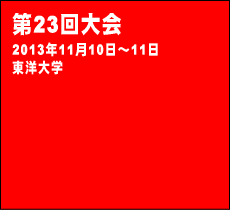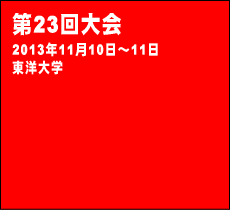
講演会
生活指導研究の成果と課題
課題研究
学校の受容過程と「教える」ということ
公開シンポジウム
教育の成果をどう検証するか |

課題研究
学校の受容過程と「教える」ということ
―歴史的様態の叙述について―
|
| 報告者: |
木村 元(一橋大学)
「学校の受容過程と『教える』ということ」
大西 公恵(一橋大学・大学院)
「読方教育における認識の問題
−1930年代の高師附小における
国語教育の再構築過程−」
本田 伊克(宮城教育大学)
「教科数学における目標・内容論の展開
−1930-1940年代の日本中等教育数学会に
おける議論に着目して−」
|
| 司会・コーディネーター: |
山根 俊喜(鳥取大学)
木村 元(一橋大学)
|
本課題研究では,まず木村元会員によって次のように研究の全体像が整理されました。そもそもこの研究は『日本の学校受容 教育制度の社会史』(木村元編著,勁草書房,2012年)をベースとし,こんにちの学校システムを支える基盤について考察するべく,積み上げ式の学校体系に基づいて人間形成を行うこと自体の歴史的な性格を明らかにすることが目指されました。ここで,ペタゴジーと教育人口動態史を両輪とすることで,教育制度の社会史という新しいカテゴリーが提示されます。そして,教育制度の社会史という新しいカテゴリーを通じて,歴史学と制度研究や法令史研究の間にある実践史研究に枠づけが行われました。
そのための具体的な問いとして「日本の学校はいつ社会に受け入れられたのか」という問いが設定されました。ここで,学校を受け入れるとは,通説のように義務教育機関への就学率の上昇を意味するのではなく,義務教育を終え,受ける義務がない教育,すなわち初等教育を補足するような初等後教育を人々が当たり前のように受ける時期を意味します。このような視点に立つと,受容された時期は1930年代になり,学校が定着した結果,学校システムの内部の変化が生じ,ペダゴジーにも変化が起こります。こうしたペダゴジーの特徴を見出すことが目指されました。こうした1930年代の経験が,戦後確立する「学校化社会」にどのように繋がるのかが考究されました。
特に,従来の研究で検討されてこなかった,教科による人間形成という枠組みが問われる過程と実相を学校の中で捉えるべく,以下,国語教育と学校数学が事例として検討されました。これにより,学校知識を媒介にした社会と学問,そして実践の往還と,学問を教育の言葉へと創造的に教師が作り直すという,相互関係が浮き彫りになります。このことを具体的に描くために,国語教育では全国小学校訓導協議会,学校数学では日本中等学校数学会といった中間団体が着目されました。
以上に示された全体像の下で,大西会員によって,1930年代の国語教育の読方に着目した報告が次の通り行われました。国語教育では1930年代において,文の本質に迫る形象理論と解釈学を学問的基礎として読むこと自体が追究されました。報告では,全国の現場の教師によって国語教育のペタゴジーが協同的に構成される場である全国小学校訓導協議会に着目し,教科として国語科の定着が図られる過程で形成されたペダゴジーの特徴が検討されました。
1930年代,国語教育において,教科の目的を心情教育・道徳教育と考える立場と,言語技術の習得とする立場,すなわち「内容主義」と「形式主義」の間で対立が生じていました。こうした二項対立を,統一的に把握することで新たな理論を打ち立てた人物が,高等師範学校教授,垣内松三でした。垣内は国語教育論の中で,形象理論と解釈学を打ち立て,彼の理論は著作や講演を通じて教師に共有されていきました。これにより,文を読ませてその内容についての解釈を指導するという従来の国語教育のあり方が問い直され,子ども自身が文を読み進める過程での認識の深まり,すなわち「理会」が着目されるようになりました。1934年の訓導協議会においては,垣内の理論が参照されながらも,教師によって眼前の子どもに即して展開された実践が協議され,物の存在をいかに認識するのかという読みの本質に迫る議論が展開されました。このことが芦田の実践や垣内の読方実践の分析などの具体例に即して報告されました。
他方で,1930年代に論じられるようになった日本精神をめぐる問題への国語教育の対応も報告されました。国語科では,日本精神の概念そのものが前提として議論された上で,読方教育としての内容と方法という実践レベルで議論されました。その結果,日本語で書かれた文にはそもそも日本精神が内在するのであり,あくまでも文を読んで「理会」する解釈学に基づいた方法をとることで,自然と日本精神が体得されることが論じられました。この過程で,国語教育の教科としての自立性が再認識されました。このことは全国小学校訓導協議会においても,国語教育の固有の方法として内容(日本精神)は形式(日本語による表現)と一体のものとする読みによって「理会」が深化されるべきであると議論されていたことが報告されました。
このように1930年代の訓導協議会における議論を通して,国語科の教科の外延が自覚され,その内側にあるペダゴジーが形象理論と解釈理論によって組み替えられたことが報告から明らかになりました。
続いて本田会員からは1920年代から1940年代に焦点を当てた,学校数学を事例とした報告が次のように行われました。ここでは,教育制度の社会史において,どのように制度化されたカリキュラム,教授要目を見るのか,これらが当時の中等学校において,誰の影響でどういう風に変遷したのか,といった問いが学校教育現場との関係から検討されました。教科書としては,現在の中学校の数学科で使用されているものや1930年代に高等師範学校で編集された中等学校用の教科書が示され,カリキュラムとしては1902年,11年,31年,42年の中学校数学教授要目が示されるなど,豊富な資料に基づいて報告が行われました。これらの史料に即して,1920年代から1940年代にかけて,制度化された教科内容が転換していく過程が示されました。その転換が顕著にみられた中間団体として,日本中等教育数学会に焦点が当てられました。
1900年代初頭において中等学校は男子高等普通教育を担う機関として位置づけられ,教科数学の目標・内容は東京帝国大学の数学者をはじめとする専門的研究者によって構想されていました。教科の目標はアカデミックな数学への導入におかれ,数学を学ぶ意義を推理力の練磨におく形式陶冶説の伝統が支配的でした。そのため,教科数学を構想する内容領域にはアカデミックな数学の専門領域区分が反映され,算術・代数・幾何・三角法が相互に厳格に分離される分科主義の下で教えられていました。それぞれの分科ではテキストに示された論理展開や証明手順を一律に習得していくペダゴジーが一般的でした。
しかしながら,1920年代以降,学校の定着に伴って中等教育が拡大し,生徒は多様な進路選択を行うようになりました。その結果,中等学校の教科数学は初等教育や上級学校との接続や,教科数学の目的,内容が問い直されるようになりました。中間団体として位置づけられた日本中等教育数学会は,1920年代以降,一貫して会員が増大し,数学科の中等学校教師の半数近くが入会し,これらの問題が本格的に議論された場になりました。
1930年代の日本中等学校数学会において,教科数学の目的や内容の再検討が行われ,欧米の数学教育改革運動や新算術運動の展開を背景に,卒業後の職業生活や日常生活においても役立つような知識を重視する実質陶冶説に基づく目的論が展開されるようになりました。そのため,内容領域の構成においても,かつての分化主義が改められ,各分科を総合した総合主義や,内容を相互に関連付ける融合主義に基づく配列が模索されました。ペダゴジーにおいても,実験・実測が重視されました。教育様式の革新と教育内容のレベルアップが同時に追究されたと考えられます。その中で,日常の自然現象・社会現象に潜む法則性の発見とそれに基づく意思・行動決定を導くものとして関数概念が重視されました。
しかしながら,教育現場レベルの実現化は,従来型の教育観に基づく上級学校への入試に阻まれ,容易には進みませんでした。また,教科書においても算術・代数・幾何・三角法を関数を核として統合する構想もありましたが,結果的には「算術・代数」,「幾何・三角法」という形でまとめられました。しかし,こうした数学教育改革運動は,1930年代の初等教育の算術教育改革においてまず実現し,1940年代に中等教育数学に跳ね返ってくることで,従来型の教科数学とは内容も目的も様式も異にする教科数学として実現されるようになりました。
以上の報告が行われた後,質疑が行われました。質疑では,フロアからは例えば「中間団体」とは何と何の中間を意味するのか,といった用語に関する質問から,「国語教育の再構築過程」という国語教育史の解釈を問う質問,研究課題を指摘するコメントなど,様々な角度からの質問が寄せられました。これに対し,報告者からは,「中間団体」とは,国家から教育への一方的な流れに対して,教育の側の反省が蓄積される中で,一方的な流れが実現しなくなる場面や,学校知識を作る方も意識しなければならない場面に,国家と個や研究での位置づけの中で,工夫を経て出来上がってきたものや新しい展開を具体的に見たときに,「中間団体」として見えてくるという説明が行われました。また,別の説明では,教育には政策の影響もある一方で,眼前の子どもに効果がなければ変えざるを得ないという現場の自立性もあり,学問を教育的観点から再文脈化する必要性が生じる中で,どういう学問をどうのように教えるのか,こうしたことを模索するものが中間団体となるという説明が行われました。報告に対して,このように多くの質問が寄せられ,報告者から丁寧な応答が行われるなど,活発な議論が展開されました。 |
|
|