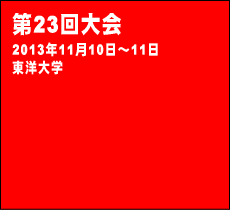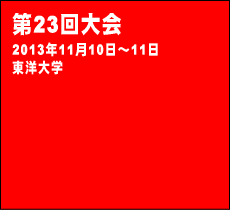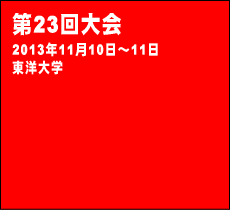
島墘夛
丂惗妶巜摫尋媶偺惉壥偲壽戣
壽戣尋媶
丂妛峑偺庴梕夁掱偲乽嫵偊傞乿偲偄偆偙偲
岞奐僔儞億僕僂儉
丂嫵堢偺惉壥傪偳偆専徹偡傞偐 |


丂嫵堢偺惉壥傪偳偆専徹偡傞偐
丂丂乗悽奅揑昗弨壔偺摦偒偲擔杮乗
|
|
|
| 曬崘幰丗 |
嵵摗丂棦旤乮搶梞戝妛乯
乽嫵堢惉壥偺専徹偲悽奅揑昗弨壔
乗OECD偺嫵堳挷嵏乮TALIS乯偑傕偨傜偡傕偺乗乿丂
愒戲丂憗恖乮撧椙嫵堢戝妛乯
乽擔杮偵偍偗傞妛峑昡壙偲庼嬈昡壙偺尰忬偲壽戣乿
彑栰丂惓復乮搶嫗戝妛乯
乽嫵堳昡壙傪揥朷偡傞乿 |
| 巌夛丒僐乕僨傿僱乕僞乕丗 |
媣晊丂慞擵乮堦嫶戝妛柤梍嫵庼乯
嶳丂弨擇乮搶梞戝妛乯 |
丂
丂杮僔儞億僕僂儉偼丆乽幙曐徹乿偺巤嶔摦岦傪娪傒偮偮乽嫵堢偺惉壥傪偳偆専徹偡傞偐乿偲偄偆壽戣傪僥乕儅偲偟偰宖偘丆崙嵺揑側摦岦偲偲傕偵崙撪偺庢慻忬嫷傕摜傑偊偮偮丆崱屻偺尋媶揑壽戣偺柧妋壔偲偲傕偵幚慔揑側懳墳壽戣傑偱傪媍榑偡傞応偲偟偰愝掕偝傟傑偟偨丅傑偢丆巌夛丒僐乕僨傿僱乕僞乕偱偁傞嶳弨擇夛堳傛傝忋弎偺庡巪偑愢柧偝傟偨屻丆3恖偺曬崘幰偐傜曬崘偑偁傝傑偟偨丅
丂傑偢丆嵵摗棦旤夛堳偐傜丆TALIS挷嵏偵偮偄偰偺曬崘偑峴傢傟傑偟偨丅TALIS挷嵏偺寢壥奣梫偵偮偄偰偼丆儅儗乕僔傾丆僲儖僂僃乕丆僩儖僐丆僨儞儅乕僋偲偄偭偨懳徠揑側4偐崙偵峣偭偰徯夘偝傟傑偟偨丅挷嵏偵偍偄偰偼丆嫵堳偑偍偐傟偰偄傞娐嫬傗妛媺婯柾偲偄偭偨奺崙偺妛峑媦傃嫵堳奣梫傗丆嫵堢偵妱偔帪娫丆峑挿偺嫵巘偺懺搙傊偺擣幆偲偄偭偨奺崙偺妛媺媦傃妛峑偺妛廗娐嫬偵偁偨傞撪梕偑帵偝傟偨忋偱丆偦傟傜偺崙偺嫵堳偺帺屓岠椡姶偲怑柋枮懌姶偑偳偺傛偆側忬嫷偱偁傞偺偐偑帵偝傟傑偟偨丅偦偺忋偱丆偦傟偧傟偺崙偺嫵堳偑嫵堳昡壙偲僼傿乕僪僶僢僋傪偳偺傛偆偵懆偊偰偄傞偐偑尵媦偝傟傑偟偨丅
丂偙偆偟偨TALIS挷嵏偐傜偺帵嵈偲偟偰丆嘆乽嫵堢惉壥乿傪媮傔丆惗傒弌偡幮夛揑攚宨偼崙偵傛偭偰懡條偱偁傝丆乽嫵堢惉壥乿傪崙嵺揑偵昗弨壔偟偨広搙偱應傠偆偲偡傟偽丆偦偺巜昗偼偳偆偟偰傕尷掕揑偵側傜偞傞傪偊側偄偙偲丆嘇嫵堢惉壥偺専徹偲偦偺昗弨壔偵傛偭偰丆TALIS偼嫵堳偺帺屓岠椡姶偵寢傃偮偒傗偡偄娐嫬梫場傪堦掕掱搙柧傜偐偵偟偨堦曽偱丆壜帇壔偝傟側偄嫵堢惉壥傪幪徾偟偨傝丆嫵堢惉壥偺乽婾憰乿傪彽偄偨傝偟偐偹側偄偲偄偆柕弬傕偼傜傫偱偄傞偙偲丆嘊嫵堳昡壙傗僼傿乕僪僶僢僋偵娭偟偰丆TALIS挷嵏偱偼峬掕揑偵懆偊傞嫵堳偑懡偐偭偨偙偲偵懳偟丆擔杮偱偼偦偆偼側偭偰偍傜偢丆摿偵乽嫵巘偵昁梫側擻椡乿偼壜帇壔偱偒側偄偲峫偊傞嫵巘偨偪偵偲偭偰乽嫵堢惉壥偺専徹乿偼戝偒側岠椡傪敪婗偱偒側偄偲偄偆栤戣偑巜揈偝傟偰偄傞偙偲側偳偑曬崘偝傟傑偟偨丅
丂嵟屻偵丆乽嫵堢惉壥偺専徹乿偵偼丆暥柆偵墳偠偨夝庍偑媮傔傜傟偰偍傝丆偦偙偱偼乽嫵堢惉壥偺専徹乿傪扤偑偳偺傛偆側僐儈儏僯僥傿傪扨埵偲偟偰峴偆偺偐偑廳梫側榑揰偲偟偰晜偐傃忋偑偭偰偔傞偺偱偼側偄偐偲偄偭偨栤戣偑採婲偝傟傑偟偨丅
丂師偵丆愒戲憗恖夛堳偐傜擔杮偵偍偗傞妛峑昡壙偲庼嬈昡壙偵偮偄偰偺曬崘偑偁傝傑偟偨丅傑偢朻摢偱丆妛峑昡壙偲庼嬈昡壙偺娫偺夞楬偑愗傟偰偄傞尰忬傊偺栤戣堄幆偑帵偝傟傑偟偨丅
丂懕偄偰丆妛峑昡壙偲庼嬈昡壙偑惂搙柺傪娷傔偰傾僇僂儞僞價儕僥傿傪壥偨偡偨傔偵乽媮傔傜傟傞乿傛偆偵側偭偨尰忬偑巜揈偝傟傑偟偨丅偦偟偰丆偦傟傜偺昡壙偑傾儞働乕僩傪悢抣壔偟偰嫵堢惉壥傪帵偡偙偲偺傒偵廔巒偟偰偟傑偆梫場偲偟偰丆嘆嫵堢壽掱傗嫵堢妶摦偵娭偡傞栚昗偑拪徾揑丒堦斒揑偱偁傝丆嬶懱惈傪旛偊偰偄側偄偙偲丆嘇娗棟怑傪拞怱偲偟偨堦晹偺嫵怑堳偺傒偱栚昗傗昡壙崁栚偺愝掕偑峴傢傟丆偦傟傜偑懡偔偺嫵怑堳偵嫟桳偝傟偰偄側偄偙偲丆嘊嫵堢偺惉壥傪乽傢偐傝傗偡偔愢柧偡傞乿偙偲傊偺夁忚斀墳偲偟偰丆抁棈揑偵悢検壔偵憱偭偰偟傑偆偙偲偺3揰偑曬崘偝傟傑偟偨丅
丂偝傜偵丆巜摫曽朄偺岺晇夵慞偑尋廋偺夞悢偱帺屓昡壙偝傟傞帠椺傗丆庼嬈偲寢傃偮偔偙偲側偔曐岇幰岦偗偺妛峑傾儞働乕僩偵傛傞昡壙偑峴傢傟偰偄傞帠椺偑徯夘偝傟丆妛峑昡壙丒庼嬈昡壙偺栤戣忬嫷偑帵偝傟傑偟偨丅偦偺忋偱丆嘆僄僶儕儏僄乕僔儑儞偺婎杮奣擮偱偁傞扤偺偨傔偺壗偺昡壙側偺偐偲偄偆帇揰傗嘇嫵堢栚昗傪扤偑愝掕偟嫟桳偡傞偺偐偲偄偭偨帇揰偺廳梫惈偑採婲偝傟傑偟偨丅
嵟屻偵丆栤戣忬嫷偺夵慞傪栚巜偟偰峴傢傟偨帠椺偲偟偰丆惗搆偺惉挿傪僩乕僞儖偵懆偊丆偦傟傪嫵巘偨偪偑嫵堢栚昗壔偟偰偄偔偙偲偱妛峑昡壙偲庼嬈昡壙傪寢傃晅偗傞偙偲傪栚巜偟偨帠椺傗丆妛峑偺偁傞堄枴偱偺栚巜偡巔偲偟偰庼嬈昡壙傪尒捈偟偰偄偔偲偄偆庢傝慻傒帠椺偑徯夘偝傟傑偟偨丅
丂嵟屻偵丆彑栰惓復巵偐傜乽嫵堳昡壙傪揥朷偡傞乿偲偄偆僥乕儅偱曬崘偑偁傝傑偟偨丅傑偢丆TALIS挷嵏偺嫵堳昡壙偺晹暘偵偮偄偰偺尒夝偑弎傋傜傟傑偟偨丅TALIS挷嵏偱偼奺崙偺嫵堳昡壙偲僼傿乕僪僶僢僋偺僨僓僀儞偲幚巤偺懡條惈偑慻傒崬傑傟偰偄側偄偲巚傢傟傞偙偲丆挷嵏偱偺婎弨偲岠壥偵僘儗偑偁傞偙偲丆挷嵏偱堄恾偝傟偨岠壥傪偁傑傝惗偠偝偣偰偄側偄偙偲偐傜丆TALIS挷嵏偱嫵堳昡壙偲僼傿乕僪僶僢僋偼堦斒揑偵峬掕揑側塭嬁偑偁傞偲敾抐偝傟偰偄傞偙偲偵懳偟偰傕偆彮偟怲廳偵敾抐偡傞傋偒偱偁傞偲曬崘偝傟傑偟偨丅
丂懕偄偰丆傾儊儕僇偵偍偗傞晅壛壙抣暘愅偺堄媊傗尷奅偑曬崘偝傟傑偟偨丅偦偙偱偼丆惗搆偺妛廗偵嫵巘偑壗傜偐偺壙抣傪晅梌偱偒傞偲偄偆奣擮忋偺堄媊傗丆堦帪揰偵偍偗傞僥僗僩僗僐傾傪嫵巘偺岠壥偲傒側偡偺偱偼側偔丆惗搆偺懏惈丒幮夛宱嵪揑攚宨摍偺條乆側曄悢傪摑惂偟偰偄傞偲偄偆揰偱偺慜恑偲偄偭偨曽朄忋偺堄媊偑曬崘偝傟傑偟偨丅堦曽丆惗搆偺妛廗偵塭嬁傪媦傏偡懡偔偺塭嬁傪夝偒傎偖偡偙偲偺崲擄偝傗丆妛廗偺惉壥傪應掕偡傞僥僗僩偺尷奅側偳偐傜偔傞尷奅偑巜揈偝傟傑偟偨丅寢榑偲偟偰偼丆偦傕偦傕晅壛壙抣儌僨儖偺慜採偲側傞撈棫偟偨乽嫵巘偺岠壥乿偺懚嵼偵媈栤偑搳偘偐偗傜傟丆晅壛壙抣儌僨儖偵偍偄偰偼嫵巘偺岠壥傪惓妋偵應傞偙偲偼擄偟偄偙偲尵媦偝傟傑偟偨丅
丂嵟屻偵丆嫵堳昡壙傪揥朷偡傞偵偁偨偭偰偺俁偮偺帇揰偲偦傟偵娭傢傞栤戣偑弎傋傜傟傑偟偨丅嘆壗偺偨傔偵昡壙偡傞偺偐乮栚揑乯偲偄偆帇揰偵偮偄偰偼丆嫵堳昡壙偺晅壛壙抣儌僨儖偼幚慔偺岦忋偵桳塿側忣曬傪採嫙偟側偄偲偄偭偨栤戣偑採帵偝傟丆憤妵揑昡壙偲宍惉揑昡壙偺嬫暿偺廳梫惈偑帵偝傟傑偟偨丅嘇壗傪昡壙偡傞偺偐乮懳徾媦傃婎弨乯偲偄偆帇揰偵偮偄偰偼丆嫵巘偺摿惈丆僷僼僅乕儅儞僗丆岠壥偺3偮偺僇僥僑儕乕偑偁偘傜傟丆偦傟偧傟偵偮偄偰椺偊偽僷僼僅乕儅儞僗昡壙偑嫵幒偺峴摦傪奜晹偐傜僐儞僩儘乕儖偡傞庤抜偲側傞偙偲傊偺拲堄側偳偑尵媦偝傟傑偟偨丅嘊偳偺傛偆偵昡壙偡傞偺偐乮曽朄丒僣乕儖乯偲偄偆帇揰偵偮偄偰偼丆億乕僩僼僅儕僆側偳偺桳岠惈偑巜揈偝傟傞偲偲傕偵丆摨椈偵傛傞昡壙偺傛偆側怑擻惉挿傪栚揑偲偟偨惂搙偲幚慔偺堄媊偲壽戣偵偮偄偰傕専摙偡傋偒偱偁傞偲曬崘偝傟傑偟偨丅
丂埲忋偺敪昞傪傆傑偊偰丆俁採埬偵懳偟偰懡悢偺幙栤偑婑偣傜傟傑偟偨丅幙栤傗偦傟偵懳偡傞墳摎偺偆偪丆庡偵埲壓偺4偮偺榑揰傪偙偙偱偼徯夘偟傑偡丅傑偢1偮傔偼丆TALIS挷嵏偲PISA挷嵏偺娭學偵偮偄偰偺榑揰偱偡丅偙傟偵偮偄偰偼丆嵵摗夛堳偐傜丆PISA偲TALIS偑楢摦偟丆妛椡偼PISA偱應傝嫵巘偺巜摫娐嫬偼TALIS偱應傞偲偄偆偙偲偑僷僢働乕僕壔偟偰偄偔偙偲傊偺婋湝偑弎傋傜傟傑偟偨丅傑偨丆彑栰巵偐傜傕丆PISA偲TALIS偑楢摦偟偰偄偔偱偁傠偆偙偲丆偦偺嵺偵PISA偺妛椡娤偲偄偆傛傝偼PISA偺僥僗僩惉愌傪扨偵偁偘傞偲偄偆堘偭偨妛椡娤偲偺楢摦偑峫偊傜傟傞偙偲偑巜揈偝傟傑偟偨丅
2偮傔偼丆愒戲夛堳偑徯夘偡傞帠椺傪傔偖傞榑揰偱偡丅傑偢丆徯夘帠椺偑廬棃偺妛峑昡壙丒庼嬈昡壙傪崕暈偟偰偄傞揰偲偟偰丆廬棃偺惗搆傾儞働乕僩偱偼嫵巘偺媄弍偑惓妋偵昡壙偝傟偵偔偐偭偨偙偲偵懳偟丆庼嬈偵椪傓惗搆帺傜偺巔傪昡壙偝偣偨傝丆栚巜偡恖奿揑壙抣偑庼嬈偱幚尰偝傟偰偄傞偐傪昡壙偝偣偨傝偡傞帋傒偱偁偭偨偙偲偑曗懌偝傟傑偟偨丅偝傜偵丆徯夘帠椺偵崌奿幰悢偲偄偭偨杮幙揑偱偼側偄栚昗偑娷傑傟偰偄傞偲偄偆巜揈偵懳偟偰丆嫵巘偨偪偐傜弌偰偒偨栚昗傪堦扷埵抲偯偗偨忋偱丆偦傟傪杮幙揑側嫵堢栚昗傊偸傝偐偊偰偄偔僗僥僢僾傪摜傓廳梫惈偑弎傋傜傟傑偟偨丅
3偮傔偼丆彑栰巵偺曬崘傪傔偖傞榑揰偱偡丅彑栰巵偺曬崘偺嵟廔揑側寢榑傗丆昡壙偑擻椡奐敪偵懳偡傞巟墖傪栚揑偲偟偰偄偨偲偟偰傕僴僀僗僥僀僋僗側傕偺偺巟攝偐傜摝傟傜傟側偄偲偄偆壽戣傊偺揥朷偵偮偄偰偺幙栤偑偁傝傑偟偨丅偙傟偵偮偄偰偼丆僾儘僼僃僢僔儑僫儖丒僗僞儞僟乕僪傗傾僇僂儞僞價儕僥傿傪偳偆峫偊傞偺偐偲偄偭偨栤戣偵偮偄偰丆椺偊偽幚慔婎弨偲昡壙婎弨偲偄偆僗僞儞僟乕僪偺2偮偺巊偄摴側偳傪媍榑偡傞側偐偱扵偭偰偄偔偙偲偺廳梫惈偑弎傋傜傟傑偟偨丅
4偮傔偼丆愑擟偺庡懱偼扤偐丆扤偵岦偗偰偺昡壙側偺偐偲偄偭偨榑揰偱偡丅偙傟偵偮偄偰偼丆嵵摗夛堳偐傜丆摨條偺栤戣堄幆偑採帵偝傟偨忋偱丆嫵巘偵嵸検偺梋抧偑側偄側偐偱嫵巘偵愑擟傪媮傔丆嫵巘屄恖傪扨埵偲偟偨昡壙傪恑傔傞偙偲偺擄偟偝傪TALIS偐傜撉傒夝偗傞偺偱偼側偄偐偲偺尒夝偑弎傋傜傟傑偟偨丅傑偨丆愒戲夛堳偐傜偼丆扤偵岦偗偰偺昡壙側偺偐偲偄偆揰偵偮偄偰偼丆巕偳傕偺惉挿偺偨傔偱偁傞偙偲偼備傞偑側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆偙偲偑弎傋傜傟傑偟偨丅
嵟屻偵巌夛丒僐乕僨傿僱乕僞乕傪柋傔傞嶳夛堳偐傜丆崱夞偺媍榑偱TALIS偺挷嵏傪偳偆偄偆晽偵傒偰偄偔偐偑柧妋偵側偭偨偲偺傑偲傔偑偁傝傑偟偨丅偦偺忋偱丆杮妛夛偺昡壙偲偄偆傕偺偵懳偡傞懆偊曽偺尨揰偵棫偪栠傝側偑傜栤戣傪峫偊偰偄偐側偔偰偼側傜側偄偲憤妵偑側偝傟傑偟偨丅 |
|
|