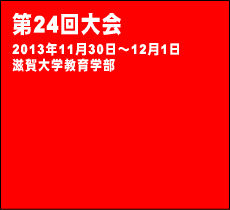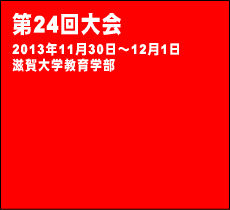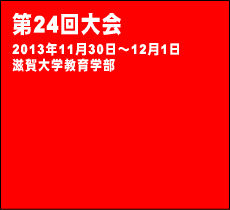
課題研究1:
〈新しい能力〉の形成と評価
―大学から社会へ―
課題研究2:
ポスト高度成長期の民間教育実践における
「目標・評価」の検討
―階級・階層的不平等への取り組みに
焦点を当てて―
公開シンポジウム:
個と集団を育てる教育実践
―どのような目標を設定し、
どのように評価するか―
|


〈新しい能力〉の形成と評価
―大学から社会へ―
|
| 司会: |
石 井 英 真(京都大学)
|
| コーディネーター: |
松 下 佳 代(京都大学) |
| 指定討論者: |
山 田 哲 也(一橋大学) |
| 報告者: |
松 下 佳 代(京都大学)
大学における学習成果としての能力とその評価 ―標準化への対抗軸―
杉 原 真 晃(山形大学)
大学教育の社会的レリバンス
―「社会人基礎力」のロジックの検討―
樋 口 とみ子(京都教育大学)
リテラシーをとらえる新たな枠組み
―OECDのPIAAC― |

OECDのPISAリテラシーやDeSeCoキー・コンピテンシー,経済産業省の「社会人基礎力」,文部科学省の「学士力」にみられるように,今日,ポスト近代社会を生きていくために必要な能力としてさまざまな〈新しい能力〉が提案され,その形成・評価のための政策や実践が展開されています。本課題研究は,義務教育段階から社会人一般にまで広がりをみせている〈新しい能力〉の形成と評価について紹介・分析し,批判的再構成の可能性を議論することを目的として設定されました。とりわけ,高等教育段階が対象とされました。
まず,コーディネーターの松下佳代会員から,これまでの共同研究の経緯と今回の趣旨が説明されました。その上で,松下会員,杉原真晃会員,樋口とみ子会員の3名から,それぞれの視点に基づく報告がおこなわれました。
松下会員からは,標準化を視点として,大学における学習成果としての能力とその評価の方法について報告がおこなわれました。これまで,標準テストへの対抗軸としてパフォーマンス評価などのオルタナティブ・アスメントが提案されてきました。そこでは,標準テストvsオルタナティブ・アセスメントという図式で整理されてきました。しかし,アカウンタビリティの要請の高まりとともに,標準化が強まり,その影響は,標準テストへのオルタナティブとして生まれたパフォーマンス評価などにも及んでいると松下会員は指摘しました。したがって,今日おこなわれているパフォーマンス評価には,「標準化を志向」するタイプと「標準化を否定」するタイプがあると再整理されました。前者の事例として,OECD-AHELOにおいてジェネリック・スキル(分析的推論・問題解決)の評価に採用されたCLAが紹介されました。この評価法は,パフォーマンス課題とルーブリック型の採点基準を使用し,同一の評価基準でおこなわれるものであると述べられました。後者の事例としては,AAC&U(アメリカ大学・カレッジ協会)によるVALUEプロジェクトが紹介されました。このプロジェクトで開発されたVALUEルーブリックは,各大学が文脈に合わせて,修正して使用するメタルーブリックであり,共通性と多様性の調停を図るものであると述べられました。しかし,各大学・学科・科目による修正が大きくなるほど,共通性が失われ,比較可能性が担保されなくなるという課題も指摘されました。このような動向・状況を踏まえて,そもそも多様性を許容しながら,比較可能性を担保することは可能か,そもそも,比較可能性を追求することに意味はあるのか,という問いがフロアに投げかけられました。
杉原会員からは,社会的レリバンス(社会との関連性)を視点として,大学教育で「社会人基礎力」を育成する意義(メリット),問題点(デメリット)とそれへの対応について報告がおこなわれました。まず,現在展開している社会的レリバンスとキャリア教育に関する議論を紹介し,そこで問われている「社会」や「キャリア」が「職業」(賃金労働)へ無自覚に読み替えられ,矮小化されていることが説明されました。杉原会員は,こうした読み替えは「社会人基礎力」の育成においても起こりうると指摘しました。その理由として,「社会人基礎力」の性格に関する以下の3点が説明されました。①知識内容を問わない「(活用)能力」であるため,どの知識内容(学問領域)にも浸透可能に見える。②「仕事」をどのように捉えるのかによって,「社会的」の対象領域をいかようにも伸縮できる概念である。③「基礎」をどのように捉えるのかによって,育成の対象領域をいかようにも伸縮できる概念である。杉原会員は,「社会人基礎力」の意義を生かすためには,その性格が内包する問題点を理解し,対策を打たなければならないと述べました。具体的な対策として,リベラルアーツ科目における実践性の回復,多様な学問領域を学ぶ教養科目の充実が欠かせないとしました。その上で,「社会人基礎力」育成を契機とした教養教育の再構築,FDの実施が提案されました。
樋口会員からは,リテラシーをとらえる新たな枠組みとして,OECDが成人を対象として実施したPIACCについて報告がありました。PIACCは,成人力の国際比較を目的としておこなわれた調査です。成人力とは,①読解力(literacy)/読解力の基礎的要素(reading
components)②数学的思考力(numeracy)③ITを活用した問題解決能力(problem-solving
in technology-rich environments)の3要素から構成されています。樋口会員は,PIACCのリテラシー概念の特徴を,PISAリテラシーとの違い,他の成人対象調査(ALL,IALS)との関係から説明しました。PISAリテラシーとの違いについては,デジタル・テキストを多用していること。自分自身の見解を述べるよりも,テキストの外部から知識やアイディア,価値を引き出すことが重視されていること。コミュニティ・社会に関する内容よりも私的状況を問う質問が多いことが指摘されました。その上で,扱われているリテラシーの範囲について,教科横断的にとらえるPISAに対して,PIACCは読み書き領域に限定してリテラシーをとらえていると説明しました。これらを踏まえて樋口会員は,PIACCリテラシーの特徴について,以下のように指摘しました。まず,読み書きに取り組む能動的な「態度」や「意欲」が重視されていることです。そして,情報化への対応として,デジタル環境のなかでリテラシーの意味を拡大させていることです。こうしたPIACCのリテラシー概念の背景として,知識基盤社会への対応が関係していることが説明されました。
以上の報告に対して,教育社会学の立場から学力研究を進めてこられた山田哲也会員が,指定討論者として意見・質問を述べました。松下会員へは,①VALUプロジェクトは,オルタナティブの例として挙げていたが,ここでは,共通性も模索していたので,これももう一つの標準化ではないか。むしろ,標準化の有無より目的(教育か選抜か)を問うことが重要ではないか。②オーセンティックな評価では,実際に出来るかどうかのパフォーマンスが重視されている。オーセンティックとは,企業での実績評価と変わらないのではないかと質問しました。杉原会員へは,社会的レリバンスをめぐる今日の議論は,あえて職業的に限定しているのではないか。職業的レリバンスが必要だという議論にどう答えるのか。労働を切り口に,学びと生活をつなげることの重要性に関する議論に対してどう考えるのかと質問しました。樋口会員へは,成人の能力を具体的にとらえるとは,どういうことなのか。成人の能力は,所属している集団とそこでの人間関係に依存している。彼らの能力は,関係論的にとらえるべきではないか。その中で,あえて個人を対象として調査していることの意味は何なのかと質問しました。
以上の指定討論がおこなわれた後,フロアからの質疑がおこなわれました。松下会員へは,比較可能性を追求することに関して意見を聞きたいという要望が出されました。また,松下会員と樋口会員に共通して,報告で使用された「真正(オーセンティック)」という用語の内実に関する質問がされました。杉原会員へは,「社会人基礎力」という言葉を出した人たちが,何を根拠とし,何を考えているのか教えて欲しいと質問がなされました。樋口会員へは,PIACCの信頼性に関する指摘,批判的リテラシーの本質的な意味合いをもう少し聞きたいという質問,さらには,今後の方向性を示して欲しいという要望が出されました。この他,活発な質疑がおこなわれました。
山田会員およびフロアからの質問・意見に対して,各報告者は以下のように答えました。松下会員は,標準化に関して,問題があるのは国際的,全国的なレベルの標準化であり,ある科目でルーブリックを使って,評価することを批判しているのではないと答えました。ただし,ルーブリックを作成した教員以外が共同で使用し評価する時に,ルーブリックからはみ出た部分を拾い上げていく必要があるとして,松下会員が,大学で実践している評価法が紹介されました。「真正(オーセンティック)」という用語に関しては,AAC&Uの場合,日常の学習場面で自然な形でおこなわれる評価として使用していると説明されました。比較可能性を追求することの意味に関しては,アメリカの大学教育では日本と異なり強くアカウンタビリティが求められていることに言及しました。そのため,標準化に対抗するためには,これと違った形で付加価値を示したり,比較可能性を示したりすることがさけて通れないとAAC&Uの人は考えていると説明しました。その上で,松下会員は,ここまで日本の大学でやるべきか,まだ悩んでいると述べました。杉原会員は,今日の社会的レリバンスをめぐる議論に関して,あえて職業的レリバンスに限定していることは同感であると述べました。その上で,"あえて性"を分からずに,そうなのだと思い込んでいる人が多い現状を指摘しました。「社会人基礎力」の大学教育への浸透に関しては,企業が人材育成にお金をかけられないので,大学にやって欲しいという要求と大学の機能の変化(社会貢献)がマッチしたことが背景にあると指摘しました。樋口会員は, PIACCの信頼性に関して,この調査には問題があると思っていると述べました。その上で,理念の面白さを強調しました。しかし,実際の問題を見てみると,知識経済を担う人的資本をとらえるものになっていないとし,理念と実際の相違を指摘しました。リテラシー概念の中身に関しては,機能的リテラシーという発想と批判的リテラシーという発想の良い部分を融合・統合していく形を想定していると述べました。特に,批判的リテラシー論が提起したことを基盤にしつつも,読み書きをすることで生活が豊かになっていくといったリテラシーの機能に目を向けたいと答えました。成人力を評価することに関しては,個人を点数で評価して国際的な指標で並べることには,疑問を持っていると述べました。しかし,その点を吟味するためにもOECDが何を考えているか調べていきたいと答えました。
最後に指定討論者の山田会員から,新しい能力の中に互恵的な関係をどう作るかなどが問われるべきこと。また,OECDは市民性の育成を重視しているが,市民性の中身の問題が問われていると述べられ,課題研究が締めくくられました。
|
| 文責:渡邉 巧(広島大学大学院・院生) |
|
|