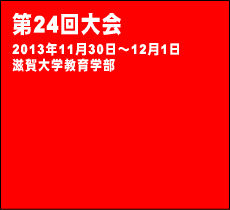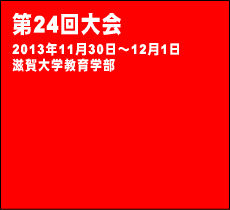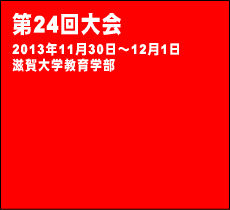
課題研究1:
〈新しい能力〉の形成と評価
―大学から社会へ―
課題研究2:
ポスト高度成長期の民間教育実践における
「目標・評価」の検討
―階級・階層的不平等への取り組みに
焦点を当てて―
公開シンポジウム:
個と集団を育てる教育実践
―どのような目標を設定し、
どのように評価するか―
|


ポスト高度成長期の民間教育実践における
「目標・評価」の検討
―階級・階層的不平等への取り組みに焦点を当てて― |
| 司会・コーディネーター: |
久 冨 善 之(一橋大学名誉教授)
小 澤 浩 明(東洋大学)
|
| 報告者: |
本 田 伊 克(宮城教育大学)
1970、80年代における民間数学教育研究・実践の展開
―学校知識論的視角から―
長谷川 裕(琉球大学)
全国生活指導研究協議会の集団づくり実践論の転回と階級・階層論
松 田 洋 介(金沢大学)
「閉じられた競争」の成立と進路指導問題の変容
―全国進路指導研究会の展開に焦点を当てて― |

はじめに,久冨善之会員から,本課題研究の立場として次のことが確認されました。それは,教育研究の世界に流布されている「日本の民間教育実践が,階級・階層的不平等に無関心だった」という言説に対し,民間教育実践が,階層的に不利な子どもたちの状況やその学習的達成に心を砕いてきたこと,そもそも教育実践は不利で学校教育になじめない子どもを学校に惹きつけるという課題を必然的に抱えていたこと,という立場です。そして,今回の追求点として,「ポスト高度成長期」に絞り,数学教育協議会(数教協),全国生活指導研究協議会(全生研),全国進路指導研究会(全進研)の実践団体について,その時代における主要な実践や実践論をめぐる議論を検討することで,民間教育実践のこの時期における「階級・階層的不平等」問題に対する把握,進展,試行錯誤などについて検討し,その成果・限界を考察することが設定されました。
本田伊克会員の報告では,1970,80年代における民間数学教育研究・実践の展開として,仲本正夫実践の意義と性格が,仲本が生徒に課した「卒業論文」等を手掛かりに,学校知識論的視角から検討されました。仲本が1967年から2000年まで実践した山村女子高等学校の生徒は,学歴序列において底辺の位置づけに置かれ,子どもたちは入学時点から学校知識を否定的に体験し,そのアイデンティティに学力による競争と選別による傷を刻印されていました。同校に赴任した当初の仲本は教育運動に奔走したため,「チョーク1本の授業」をしていました。しかし,ある生徒の「せめて30点はとりたかったよ」という言葉を画期に,1970年代半ばより仲本は「授業づくり」を開始します。1976年度より,微分の「威力」を生徒に実感させる教材「おりがみで作る容積最大の箱」が考案され,形成的評価としての1回1問の小テストも開始されました。1977,78年には,学習内容の定着のため厳しい勉強を課し,生徒の意識の変革を図る取り組みが行われました。しかし,1980年代になると,生徒から「カボチャを買うのに微分がいるか」という日常生活とは関係ない微分・積分をじっくりと学ぶことへの疑問の声が挙がり,授業が崩壊する状況となりました。そこで,仲本は,近代数学の歴史的意義を学ぶ課題を取り入れます。これは,1985年に「分析的な学習から学習の総合化へ」と進み,1980年代後半には,受験勉強のためではなく学ぶことの意味を追求して3年間の授業づくりが追求されました。しかし,こうした取り組みに対し,進学希望の普通科の生徒には,受験勉強との兼ね合いから反発する傾向も見られました。以上の検討から,仲本の実践記録の価値は,こうした「失敗」を正面から取り上げたものであり,仲本が1980年代の実践のつまずきとその葛藤と克服の過程それ自体を著作にしたことや,「失敗」を受け止め,そこから授業実践を新たに構築していくという姿勢はその実践に貫かれていることが見出されました。
長谷川裕会員は,全生研集団づくり論における階級・階層の視点の導入を理論的に主導した竹内常一に着目し,1980年代における竹内の理論の転回と,その中での階級・階層論的視点の導入の位置づけについて報告されました。1970年代の竹内は,当時の子ども・若者の状況を「発達疎外」という概念によって把握し,これを捉えるために「発達論・教育論的視点」(子ども・若者の「別の発達の可能性を掘り出していく」ことをねらいながら教育的指導がなされるべきであるとする視点)を提示しました。しかし,1980年代になると,竹内は近代に誕生した「青年期」の歴史的意義(既存の社会規範の問い直しを理想とする自己のあり方の模索)を認め,当時の子ども・若者の問題行動を学校への過剰適応から脱却する際のもがきとみなし,これを「自分くずし自分つくり」としました。こうした転回は,1970年代の発達論から1980年代には社会学理論(社会理論)へと整理されました。これを踏まえ,竹内の理論には社会学的な視点(人々の日常の編成を現代社会の支配・権力が作動するメカニズムの重要な一環であると捉える視点)が採用されたこと,また,そのように人々の生活を支配・権力のメカニズムと関連づけながら綿密につかもうとする関心に伴って,階級・階層論的視点がその理論の中に本格的に導入されるようになったことが指摘されました。その上で,近年の子ども・若者をめぐる状況は,価値観の「コンサマトリー」化の一方で,能力主義がその正統的なイデオロギーとしての力を未だに強く保っているとし,竹内の理論に対して,どのような方向に向けてさらなるヴァージョンアップを図るべきかどうかが課題として提示されました。
松田洋介会員の報告では,全進研に焦点をあて,高度成長期に形成された進路指導の枠組みが「閉じられた競争」が成立していく1970年代の時代状況の中でいかに変容したのかについて検討されました。高度成長期の全進研の進路指導理論は,①進路指導は教育課程全体を通じてなされなければならないと主張したこと,②子どもの望む進路の「選択」ではなく,「正しい進路」を教育外部の運動と連携しながら集合的に作ること,③社会的条件等に翻弄されずに,教師たち自身の力による「進路指導」実践の深化を可能にすること,に整理されます。しかし,学力偏差値に基づくヒエラルキカルな構造を持つ高校全入体制や,「進路指導」の位置づけの変化(教育課程を通しての進路指導),産業構造の転換による「下からの能力主義」のため,1970年代に入ると全進研の対抗的な進路指導のあり方に再考が迫られました。これについて,内申書に対する全進研の議論の検討を通して以下の考察が導出されました。高等教育機会が拡大した1970年代は教育システムに選抜システムが内在化し始めた時代でした。全進研は,選抜システムと結びついた教育システムをより民主的なものへと漸進的に変えていくことを志向しました。それゆえ,教育システムを選抜システムから切り離すことは,結果的に,教師の手の離れたところで,選抜システムの自律化を展開させ,子どもの家庭的背景が如実に反映した選抜結果となってしまう,と全進研は考えました。しかしながら,全進研は実現可能な具体的な方途を持たず,次の2つの課題が指摘されました。①子どもが生きる生活世界に即して既存の学校知識がもつ社会性を問い直す視点に欠けており,既存の学校知識を正当化し補完する実践になっていたこと。②進路指導の集団間の違いを問い直す視点が弱いこと。
以上の報告の後,質疑応答では,それぞれの会員の報告について次のような議論がなされました。
本田会員の報告については,仲本実践と階級・階層の問題とのつながりが分かりにくい,という質問がありました。これに対し,本田会員は,大学進学が必ずしもメインではない学校において階級・階層的な視点が学校において何を意味するかが問題である。仲本実践は,学校序列の時代の中で,自分たちの文化・数学・アイデンティティ形成を取り戻せるかという試みと考えられる,と応答しました。ただし,階級・階層的視点とそれが直結しているかについては課題とされました。これに関して,久冨会員は,数学をめぐる達成の格差がもたらした成績の序列化は大きく,それが子どもたちの現在を規定し,その後の社会的地位を再生産している。仲本実践は,学校数学の中身とそれに対する生徒たちの向き合い方についてのユニークな模索であったと言える,と述べました。また,仲本の商業科と普通科の生徒の捉え方の違いに着目し,仲本の実践から両者の可能性にとって意味あるものが出てきたと考えれば階層克服と読めるのではないか,という指摘がありました。以上を受けて,今後の課題として,伝達―獲得される,獲得の側面を仲本がどのように教えようとしたのかではなく,生徒自身が学校序列の中で数学を学びながら傷ついてきたことを含めて,仲本実践がその問題をどのように変えたのか(変えられなかったのか),すなわち,獲得される側の生徒にとっての仲本実践の意味を学校知識論的視角から問うことが挙げられました。
長谷川会員の報告については,報告で提示された竹内の理論のさらなるヴァージョンアップという課題について,竹内のヴァージョンアップは,1970,80年代に全生研が直面していた教育実践上の課題と結びついたものなのか,竹内の理論的枠組みと現実との距離に即して生まれたものなのか。また,前者については,現在の全生研の議論とどのような点で結びついているのか,という質問がありました。これについて,長谷川会員は,全生研は子どもを捉えきれていない印象があるとし,現代の能力主義がどのように子どもに刻み込まれているかを課題としました。また,竹内の発達から社会理論へという理論転回を平等論としてどう読めるかについて質問がありました。長谷川会員は,竹内の提示した「自分くずし自分つくり」によれば,個々の子どもによって直面している課題は異なり,教育者は共存的な他者として関わっていく「平等」をとる。それは学力の平等のような達成水準ではなく,アイデンティティ課題を抱えた子どもに応えていくという「平等」ではないか,と応答しました。
松田会員の報告については,①内申書をめぐる議論と高等学校教育機会の拡大や近代学校批判との関連と,②1970年代の社会における構造移動と全進研の進路指導の集合的な進路指導のオルタナティブの模索とのつながりについて,質問がありました。①について,松田会員は,近代学校批判や社会の成熟化に対して民間教育運動は対応できなかったのではないか,と応答しました。②については,1970年代の民間教育運動は,当時のフェミニズム運動等とのつながりを持ち,ミクロポリティクスを理解する可能性があったが,成し得なかった。結局,1970年代以降の民間教育運動は新中間層との結びつきはあったものの,"市民"と結びついたが"庶民"と結びつかなかったという見解を述べました。また,松田会員の全進研の評価の根拠となる実践のイメージについて質問があり,松田会員は,既存の学校知識を正当化するにとどまっていた実践のイメージがあると応答しました。その上で,この問題を問い直す視点として全生研の吉田和子や『10人のスーパー・ティーンたち』(太朗次郎社,1995年)を著した高橋清行の実践に言及し,彼らの実践に見られる,他者性を尊重しながらコミュニケートするような実践は少ないと述べました。
最後の総括では,久冨会員より,1970,80年代半ばの状況が未だ判然としないという課題が述べられました。小澤会員は,これを踏まえ,今後の課題として次の点を挙げました。ポスト高度成長期の民間研に階層的視点があったことは確認されるものの,どのように実践を作っていくかに焦点化したものは無かった。中内敏夫のいう「教材の社会的かたより」のような,子どもが一生懸命勉強するほど自分ではなくなってしまう状況が1960年代から1970年代にあったのではないか。 |
| 文責:永田 和寛(京都大学大学院・院生) |
|
|