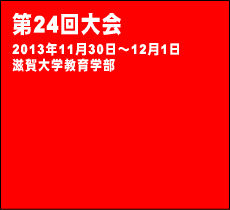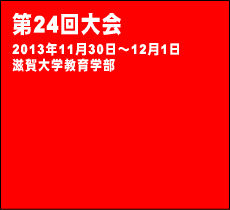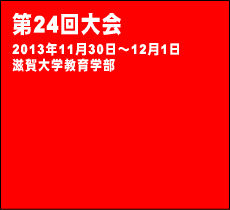
課題研究1:
〈新しい能力〉の形成と評価
―大学から社会へ―
課題研究2:
ポスト高度成長期の民間教育実践における
「目標・評価」の検討
―階級・階層的不平等への取り組みに
焦点を当てて―
公開シンポジウム:
個と集団を育てる教育実践
―どのような目標を設定し、
どのように評価するか―
|


個と集団を育てる教育実践
―どのような目標を設定し、どのように評価するか―
|
| 司会: |
岸 本 実(滋賀大学)
川 地 亜弥子(神戸大学)
|
| シンポジスト: |
川 嶋 稔 彦 (湖南市立三雲小学校)
小学校における個を育てる教育実践と個の評価
藤 木 祥 史(京都府府民生活部青少年課)
中学校における集団づくりの教育実践
河 原 尚 武(近畿大学)
教科外活動を中心とした教育目標・評価論の展開 |

学校現場での人間関係上のトラブルにおける子どもたちの「問題」行動に対して,どのような目標設定と支援の評価によってその充実を図っていけばよいのか。本シンポジウムは,上記の問いについて検討することを趣旨として開催されました。
シンポジウムに先立ち,司会の岸本実会員から趣旨説明と報告者の紹介がなされ,その後,川嶋稔彦氏,藤木祥史氏,河原尚武会員の3名が登壇し報告が行われました。
川嶋稔彦氏からは,暴言・暴力に支配された学級の中心を担っていた小学生の子どもたちに対して,どのような実践を行い,評価し,手だてを講じてきたかについての報告が行われました。まず,授業が成立しない暴言・暴力に支配された学級の様子,それに対する教師の疲弊感の様子という実践の背景が説明されました。そして,その状況を改善するために,大きく2つの試みが紹介されました。1つは,授業中や家庭訪問の様子などから詳細な一人ひとりの成長を書き込む「カルテ」の作成により,子どもたちとの信頼関係を築くというものでした。2つ目は,学級が抱える問題を克服するため,問題の中心となっていた2人を抽出児とし,彼らの「個の目標」を達成することで,学級の課題を克服していこうという試みでした。その後,2つ目の試みについての詳細な報告がありました。それは,抽出児に対してどのような「個の目標」を立て,それを達成するためにどのような実践を行い,それをどのように評価したかというものでした。まず,詳細な情報を交えながら抽出児の紹介がなされました。次に,この子どもたちの課題から「暴言」や「コミュニケーション下手」を彼らの「個の目標」として設定したことが説明されました。そして,この「個の目標」を達成すべく行われた実践が紹介されました。その中で,抽出児たちが他者との話し合い活動による問題解決を通してどのように変容したか,また,学級がどのように変容したかについて,授業の話し合いの逐語記録から説明がなされました。そして,この実践を行った結果,抽出児たちは暴力でない解決の仕方に気づくことができ,学級としても和やかな雰囲気の学級へと徐々に変容していったという成果が報告されました。
藤木祥史氏からは,中学生の子どもたちの「問題」行動に対して,どのような実践を行い,評価し,手だてを講じてきたかについての報告がなされました。まず,藤木氏は,学校が加害・被害の関係で処理し被害側の親から文句が出ないようにしたいという管理職の指導目標を否定する実践をどのように展開すべきかを考えることが現場の指導目標であるべきという提起がなされました。そして,「問題」行動が起こった際に,集団に対してどのような評価をし,手だてを講じていくべきかについて「ガラス破損事件」,「イス落下事件」という事例を交えながら説明がなされました。具体的には,まず,荒れていく際の集団の中に属する子どもたちの類型として①課題の先頭に立っている子,②それに追随する子,煽る子,③中間に位置づく子,④反対に良心的なリーダーとして期待する子,⑤リーダーに協力的な良心層の5つが示されました。次に,この類型をもとに,被害者の子どもは①と②の近くにおり,①・②からいやがらせを受け自尊心を傷つけられた結果,「問題」行動に発展したという説明がなされました。それに対する手だてとして,アンケートによって,被害者の子どもの心境を推し量らせ,①だけの責任だけではないことを考えさせ,④や⑤の子どもの認識を変えることを試みたことが報告されました。その結果,④・⑤に加えて,①・②の子どもも生活改善をしっかり考えるようになり,落ち着いてきたとのことでした。同時に,③という層の非協力,無関心が最も問題であることが浮かび上がってきたことが説明されました。最後に,教師が一つの出来事を通して関係性の指導をすることによって,③に批判がくるように集団を指導することが重要であり,そのような指導ができないことが現在の学校現場の一番大きな課題であるということが指摘されました。
河原尚武会員からは,各教科・科目以外の学習領域及び教育指導の分野に関する教育目標と評価論についての報告がされました。まず,報告の前提として,従来,特活,総合,道徳,外国語活動,生徒指導を形式上教科外教育・教科外活動と一括することは不斉の感があるということを指摘し,この教科外の存在理由や成立根拠を改めて再検討することの必要性が指摘されました。次に,①生活綴方による生活指導についての検討,②現代的課題の検討,③教科外活動における教育目標・評価論の探求についての先行動向の整理結果が報告されました。最後に,これらの論考の整理を通して,「教科外教育の目標-評価システム」という形で一つの構想が提起されました。その特徴は以下の4点から説明されました。1つ目は,教科外活動における基本的な能力を大きく「観点」として整理し,それぞれの観点の成長・深化のありようを評価するための基準として「指標」という用語を充てたというものでした。2つ目は,ここでの「観点」は,集団にかかわる力,活動内容を構想する力,交流を支える力の3つであるというものでした。3つ目は,「指標」である「集団に関わる力」の基準と「活動内容を構想する力」の基準の構造的な関係でした。まず,集団に関わる力の基準は集団への「参加のしかた」を置き,その下位指標として,「リーダーとして」「自治組織の係として」「集団の中の他者への関心」などを設定するというものでした。また,活動内容を構想する力の基準であれば,計画作成の主体(下位指標としては,生徒の発意か,教師の原案か)などを設定するというものでした。4つ目は,この「システム」は,具体的な活動内容の系統は含まず,観点や指標は学習者と集団の力を理解するためのてがかりであり,活動内容や到達目標はそれぞれの実践の場における課題や実践の条件に応じて構想されるものというものでした。
以上の報告の後,司会者の1人である川地亜弥子会員から指定討論として3名の報告者に質問が投げかけられました。
まず,川嶋氏に対して,①お互いの意見を出し合えたり聞き合えたりするための具体的な指導はどのようなものか,②子どもの実態をどう捉え,どのような願いや目標を立て,中学年には難解なイラク問題を題材として選んだのか,③教師集団,保護者,管理職も含めて実践の課題や目標が共有されたのか,④生活の問題と学力が結びついていないという指摘についてどう考えているか,⑤長期の教科外活動の中で子どもたちがどのように変わってきたのか,また,それを捉えてどのように実践を組み立て子どもたちや実践を評価し目標を立て直したのか,という5点の質問が出されました。これらに対して,川嶋氏からは以下のような回答がなされました。①の質問に対しては,いつでも話し合いができる環境を整え,話し方については細かいルールは設定せず小さなつぶやきも拾うというスタンスを示し,聞き方についてはそれを話し合い子どもたちの中で確立したという説明がなされました。②の質問に対しては,暴力・暴言が蔓延している状況を自分たちの問題として捉える,やられている子が声を挙げることのできる集団にするという2つの目標を「平和」を考えることで達成するためにイラク問題を取り上げたという回答がなされました。③の質問に対しては,隣のクラスの担任と協力して学年で行う活動を増やし,保護者に対しては,家庭訪問を増やし,学級通信,忙しければ電話で共有を図ったとのことでした。④の質問に対しては,問題解決学習を採用しいじめられている子がどのようなことを考えているかについて話し合うことなどを行ったという説明がなされました。⑤の質問に対しては,全ての子どもたちに対して,自身の手で行事を作り,子どもたちから子どもたちへ発信させる機会を保障したとのことでした。
藤木氏に対しては,①個々のケアの関係の詳細はどのようなものか,②中間層の子どもたちへのアプローチの方法はどのようなものか,③中間層の課題が教育目標として立ち上がるための実践のポイントや工夫はどのようなものか,④アンケート以外の中間層の把握に関する名人芸的方法はどのようなものか,という4点の質問が出されました。これらの質問に対して,藤木氏からは特に①と②についての回答がなされました。①の質問に対しては,課題のある子どもへは,彼らのやっていることを認めて対話をすることから始め,応答の関係を作り,さらに,批判に耐えうる関係を作ったとの説明がなされました。②の質問に対しては,中間層の自己責任の論理を崩すため,ワーキングプア,多重人格,ストリートチルドレン,養護学校の実践のビデオを次々に見せ,「これらは自己責任か」ということを問い,変容させることを試みたとのことでした。
河原会員に対しては,集団に関わる力や交流に関わる力というものが他の2人の報告からどう捉えられるのかという質問がなされました。それに対して,河原会員からは,まず,交流を支える力というのは,いろいろな問題に直面した時に基本になるものであると説明がなされました。その上で,川嶋氏の実践では問題解決学習の中で子どもたちが言葉の力を身につけるという見通しがあり,藤木氏の実践では事態をどう把握するかという際も言葉でつかむ必要がある,と2人の報告を踏まえて回答がなされました。そして,実践の最も基礎である交流を支える力とその中核にある言葉を育てる方略の重要性,子どもたちが生活現実を分析する力を獲得する際の方法に焦点を置く必要性が提起されました。
その後,フロアからの質問と応答がなされました。
川嶋氏に対しては,学校として共通の価値観へ進むために,構造的(子ども集団・教師集団・保護者集団の三重構造)に集団づくりを進めていくという点をもう少し教えて欲しいという質問が出されました。それに対して,川嶋氏からは以下の返答がありました。まず,教師集団に関しては,ミドルリーダー世代がいろいろな面で若手教員とともに学び合う場を設定し,子どもについて語り合える教師集団を作ることの重要性を指摘されました。次に,保護者集団に関しては,教師が保護者のもとに多く足を運んで関係を作ることで,保護者会に参加してもらえ,そこで教師を介して保護者集団が形成されるとのことでした。
川嶋氏と藤木氏対しては,若手教員に知や技を伝え,学校としてサポートしていくための示唆や提言や子どもの必要を捉える枠組みや見通しがあれば教えて欲しいという質問が出されました。それに対して,川嶋氏からは,学級経営や保護者対応,授業の話し合いの仕方などの勉強会や市教委が立ち上げた勉強会で市内の小中学校の若い先生に対して講師的立場で伝えていくということを行っているとの説明がなされました。藤木氏からは,学校外と学校内の2つの側面から回答がなされました。まず,学校外に関しては,退職された先生方に非行問題を抱えた少年の支援をしてもらい,それに関わる教育講演会などをやりながら若手教員の学ぶ場を提供しているとのことでした。学校内に関しては,毎年気になる子どもの指導の度にアセスメントを積み重ね,そのアセスメントをもとに話し合いをし,共有をしているとのことでした。この話し合いでアセスメントについての質問を受け,修正するということをしており,若手教員にとって勉強の良い機会にもなるということも重ねて説明されました。
河原会員に対しては,川嶋氏と藤木氏の実践を今までの研究の到達点を踏まえてどう分析されたのかという質問が出されました。それに対して,河原会員は,報告にあったアセスメントは細かい目標の内訳に即した評価ではないかもしれないが,きちんと自分たちが実践や取り組みの中で使ったものを評価し,次に生かすということがなされており,そのことが重要だと返答されました。
最後に,司会の岸本会員から①優れた教育実践を継承していくときにも目標評価があるからこそできる,②目標が指導の中で立ち上がりながら指導の方針を変えていくという時にも目標評価ということが鍵になっている,という本シンポジウムのまとめがありました。 |
| 文責:岡田 了祐(広島大学大学院・院生) |
|
|