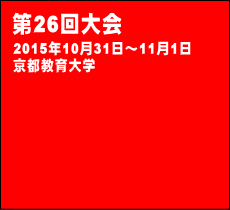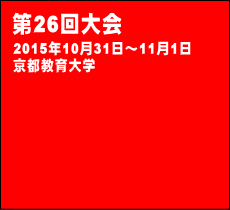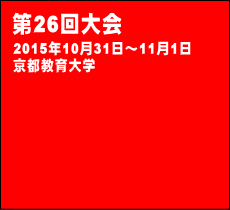
課題研究:
社会科で習得させる知識・理解と
価値観・行動の指導と評価
―国内外の関連領域の検討をふまえて―
課題講演:
戦後の学校の展開と人づくりの課題
公開シンポジウム:
教師として求められる資質・能力
―教育目標・評価論からの提起― |

課題研究
社会科で習得させる知識・理解と
価値観・行動の指導と評価
――国内外の関連領域の検討をふまえて―― |
司会
コーディネーター |
岸 本 実(滋賀大学) |
| 指定討論者: |
鋒 山 泰 弘(追手門学院大学) |
| 報告者: |
木 村 裕(滋賀県立大学)
オーストラリアのグローバル教育の検討をふまえて
川 口 広 美(滋賀大学)
イングランドのシティズンシップ教育の検討をふまえて
長谷川 豊(京都府立大学)
日本の福祉教育の検討をふまえて |

はじめに
社会科とは何を目標とする教科であるか。この答えについては,歴史学,地理学,社会諸科学にもとづく科学的な社会認識の形成に重点をおく見方から,態度や価値観も含めた総合的な資質の育成にあるとする見方まで多様である。本課題研究では,科学的な知識・理解を重視しつつも,それらを価値観や態度,行動の能力の発達と関連づけて総合的にとらえるところに社会科の教科としての特質があるという立場に立つ。グローバル化など社会の急激な変化の中で地球的諸問題や国内の社会問題からの要請として,価値観や行動能力を育てる教育の重要性が増大している。学校教育としては,社会科という教科の中で対応するにしても,社会科と総合的な学習の時間,特別活動,道徳とを合わせた指導として対応するにしても,社会認識とそれに関わる価値観や行動の指導において,目標をどのように具体化し,指導に生かせばよいのか,そして,それをどのように評価すべきであるかについての検討が重要な課題となっている。
この課題についての中等社会科におけるこれまでの議論について最小限のことをふまえておきたい。まず,戦後直後の構想では.公民教育の目標を「(前略)生活のよき構成者たるに必要な智識技能の啓発とそれに必須なる性格の育成」 とし,公民教育の中で「公共的問題への関心を高める」とともに,学校組織運営全体が「公民的実習」の場となることを提起した。その内容は,生徒代表等の選挙など学校の自治的な運営,遠足や地理,歴史に関する研究,調査の企画と参加などであった。勝田守一はそこでのポイントを ,「子供たちがはっきりした自分の意見をもち,社会や公共の事象に対する判断の力をもち,しかもそれを公共の問題として,すなわち,自分の問題として,討議し,理解し,解決する責任を感じ得るようになるか,否かにある」と指摘していた。また,「学習指導要領社会科編(Ⅱ)(試案)」(1947)で示された政治単元の目標には,「新憲法の原則に従って,政治の現状を,批判的に自主的に判断する能力」,「宣伝にとらわれずに,自分自身の政治的意見を持つ能力」など価値観や行動に関わる目標が含まれていた。
このように初期社会科においては,価値観と行動に関わる指導が重視されていたが,旭丘中学校事件(1953年~)が起こり,義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(1956年)が成立した後は,現実の社会の公共的な問題について,その問題を解決する責任を感じることや政治的意見を持つことを指導することが難しくなった。さらにその後,「教育の現代化」の流れも受けて,「開かれた科学的認識の形成」を目標として,「科学的知識を科学的探求の論理にもとづいて習得させる」 ことを重視し,「質の高い社会認識の形成という観点から社会科授業理論を体系化」し,質の高い認識を形成する授業の構成原理を解明する研究 が進められ,科学的社会認識に重点を置いた実践と研究が進められた。
もちろん,「問題解決」や「意思決定」を重要な構成原理とする実践や研究も戦後一貫して展開されていた。最近注目されるのは,唐木清志の日本型サービス・ラーニングの提案である。 それは,「よりよい社会の形成に参画する資質や能力」の育成を目標とし,①地域社会の課題の教材化,②プロジェクト型の学習過程,③振り返りの重視,④学問的な知識・技能の習得と活用,⑤地域住民との協働という単元構成の学習である。
社会科は民主主義的な態度・能力と知識を育成することを教育目標とし,自由で平等な社会の在り方についての認識を教育内容とするが,社会の在り方の一元的な方向付けは民主主義の理念に反するので,教育方法としては,子ども一人ひとりの多様な見方・考え方の表明を保証し支援するように組織されなければならない。ここで,教育目標や内容と社会認識の方法が矛盾することになる。これを,草原和博は「社会科教育のパラドックス」と呼び,「現行社会の漸進的な改善に教育の役割を求める」新潮流として,規範反省学習(梅津正美),比較社会学習(草原和博),合意形成学習(吉村功太郎),価値形成学習(溝口和宏),社会参加学習(唐木清志),社会形成学習(池野範男)を分析している。このパラドックスは,自由主義社会の教育においては不当な支配が排され,中立性が確保される必要があるにもかかわらず,民主主義や人権という人類の普遍的な価値については望ましいものとして教育しなければならないというパラドックスであろう。このパラドックスに対して新潮流は次の二つの点で解決方向を示している。一つは価値観をダイレクトに教えるのではなく,人々の価値観が強く投影されたミクロな社会的行為や政策の選択・決定やマクロな「制度・体制」の存在理由や正当性を捉えさせることを通して価値観を扱う方向である。もう一つは一つの見方・考え方を絶対視して教え込まないように,子どもの「自立的・反省的」な思考・判断を導くことや,個々人がもつ見方・考え方を「自律的・参画的」に行使させることである。
その他,18歳に選挙権年齢が引き下げられたことを受けて議論が活性化している主権者教育も価値観や行動の指導に踏み込む教育が構想されている。例えば,総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」 は「国や社会の問題を自分の問題として捉え,自ら考え,自ら判断し,行動していく新しい主権者像が求められている」として,「社会参加」,「政治的リテラシー(政治的な判断力や批判力)」,「社会的・道義的責任」を強調し,主権者教育を「社会の構成員としての市民が備えるべき市民性を育成するために行われる教育であり,集団への所属意識,権利の享受や責任・義務の履行,公的な事柄への関心や関与などを開発し,社会参加に必要な知識,技能,価値観を習得させる教育」を主権者教育として定義している。主権者教育において教育の中立性が問題となる時,ドイツの「ボイテルスバッハ・コンセンサス」が共有の合意として大切にされている。それは,①教員は,期待される見解をもって生徒を圧倒し,自らの判断を持つことを妨げてはならない。②学問と政治の世界において議論があることは,授業でも議論があることとして扱わなければならない。③生徒が自らの関心・利害に基づいて効果的に政治に参加できるよう,必要な能力の獲得が促されなければならない,という合意である。
さて,ここまで,社会科において学習者の価値観や行動能力の指導と目標や評価についての議論の一端を垣間見てきた。このような検討をふまえると,今課題となっていることは二つある。一つは,学習者の価値観や行動能力を目標として指導し評価していくことを,社会科本来の目標である社会認識を育てることとどのように関係づけて進めていくかという点である。もう一つは,特定の価値観や行動を押し付けたり,強要したりせず,中立的で民主的に進めていくためにはどうすればよいかという点である。
この二点を共通の論点としつつ,それぞれ固有の領域で問題になっていることも含め本課題研究では,オーストラリアのグローバル教育,イングランドのシティズンシップ教育,日本の福祉教育の検討から,社会科において,学習者の価値観と行動の指導と評価をめぐり,理論的に何が論点となるのか,そして実践的にどのように指導と評価を進めていけばよいのかについての示唆を得ていきたい。
Ⅰ オーストラリアのグローバル教育の検討をふまえて(木村 裕;滋賀県立大学)
オーストラリアのグローバル教育では,万人にとって平和で,公正で,持続可能な世界の実現に向けて活動できる学習者の育成をめざし,知識や技能の習得にとどまらず,実際の行動への参加を可能にするための力量形成をめざした目標設定が行われてきた。そしてこれらの目標を達成するために,グローバル教育の重要な理論的基盤となっているコルダー(Calder, M.)とスミス(Smith, R.),およびフィエン(Fien, J.)の開発教育論では,学習者の学習への主体的な参加および他者との協同的な学習を保障する探究アプローチを採ることが提案されてきた。
なお,両論ともに,この学習の過程においてただ行動を起こすのではなく,資料やデータの吟味や他者との議論などに基づく社会認識と自己認識の深化を基盤として,問題解決のために自らがとるべき行動を自己決定したうえでその行動に参加することと,自らの行動の結果を評価し,改善することの重要性を強調している。これにより,平和や公正,持続可能性など,グローバル教育がめざす社会の実現に際して重要とされる価値観の押しつけになることが避けられてきたのである。ただし,社会認識ならびに自己認識の深化に関して,コルダーらが相互依存関係という視点を重視するのに対し,フィエンはイデオロギーや権力のせめぎ合いという視点を重視していた。また,主に想定される行動のあり方に関しては,前者が情報提供や個人レベルでの生活改善を強調するのに対し,後者は政治的リテラシーの獲得を通した社会構造そのものへの積極的な働きかけを伴う政治プロセスへの参加を強調していた。
さらに,単元例「良いビジネス」では,教師が生徒の学習の成果や課題を直接的に把握するための評価課題や評価方法などについての意識的な言及は見られなかった。ただし,学習成果の発表とそれに基づく議論は,発信された情報や発信者の認識の質の度合いを把握したり,さらなる深化を促したりするための「評価」を行う機会ともとらえられた。
Ⅱ イングランドのシティズンシップ教育の検討をふまえて(川口 広美;滋賀大学)
成立時より,知識のみならず価値観や行動に至るまでの総合的な能力育成を志向した教科である。そのため,行動を扱うべきかどうかという議論はほとんど行われていない。ただし,成立以降「多様な価値が共存する社会で,どのように価値を扱うか?」ということが,議論の中心課題として示されていた。なお,シティズンシップ教育では,大きく2つの立場をとっていた。
第1は,私的・個人的価値観育成には直接関与しないという立場である。これは,伝統的な立場である。この立場は,公的・社会的価値育成に特化するという方法,あるいは私的・個人的価値観分析を行うことで間接的に関与するという2つに分かれる。具体的な単元案として,前者では,政策・法や制度について,そこに含まれる社会的価値観の立場から分析するというもの。後者では,「国を愛する」という個人的な選択を取り上げ,その背景にある価値観や社会的意味を分析するというものがあった。この立場に基づき,GCSE(中等学校修了資格認定試験)なども作成されている。
これに対し,第2の立場として,Arthur, J.を初めとして,積極的に私的・個人的価値観育成に携わろうという動きも出てきた。これは「普遍的な価値」=アリストテレス哲学として,私的・個人的な品格・品性(Character)育成を行おうというものである。この動きは,現在の政府の主張との親和性を背景に強まりを見せている。
以上のように,多様な価値がある社会であるからこそ,シティズンシップ教育では,(1)私的・個人的価値育成から引き下がり,公的・社会的価値育成に特化する(2)多様な価値に共通する普遍的価値を教授する,という2つの立場が窺えた。
Ⅲ 日本の福祉教育の検討をふまえて(長谷川 豊;京都府立大学)
1977年度の「学童・生徒のボランティア活動普及事業」を契機として小・中学校における福祉教育が開始された。当初は,教科とりわけ社会科の中で「社会福祉問題への知的関心・知的理解」を深めつつ,特別活動や道徳において「体験化」や「感覚化」を図ろうとしていた。70年代においては,基本的人権,福祉制度の理解,生活者としての問題の認識と問題解決のための実践意欲と実践方法を「探究」することの重要性が説かれていた。
しかしながら,80年代には知的関心や理解への取り組みの弱さが総括されていた。さらに,90年代になると「体験」重視の傾向が強まる中で,「思いやりの心」に一元化され,「体験化」や「感覚化」のみが強調され,「精神主義・道徳主義の横行」となった。社会福祉問題を「矛盾」をはらむものととらえ「探究」という方法で迫る福祉教育論は完全に後退したのである。
高校「福祉科」においても,「介護福祉士」資格取得との関連から,理解よりも実習が重視される傾向が強まった。教育内容もソーシャルワークの視点は縮小しケアワークへと大きくシフトしてしまい,もはや高校福祉教育と呼び得るものではなくなった。
さらに,教育改革国民会議(2000年),中央教育審議会答申(2002年),東京都立高校教科「奉仕」必修化(2007年)と奉仕活動の義務化の動きがある。このような動きに対し社会福祉法人大阪ボランティア協会早瀬昇は「奉仕活動の義務化」に反対し,自主的な「ボランティア学習」推進を求める提案をしている。また,倉本哲男によるサービス・ラーニングの提案などが注目される。
Ⅳ 指定討論とフロアからの議論
指定討論者の鋒山泰弘からは次の3つの論点が提起された。①対立とジレンマの問題をどう扱われているのか。②知識と問題解決,問題解決にはどれだけの知識の問題が必要だと考えられているのか。③市民の前に善き品格ということで,教科の前に,教科外,家庭教育で前提としての人格特性を育む教育の必要性が学校にはどこまで求められるのか。
これに対して登壇者から以下のような回答があった。
○木村会員の回答
①たとえば「公正」な社会のあり方に関して,どのような状態を「公正である」と捉えるのかに関する多様な議論(対立やジレンマも含めて)を調べ,それをふまえて自分なりの立場を見出していくというかたちで扱われている。
②知識を獲得しながら問題解決に取り組み,また,問題解決に取り組む中で新たな知識を得たり認識を深めたりするというかたちの学習活動が想定されている。したがって,最低限どの程度の知識が必要となるのかという議論よりも,どのような問題解決に取り組ませるのかという議論が主であると考えられる。
③グローバル教育は1つの教科としてよりもむしろ,教育活動全体を通じて実践すべきものと位置づけられている。また,人格特性と市民性の育成,あるいは知識や認識の獲得とは必ずしも切り離して考えられるものではなく,互いに影響を与えあいながら,並行して育成していくことがねらわれていると考えられる。
○川口会員からの回答
①基本的に価値に関わる事象については,「事実」としてではなく,「解釈」として扱う。従って,対立やジレンマとして扱っていると考えられる。生徒は,その対立やジレンマから,多様な価値観,価値の解釈を知ることになる。
②知識と能力育成を分離して捉えない。知識は,実践において必要な知識を習得するという立場。知識の質についての検討は余り行われない。
③シティズンシップ教育は「教科」の枠を従来どおり想定していない。品格・品性としては,全人的なところが強く,「教科」というのが難しいのではというのはその通りだと思う。
○長谷川会員からの回答
福祉教育では表面的には対立や矛盾が表にあらわれにくく,思いやりで一元化してしまう。認識のレベルは何も深まりを求められず,同じ行動を繰り返させられる状況がある。背後にある貧困の問題は見ようとしなければ見えない。
そのあとフロアから次の3つの論点が提起された。①教科教育としては,やはり,科学的認識の形成,認識の科学性が大切だと考えられるので,価値観や行動の指導という場合,制約をどうとらえるかという問題である。②国民教育と市民教育の関係をどうとらえるのか。③この課題研究では価値観と行動というような概念や用語が使われているが,指導要録の4観点,すなわち,知識・理解,思考・判断・表現,資料活用,関心・意欲・態度という概念とどう関わるのか。
概念・用語に関しては,本課題研究では,「思考」という用語が直接的には使われていなかった。それに当たる用語としては「認識を深める」や「認識の深化」あるいは「吟味・検討」という用語があった。外国の事例,あるいは日本でも福祉教育や主権者教育などでは,様々な用語が使用される。学校現場では,文部科学省が告示する学習指導要領や文部科学省の通知や報告を参考に教育委員会等が決定する指導要録の様式で使用している用語が定着しているので,それらの用語との関連についても明示することで分かりやすい議論となると考えられる。
おわりに
木村報告では,コルダー・スミスからフィエンへの理論的展開から特に示唆を得られると考えられる。一般に,社会認識を獲得させるという段階までは中立性をことさら問う必要がなく,判断をさせるところから特定の価値観に偏ることがないように留意すると考えられることも多い。しかし,フィエンは,事実認識のレベルからイデオロギー性が存在することを明示し,事実認識の背後にある立場を自覚させることが,それに対して批判できる力を保障することになると考えていた。
また,判断や行動の選択において,自己決定を保障するためには,まずは十分な情報を吟味させることが必要であることは言うまでもない。しかし,単により多くの情報というのではなく,その情報をいかに読み解くかという政治的リテラシーを獲得させることにより,学習者による自己決定を保障するという考えは評価できる。単元例「良いビジネス」においても,「調べ,審査する」というプロセスに,単なる情報の吟味から政治的リテラシーの発達へという視点が具体化されている。
なお,オーストラリアのグローバル教育では,学習指導の中で生徒が行う価値判断や行動について,教師が評価するということがあまり見られていないということであった。これについては,評価することにより特定の価値観や行動を刷り込むことになると考えて慎重になっていたのか,それとも他の理由があるからなのか,今後検討していくべき課題である。
川口報告では,価値を教えるのではなく,価値を作っていく指導の在り方を示すという点が特に参考になった。パブリックな価値とプライベートな価値とを区別して,学習対象とする価値観はパブリックなレベルに限定する。また,価値観そのものを判断の対象とするのではなく,価値観が埋め込まれた行為や政策の是非を問い,社会的な行為や政策の土台にある価値観を吟味・検討するというプロセスにより自らの価値観を自己決定できる力を育てている点が示唆に富む。
個人的な価値観も社会的に共有されていたら一定社会的なものになる。それが,パブリックな価値観と対立していたら,どう対象化するのか。報告の中でも,両者の区別は必ずしも簡単ではなく,分けられない場合も多いことが指摘されていたが,その点をどのように解決していくのかが今後の課題となるように思う。また,間接的に吟味・検討することで価値観を注入されることを避け,自ら形成していくことができるという論理はわかりやすいが,その中においても,隠された形で刷り込まれる価値観は存在しないのか,今後検討していきたい。
長谷川報告では,日本の福祉教育においては,社会科と結び付けられず,感覚化,体験化が強調されることで,精神主義,道徳主義的な傾向が広がっている問題状況があることがわかった。社会科と結び付けられず,特別活動や総合的な学習の時間,道徳などの領域だけで実践が進むことの危険性が浮き彫りとなったと言える。
70年代には「探究」を位置づけるプランも提案されていたが,それは根付かなかった。実際の福祉の問題に目を向け科学的に認識していけば,社会の矛盾や価値観に取り組まざるを得なくなる。福祉に関する国家資格において,理解よりも実習が重んじられることも,同じ傾向から来ているものと思えた。
このような課題研究を通して,社会認識の指導と結びつけて価値観や行動の指導が行われることの重要性と,その在り方について明らかにできた。また,そのことにより,特定の価値観や行動を押し付けるのではなく,自己決定させることを保障している点が明らかとなった。
報告の中で今後の課題がいくつか示された。加えて,次の点が今後の課題である。すなわち,社会科という教科教育の中で,社会認識と価値観,行動の指導を考えるのか,社会科を中心に関連付けながら,特別活動や総合的な学習の時間,道徳を「合わせた指導」という形で考えるのか。目標として指導するというレベルでは,それほど違いはないが,評価が入ってくると,教科教育の評価の論理と教科外の評価の論理が当然変わってくる。それをどう考えるのかについても今後の検討していきたい。
この課題研究は,2013~14年度の学会の共同研究補助を受けた研究をもとに取り組まれた。私たち共同研究グループとして貴重な機会を与えていただいたことに感謝している。本課題研究のまとめは,私たち自身の共同研究をさらに進めていくための総括ともしたいと考えた。三本の報告の詳細については,発表要旨や当日の配布資料を参照いただきたい。
|
| 文責:岸本 実(滋賀大学) |
|
|