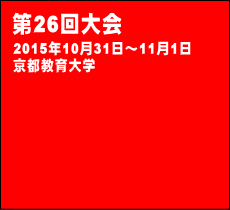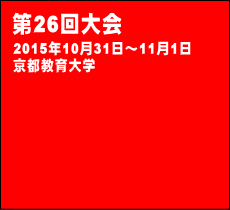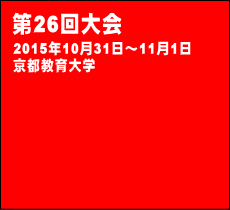
�ۑ茤���F
�@�Љ�ȂŏK��������m���E������
�@���l�ρE�s���̎w���ƕ]��
�@�@�\�����O�̊֘A�̈�̌������ӂ܂��ā\
�ۑ�u���F
�@���̊w�Z�̓W�J�Ɛl�Â���̉ۑ�
���J�V���|�W�E���F
�@���t�Ƃ��ċ��߂��鎑���E�\��
�@�@�\����ڕW�E�]���_����̒�N�\ |

���J�V���|�W�E��
���t�Ƃ��ċ��߂��鎑���E�\��
�@�\�\����ڕW�E�]���_����̒�N�\�\ |
�i��@
�R�[�f�B�l�[�^�[�F |
���@���@�G�@���i���s�����w�j |
| �w�蓢�_�ҁF |
�@���@�������i�L����w�j |
| �V���|�W�X�g�F |
���E��w�@�ɂ����鋳���{���ƌ��C
�R�@��@�Y�@��i�Q�n��w�j
�����{���̉^�c�ƕ]���ɂ݂���{�I����
�\�\������K�𒆐S�Ɂ\�\
��@�c�@�N�@�V�i�����w�|��w�j
�q�ǂ������̊肢�܂����w�Z����̎�g
���@�i�@�r�@�O�i�������s���������w�Z�j |

�@
�����{���̂�������߂����Ă��܂��܂ȉ��v���i�߂��悤�Ƃ��Ă��܂��B�{�V���|�W�E���́A����̑������{����w�ŊJ�Â���邱�Ƃ܂��A�u���t�Ƃ��ċ��߂��鎑���E�\�́v�ɂ��āA�u����ڕW�E�]���_����c�_����v�Ƃ�����|�̂��ƂɊ�悳��܂����B
�����́A�܂��i��E�R�[�f�B�l�[�^�[�̓����G��������A�����Ȋw�Ȃ́u���ꂩ��̊w�Z�����S�������̎����\�͌���ɂ��āi���Ԃ܂Ƃ߁j�v�Ȃǂ����グ�A�����{���⌤�C���x���߂�����v�������Љ��Ȃ��ŁA���ꂩ��̋��t�ɋ��߂��鎑���E�\�͂ɂ��ċc�_��[�߂�K�v�����w�E���܂����B
�ŏ��̕҂ł���R��Y�����́A���E��w�@�ɂ܂��ᔻ�I�ȁu�����i���ɋ�̓I�Ȏ��H���ӂ܂��Ȃ�����j�v�ւ́u�����v�����邱�ƂɌ��y������ŁA�Q�n��w���E��w�@�ł̎��g�݂��Љ�܂����B
���̈��Ƃ��āA�w���V���҂��܂߁A�u���g�̎��H��f�ނƂ��A���K�ƘA�������w�ۑ茤���x�̎��{�ƕ����M���C���v���Ƃ��ĉۂ��Ă���v���Ƃ���������܂����B��̓I�ɂ́A�܂��u�ۑ蔭�����K�T�v�i�P�N���U���j�ɂ����āA���ʎx���w�Z�⏬�w�Z�A���w�Z�A�c�t���ȂǁA�u�Z����z�����w�Z����S�̂̂Ȃ����c�����A�w�Z����̑S�̍\���̗�����[�߂�v���Ƃ��߂�����܂��B���ɁA�u�ۑ蔭�����K�U�v�ł́A���w�Z�E���w�Z�ł̊e12���Ԃ̎��K��ʂ��āA�u���E�����w���v�͋Ζ��Z�ȊO�ł̊ώ@�E�Q���ɂ��u����̎��H���Ȃ݂�v���ƁA�u�w���V���ҁv�͊ώ@�E�Q���ɂ��u���Ȃ̒m����Z�\�̉��P�_��F������v���Ƃ��߂����A���҂Ƃ��Ɂu�����ۑ�m������v�@��Ƃ��܂��B���̏�ŁA�u�ۑ�������K�v�i�Q�N���O����j�ɂ����āA�e���̉ۑ茤���e�[�}�̉����Ɍ��������H��30���ԍs�����ƂɂȂ�܂��B�����ł́A��w�@�̎w�������i�����ҁE�����Ɓj�Q�����y�A�ɂȂ�A����w�������{���Ă��邱�Ƃ��Љ��܂����B
���̂悤�Ȏ��H���s���Ă���Q�n��w���E��w�@�ł́A�A�h�~�b�V�����E�|���V�[�Ȃǂɂ����āA�u�ڕW�v�Ƃ���u�����E�\�́v�Ɋւ��āA�@�u�ۑ�́A�c������́v�A�A�u�Ή�����\�z����́v�A�B�u���H����́v�A�C�u���H��]�����A�čl�@����́v���l������Ă���Ǝw�E����܂����B�R�����́A���ꂼ��̒��g�̏ڍׂɂ��Đ�������������ŁA�����́u�����E�\�́v�́u�����v�ƂȂ�̂��A��q�̉ۑ茤���E�ۑ�������K�ł���Ƃ��āA���ۂ̏C�����̍s�����ۑ茤���e�[�}�̈ꗗ�Ǝ�����Љ�܂����B
�@����ɁA�u�����E�\�́v�̌`���ƕ]���ւ̎����Ƃ��āA�u���H�I�m���v�͌o���̐ςݏd�˂̒��ł����`�����ꂦ�Ȃ��ˑ��I�ő��ʓI�E���I�Ȍ����ł���Ƃ����ӌ������グ�Ȃ���A�R�����́A�����E�\�͌���Ɏ�����u�o���v�������炵����u�v�i�����j���A�u�����ҋ����E�����Ƌ����ƂƂ��ɑn�o���A�����ɃR�~�b�g���Ă����v�Ƃ����u�������v���d�v�ł���Ǝw�E���܂����B���̍ہA�u�����E�\�́v�P�̂̕]���͍���ł���Ƃ������Ƃɂ����y���܂����B
�Q�l�ڂ̕҂ł����c�N�V�������́A������K�̓��{�I�ȓ����Ƃ��āA�w���\�͂₻�̊�ՂƂȂ�m���E�Z�\�ɉ����āA�u�g�����Ȃ݁v�u�����U���v�Ȃǂ́u�O�`�I�v�f�v�����߂��A���Ƃ��Č�҂��d�������̂͂Ȃ����Ƃ����₢�̂��ƁA�����ɋ�����K���߂�����{�I�ȕz�u�W�̂��邱�Ƃ��w�E����܂����B
��c����ɂ��A���{�̋�����K�̏ꍇ�A�������{�̒��ڊǗ��̎コ�ƂƂ��ɒn�����{�i����ψ���j�ւ̋��������W���������܂��B�Ƃ��ɓ��{�̑�s�s���ł͈�̋���ψ���̊NJ����ɑ����̑�w���W�����A����ψ���ւ̕��ׂ�������Ȃ��A�u��w����ʂɒu�����W�v���蒅���Ă���Ƃ���܂��B�܂�A���܂��܂Ȍ�����L���鋳��ψ���A��w�ɑ��āA������K�ɎQ���ł���҂́u���E�ɏA���ӎv�̂���҂ł��邱�Ɓv�A�u�����̗p���ґI�l�������\��̎҂ł��邱�Ɓv�Ȃǂ�v�����či�荞�ލ\��������Ƃ����킯�ł��B
����ɑ��āA��c������g�����A�W�A���n��ŋ�����K�̎Q�^�ώ@���s�������ʂ��Љ��܂����B��w�哱�Ŏ��K�v���O�������A�����W����\�E���Ȃǂɔ�ׁA���{�̏ꍇ�́A����ψ���u��w��v�Ƃ����u�͊W�v�̈Ⴂ�����邱�Ƃ��w�E����܂����B
���̂��߁A���{�̑�w�ɂ����Ă͋�����K�̗v���Ɂu���v�u�ӎv�m�F���v�u�ʐځv�u���|�[�g�E���_���v�Ȃǂ́u��ϓI�v�f�v���ۂ��Ƃ������Ƃ��蒅������̂ł͂Ȃ����Ƃ����_���A�ŋ߂̊�c����̒��������ƂɎw�E����܂����B�m����Z�\�Ƃ����_�Ŋw�����i�荞�ނ��Ƃ�������߂ɁA��ϓI�v�f�i�������E�u�]�A�g�����A�ԓx�A�����U�����j�ōi�荞�ޏ�������Ƃ����킯�ł��B���ꂩ��̋����{���̂�����Ƃ��āA���t�Ƃ��Ă̗ϗ��A�m���E�Z�\�A���邢�͎��H�I�w���͂̂�������d�����ׂ����A�l���Ă����K�v�̂��邱�Ƃ��w�E����܂����B
�܂��A�����{���̒S����̖��Ƃ��āA�����҂Ƌ��t�A�ʉȊw�̉Ȋw�҂������ŋ���ɂ�����̂��i���Ƃ��u�w�т̋����́v�_�j�A���邢�͋���ψ���w���厖�����H�ɂ��ƂÂ��Ďw������̂��i���Ƃ��u���t�{���m�v�j�A�Ƃ������z�̈Ⴂ�������鍡���A������K�̕]���w�W�̋����J���Ȃǂ��s���Ă������Ƃ����߂���Ɗ�c����͎咣���܂����B
�R�l�ڂ̕҂ł��鐷�i�r�O���́A�w�Z����ł̎��g�݂����ƂɁA�q�ǂ�������w�Z���ǂ̂悤�ȋ��������߂Ă���̂��ɂ��ĕ����܂����B
���i���ɂ��A�q�ǂ������i���E���Z���j�����߂Ă��闝�z�̋������Ƃ��ẮA�u�킩��₷�����Ƃ�����搶�v�A�u���k�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������ɂƂ邱�Ƃ��ł���搶�v�A�u�N���X���܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���搶�v�A�u�N�ɑ��Ă��Ί�Ŗ��邭�ւ��搶�v�Ȃǂ���s�����Ŏw�E����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B
�����̊w�Z����ɑ傫�ȉe����^���鍑�̓����Ȃǂɂ��Ă����y����Ȃ��ŁA���i���́A�o�c�A���o�����u������w���v�Ɋւ���l�����v�i2015�N�j�ɂ����āA�u����́v��L����l�ޑ��Ƃ́u�Ɂv�̂��̂��u������Ă��邱�ƁA�܂����g���ւ�����������琭�����ɂ�钲���w�S���w�́E�w�K�����ɂ����ē������錋�ʂ��������w�Z�ɂ������g����W�x�i2009�N�j�ɂ����āu�w�Z�Ǝ������k��ی�҂Ƃ̊Ԃɋ����M���W�v�̂��邱�Ƃ��錍�ɂȂ��Ă��邱�ƂȂǂ��Љ�܂����B
���ɁA�w�Z�͂ǂ̂悤�ȋ��������߂Ă���̂��ɂ��āA���ɁA�u���ƂÂ���Ɛ��k������[�߂�v���Ƃ��d�v�ł���Ǝw�E���܂����B�킩����ƂÂ���ƁA���ꏊ�Â�����J�Â���͖��ڂɊւ���Ă���Ƃ��āA���҂ɐϋɓI�Ɋ֗^�ł��鋳�������߂��Ă���Ɛ��i���͎咣���܂����B���ɁA�u�w�Z��������ۑ�ɒ��ށv���������߂��Ă���Ǝw�E���܂����B�s�o�Z��g�q�ǂ��̕n���h�����ƂȂ�Ȃ��A�����̉ۑ�ɒ��ނ��Ƃ��d�v�ɂȂ��Ă���Ƃ���܂����B��O�ɁA�u�q�ǂ����������W���ɖ{�C�łԂ���v�K�v�����w�E����܂����B�Ƃ��ɍŋ߂̋�����K�����犴���邱�ƂƂ��āA��V��������w���č쐬�Ȃǂɂ����Ă��܂����Ȃ����Ƃ��ł������ŁA�ǂ����u������܂�v�Ƃ�����ۂ��邱�ƂȂǂ���A����I�Ȕᔻ�I�v�l�͂Ȃǂ����߂���̂ł͂Ȃ����Ǝw�E����܂����B
�@�܂��A�����̎����E�\�͂�L���w�Z�Â���Ƃ��āA�Ǘ��E�̖������d�v�ł���A��l�ЂƂ肪�u�L�\���v�u�������v�u�W���v�����߂Ă������Ƃ��ł���悤�Ȋ��Â���̕K�v�����w�E����܂����B�Ō�ɁA�m���E�Z�\�ɉ����A��F�m�I�Ȕ\�͂̑�����w�E����鎞��̂Ȃ��ŁA��w�S�N�Ԃʼn����ǂ��܂ň�Ă邩���l���Ă����K�v������Ƃ���܂����B
�ȏ�̂R�l�̕��āA�w�蓢�_�҂ł���،�����Y�������͎��̂悤�Ȏw�E������܂����B�܂��A�R�����̕ɑ��ẮA���l�ȕ������z�肳��鋳����K�ɑ��āA����I�ȕ]���w�W���쐬���邱�Ƃ͍���ł͂Ȃ����A�쐬�����Ƃ��Ă��w���̉��P�Ɏ�����悤�ȗL�v�ȏ��������̂ƂȂ邩�A�܂��u�ۑ�́E�c������́v�̈琬�́A������o�����̂��̂������萫�䂦�ɍ���ȕ���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����_���w�E����܂����B
���ɁA��c����̕ɑ��ẮA�Ƌ��擾�Ґ��Ǝ��ۂ̋����̗p���Ƃ̊ԂɃM���b�v�����邱�Ƃ��ǂ����邩�A�܂������̗p�����̖ʐڂŎ����E�\�͂����肳��錻��ɂ����āA�m���E�Z�\����Ȏw�W�Ƃ��ĕ]�����Ă�����w�ɂ͂������������ł���̂��Ƃ����_���w�E����܂����B
����ɁA���i���̕ɑ��ẮA�����{���n��w�̏o�g�ł͂Ȃ��搶���ǂ��搶�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��ǂ��l���邩�A���ǂ̂Ƃ���A���Ƙ_���Ȃǂɂ��ۑ�T���͂����������ɂ����ĉʂ����������傫���̂��ǂ����Ƃ����_���w�E����܂����B
�����ɂ��āA�R��������́A�������k�x���\�͂�w�Z�^�c�͂����܂��Ă���Ƃ������o���@���̊ԂɌ����邱�Ƃ��Љ�ꂽ��ŁA����I�ȃ��[�u���b�N�͂���ɂ�����������Ȃ����A���Ƃ����肩����Ƃ��ɂǂ�Ȏw�W��p���邩�Ƃ����_�ɂ��Ă͍l���Ă������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝw�E����܂����B
��c�������́A�J���������̂��ƁA�����̗p���̑����ɖ�N�ɂȂ��w���o�Ă���Ȃ��ŁA�d�g�݂��̂��̂��l����K�v�̂��邱�ƁA����ɑ�w���ア�ʒu�ɒu����Ă��錻��ɂ����āA���܂��܂ȑ�w���A���̂Ƃ��ċ��͂��A���ꂵ���w�W���Ă��Ă��������Ȃǂɉ\�������o���邱�Ƃ��w�E����܂����B
���i������́A�����{���n��w�̏o�g�ł��邩�ǂ����Ƃ����_�ɂ���قǂ̍��͂Ȃ��A�ނ��닳�t�ɂȂ��Ă��炪�u�����v�ł��邱�Ƃ��w�E����܂����B
�����̎��^�����ɉ����A�t���A������ӌ����o����܂����B���Ƃ��A�����҂����H������܂Ȃ����������ɂ����߂���̂ł͂Ȃ����A�n����L�̉ۑ�ւ̑Ή��Ƃ������_�͋����{���ɂ����Ăǂ̂悤�Ɏ��グ�邱�Ƃ��ł��邩�A�w�Z�ɂ����Ă͎��ƂÂ��肪��ŋ��ȓ��e�ւ̗������d�v���Ǝv���邪����ɂ��Ăǂ��l���邩�A�Ȃǂ̈ӌ����o����܂����B
�܂��Ō�ɁA�ŋ߂̊w���͎��Ԋ����l�܂�Z�����Ȃ��Ă���Ƃ��āA��w�����̂Ȃ��ɗ]�T���Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ����O���鐺���o����܂����B�o�d�҂���́A���肪�����Ȃ�̂Ȃ��ŁA������͓Ɨ��������z����ł���Ƃ����w�E��A��w�Ƃ��Ă����ɖL���Ȋw�т��w�������ɒł���̂����d�v�ɂȂ�Ƃ����w�E���Ȃ���܂����B |
| ���ӁF����Ƃݎq�i���s�����w�j |
|
|