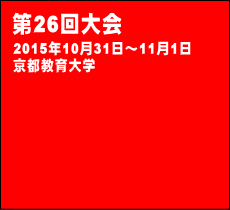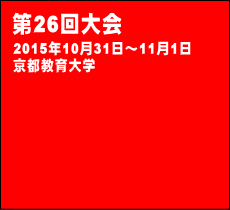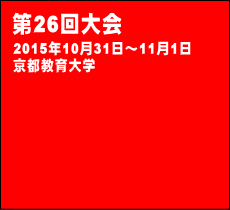
課題研究:
社会科で習得させる知識・理解と
価値観・行動の指導と評価
―国内外の関連領域の検討をふまえて―
課題講演:
戦後の学校の展開と人づくりの課題
公開シンポジウム:
教師として求められる資質・能力
―教育目標・評価論からの提起― |

課題講演
戦後の学校の展開と人づくりの課題 |
| 講師: |
木 村 元 (一橋大学) |
| 司会: |
山 根 俊 喜 (鳥取大学) |

本講演は,戦後70年に当たって,学校,教育,社会の変容を捉え,教育目標―評価研究の課題をとらえなおすことを目的として企画された。講演者は木村元氏,講演は2015年3月に発刊された,木村元『学校の戦後史』(岩波新書)を元におこなわれた。以下,講演の要旨と議論をまとめておく。
1 課題の提示
今日の教育問題の底流にあるのは,学校による人間形成という方式が揺らいでいるということである。近代学校,その上に形成された「日本の学校」,さらにその上に形成された「戦後の学校」という三重の構造の中に私たちの学校が存在し,これが基底の部分も含めて大きな転換点にあると思われる。その様な捉え方に基づき,学校の展開過程の特徴を捉え,人づくりの機関としての学校の課題を考えてみたい。
2 学校の人間形成
学校における人間形成は,人類史の上で特異な形態である。人類はほとんどすべての時代,生活に汲々とし,生活の中で次世代の再生産を行ってきた。人類の歴史全体に比すると学校による人間形成の歴史の長さは人類史の中では極めて短い。
では,人類史の中で圧倒的長期にわたる学校のない時代の人間形成はどの様に行われていたのか。そしてこれがどの様に転換したのか。これを端的に示す絵画資料がある。教育史家の宮沢康人氏が紹介している19世紀前半の靴屋の画である。靴屋は次世代の靴屋を養成する為にどうしたか。その後継者養成の方式は端的には「一生懸命良い靴を作ること」であった。そこには「教える」という行為はない。原ひろ子が紹介しているエスキモーの子どものカヌー造りも同様である。子どもは大人に教わることなく「自然に」その技術を獲得している,さて,この絵の靴屋は靴づくりに集中していない。宮澤康人氏はこの靴屋が斜めを向いたその瞬間に,文化伝達の一つの転機があると指摘している。つまりここで「教える」という行為が生まれ,これが人間の形成方式の転換を導いた。
この様な形成方式の転換がシステムとなるには様々な展開あった。その一つがランカスター法である。ここでは,「靴屋になりきる」といった形で文化が獲得されるのではなく,分析した知(その代表は文字)が,特別な空間で教えられる。つまり文化伝達が工夫された形で行われ,ペダゴジーの世界が生み出されたのである。ランカスター方式は,各国に伝播して近代学校を生み出すことになるが,その過渡的な状態を示しているといえる。
3 「日本の学校」の形成
近代学校が日本に移入されると,日本社会の変容とともに作りかえられた。近代学校から「日本の学校」,「戦後の学校」,「現代の学校」が拡大しつつ生まれてくる。これを包含関係で示すことができるが,一番外側にある「学校方式以外の人間形成」と「現代の学校」の境界線は点線で示してある。このようにその境界が曖昧になっているのが現代の問題状況を示している。
さて,「日本の学校」の特徴はどの様なものであったか。従前の教育機関であった寺子屋は,師匠と子どもが一対多の関係だが,「一斉」「教授」しているわけはなく,子どもそれぞれが有する課題に対する個別指導が基本であった。これに対して,近代学校の教授の在り方を示した図は,国家の定める同一の内容を一時に多数の子どもに一斉に教授されたことを示している。
日本が採り入れた学校システムは,帝国大学を頂点とするピラミッド型の体系であった。これは要するに知識の階層秩序に対応して,学校や等級を整序したものであり,大学に向かってこの階段を登っていくことが学校に行くということであった。進級や入学は修得主義型の「試験」によっていたので,「学校」とは「試験」であると表現できるものであった。
しかし,この学校体系に参入したものは少数であった。当時の日本の人間形成方式は,圧倒的に「自然」に人を育てるシステムだったからである。国民形成という視点からは,子どもを学校に来させなければならない。この課題への対応が日本の学校の基本的性格を形成した。その一つが,試験-修得主義のシステムから,学級編制等ニ関スル規則(1891年)を契機とした,履修主義のシステムへの転換であった。そこでは,知識の修得よりも「教師と生徒が共にいる時間」が重要とされた。つまり,先生と生徒達が創り出す共同性が重視されたということである。その「共同性」を創り出すには相当な苦労と工夫が必要であった。極端な例だが,20世紀初頭のある教師の日誌のなかの教室の図にはムチが描き込まれている。極端にはムチがなければ学級を統制することが難しかったと思われる。天皇制教育における慈恵-服従関係とパラレルに,教師(生活綴方教師なども含めて)-子ども関係は無償の献身-服従の関係として組織され,これを元に学校の共同体が作られていった。学校の日常ということで言えばこうした関係は戦後も引き継がれている。
4 戦後の学校
学校の課題を,生活世界,政治(公共社会),経済(市場)という三つの関係の在り方から成立すると考え,戦後の学校を三つの時期に区分したい。第1期は,1950年代後半(戦後民主主義社会の担い手づくりを課題とする教育)まで,第2期80年代まで(産業化社会の構築に対応する教育)。第3期はそれ以降現代に至る時期(新たの課題への対応と学校の土台の再構築)である。
第1期の課題は,憲法・教育基本法を基礎に戦後民主主義社会の構築を担う人間をどう教育するかということであり,これを象徴するのが義務制の新制中学校の設立である。とはいえ,在ってはならないがなくてはならないという微妙な位置づけを与えられた夜間中学や,制度的にはないものとされたが存在し続けた朝鮮学校など,独特の外延をもちつつ学校制度が構築された。
第2期の学校は,政治から経済に大きく軸足をずらしていく。この時期,就学強制のない高校という「いかなくてもいい学校」にみんなが行くようになる。高校進学率は急上昇し1970年代中頃にはプラトー状態に達する。学校化社会の出現である。同時に1970年代中頃以降,減少しつけていた不登校率が反転し,V字型を描いて増加しつつづける。つまり,「いかなくてもいい学校」にみんなが行き始めた時,子どもは学校に行かなくなったといえる。
同時にこの時期,企業社会の成立に伴って,教育-企業-家庭が結びつき,教育は労働力を企業に提供し,企業は賃金を家庭に提供し,家族は子どもを学校へやるという形で強固なシステムをつくりだした。このシステムが動き出すと,学校に行くのが当たり前で,学校で何を教え・学ぶかということが問われなくなってしまう。
教育と学校の変容は,教育学の変容からも捉えられる。例えば岩波教育講座の変遷を辿ってみると,幅広い視野から教育を捉えた『教育』(1952-53)から,『現代教育学』(1960-62)では教育内容,『子ども発達と教育』(1980)では発達,『教育の方法』(1987)では内容と発達を結ぶ方法へと展開している。『教育の方法』では,学校方式よる人間形成の「葛藤」,揺らぎがみられるが,1998の『現代の教育』に至ると,学校は,告発・模索・転換・再構築されるものして捉えられ,その後は,講座本が発行されない状況が続いた。現代は人間形成の学校方式と共に,これを支える枠としての教育学への信頼が崩れている状況が現出している。
第3期は,政治,経済よりも生活世界の再構築が課題となっている。日経連の「新時代の日本的経営」(1995)にみる様に,日本社会を支えてきた教育-企業-家庭の循環関係が崩れた。この中で,学校の基盤が揺らぎ,学校の課題とは何かが問われている。学校への就学=教育権保障という構図が揺らぎ,不登校の増加に見られる様に教育への権利と就学の権利が背反するという事態が起き,この中で「多様な教育機会確保法案」が作られるなどしている。また,全生研も従前の「民主主義の訓練」から,その前提としての集団の中で認められる「居場所づくり」を課題とするに至っている。「チーム学校」の提起に見る様に,学校=教師と子どもの共同体という関係が揺らぎ,そこに福祉,心理支援等の関係者が入らないと学校が成立しなくなってきている。
5 学校の課題
以上を踏まえて,現代学校の課題を考えてみたい。
これまでは,学校が人間形成の土台であり前提だという自明の共通認識があったが,これが崩れてきている。現在,学校という場を成立させる為にはケア(元来エデュケーションの概念に含まれていたのだが)の視点が不可欠になっている状況にある。ところで,「教育」は「よくすること」が課題だが,ケアは「そのままでよい」という思想であり,学校において併存するには葛藤がある。これが顕在化しているところに今日的な課題がある。
また,今日,不登校やオールタナティヴスクールに関わって,当事者主権に基づく自己決定が強調されるが,これとこれまで学校を成立させる基盤であった教育目標論における代行論との対立が顕在化してきている。こうした問題に教育目標―評価論がどの様に対応していくのが問われている。
最後に,教える行為を成立させる際,教科と生活を繋ぐことが最大のポイントだった。今日重要なのは,子どもの生活と同時に,社会変動と結びついて変化している子ども達の学校の生活,これを成り立たせる為の教科の役割,さらに既存の枠組みを超えた教科(教える中身)の在り方が問われているという点である。
6 討論
討論では以下の点について応答があった。論点のみを記しておく。
①人間形成全般と学校教育の関係をどう捉えるのか,学校の固有の役割は何か。
②戦後第2期,子どもの生活世界は狭められたが,なくなったわけではない。これをどう捉えるのか。
③報告では学校は初等中等教育が中心に展開されたが,とくに今日では,大学まで含めて一つのロジックで語られるに至っている,これを含めて考えると変化がより鮮明になるのではないか。
④ケアと「教育」は概念的には対立する側面があるかも知れないが,実践的には「うまくケアされれば,よく変わっていける」ということがあるのではないか。また逆に,教科学習がうまくいけば学級が落ちつくといったこともある。これをどう捉えるのか。 |
| 文責:山根 俊喜(鳥取大学) |
|
|