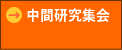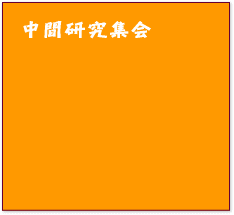index > ���Ԍ����W��
|
|
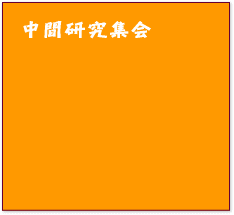
��2013�N6��1���@
�@�@�����{���ɂ�����h���h�ۏ̘_�_�͉����H
��2012�N6��9���@
�@�@���ƂɊ������]���̂�������߂�����
��2011�N6��11���@
�@�@����ڕW�E�]��������20�N��U��Ԃ�
�@
��2010�N5��22���@
�@�@���E�Ƃ��Ċw�э����R�~���j�e�B��
�@�@�@�@�@�x����]���̍\��
��2007�N6��16���@
�@�@���{�̊w�Z�ڑ��̉ۑ�
�@�@�@�\���B�̓����܂��ā\
��2006�N6��10���@
�@�@�����Y�̍��Ǝv�z
��2005�N7��9���@
�@�@�V�������E�̔����A�V���������̔���
�@�@�@�\�w�w�͂ւ̒���x�Ƃ��̌�\
��2003�N5��10���@
�@�@��������̐l�Â���ƁC��ƎЉ�̐l�Â���
�@�@�@�@�\�ڕW�E�]���_�ɂ�����C
�@�@�@�@�@�@�@����w�̌ŗL���Ƃ͂Ȃɂ��\
��2001�N4��28���@
�@�@�w���v�^�����ŕ]���͂ǂ��ς�邩
��1998�N5��31��
�@�@��P���F����ے������̔ޕ���21���I��
�@�@�@�@�@�@�@�]���������ǂ̂悤�ɓW�]���邩
�@�@��Q���F������v�̓W�J�ɑ����āC��x��
�@�@�@�@�@�@�@�킽�鋳��ے������̓����𖾂�
�@�@�@�@�@�@�@���ɂ���
|

���E�Ƃ��Ċw�э����R�~���j�e�B��
�x����]���̍\��
�\�����w�̎��g�݂�����Ɂ\
|
2010�N5��22��
�������w�����L�����p�X
|
�w�э����R�~���j�e�B�Ƃ��Ă̊w�Z���x�������
�\���E��w�@���_�Z�̎��g�݂���\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�q�@�c�@�G�@��
�i����s�������w�Z�j |
|
�w�Z���_�̋��E��w�@�ɂ�����]���̏d�w��
�@�\�������H�����ɂ��e�c�ց\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|
�w�K�̐��E�Ƃ��Ă̋��t�ɕK�v�Ȕ\�͂��ǂ��ۏ��邩
�@�\�����{���X�^���_�[�h����̎��g�݂���\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���@�c�@�K�@�b
�i�����w�j |
|
�����I���W���x����Ȏ@�̊��
�@�\���H�R�~���j�e�B�̃t���N�^���\���\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|
�@�R�����e�[�^�[�F�@��@�p�@�^
�i�_�ˏ������q�w�@��w�j
�c�@���@�k�@��
�i���s��w�j
�i��F ���@���@�M�@�L
�i�����w�j
|
|

�@
�@�܂��C��\�����̓c���������C�n��20�N���}�����{�w��̗��j��C����ڕW�E�]���_�Ƃ������p�ɂ��Ă̐����������Ȃ���C�J��A���s���܂����B
�����Ďi��̉�����������|�������s���܂����B�����C�}�W�J�������鋳���{���ɂ����āC�����w���E��w�@�̓��f���Z�̈�ƂȂ��Ă���B�{�����W��ł́C���E�Ƃ��Ċw�э����R�~���j�e�B�iprofessional learning communities�j�̎����Ɍ����������w�̎��g�݂̑S�e���T�ς��Ȃ���C���̃R�~���j�e�B���x���Ă���]���̍\���ɖڂ������C����ڕW�E�]�������̐V���ȉۑ��T��B�����ŁC���E��w�@�̋��_�Z�ł��镟��s�������w�Z�̖q�c�����瓯�Z�̎��g�݁C�����w�̏��؎�����͋��E��w�@�̎��g�݁C�����w�̔��c�������͕����w����n��Ȋw���̎��g�݂ɂ��ĕ���B�Ō�ɕ����w�̖�����C���_�Z�E��w�@�E�w���̎O�҂̔w��ɂ��鋤�ʂ���c�݂ɂ��ĕ���B�ȏ�𒆊ԏW��̊���|�Ƃ��Ē��܂����B
�q�c������͎������w�Z�ɂ�����ߋ�6�N�Ԃ̊w�Z���v�̉ߒ��⌻�݂̎��g�݁C����̓W�]�ɂ��ĕ�����܂����B�̗v�_�͎��̒ʂ�ł��B
�������w�Z�͂R�N�O�ɐV�Z�ɂɈړ]���ꂽ�B�V�Z�ɂ͋Ȑ��̃��C���Ō`����C�w�Z���z�ɂ��傫�ȓ���������B���̊w�Z���z�Ɏx�����Ȃ���C�يw�N�N���X�^�[���C���ȃZ���^�[�����C�n��Ƃ̘A�g�Ƃ��������Z�̗��O���������錻�݂̎��g�݂��s���Ă���B
�����������Z�̊w�Z���v�͂U�N�O�ɂ����̂ڂ�B���v�̂��������́C���k�����Ƃ�w�K�Ɋւ��Ē��w�Z�����̎v���o�������Ă��Ȃ����Ƃɂ������B�w�Z�����̑唼���߂���Ƃ�ς��邱�ƂŁC���U�ɂ킽���Ċw�ԗ͂�{���ׂ��C���Ɖ��v����w�Z���v���n�߂��B
���Z�̎��Ƃ͖������^�w�K��i�߂�ׂ�1�R�}70���ōs���Ă���B�������C�w�K���e�̒蒅��������w�K�ł͖ԗ��ł��Ȃ����������邽�߁C���K�Ȃǂ��s��20����RE�^�C���ireflection, review�j���݂�����悤�ɂȂ����B5�N�ڂ��}����70�����Ƃɂ��C���Ƃ̘g�g�݂���������C�ڕW�����m�������悤�ɂȂ����B
�w�K�`�Ԃɂ����Ă��C���w����̓]����}��C�V�����w�т�Nj����Ă����B���̂��߁C�V�������[�����K�v�ƂȂ�C���k��ی�Ҍ����̊w�K�����SSL�iShimin Study Life�j��ҏW�����B�ҏW�ɂ������ẮC�e���ȂŁu�Ȃ����̋��Ȃ̊w�Ԃ̂��v�Ƃ����₢����o�������B����SSL�͋��ȂƋ����₢�����@��ɂȂ��Ă���B
�ȏ�̂悤�ɁC�q�c���͎������w�Z�̊w�Z���v�ɂ��Đ������������ŁC���猻��ɂ����鋳�t�̊w�т̎���Ƃ��ē��Z�̎��g�݂���܂����B
���Z��]�o������������C�u�������w�Z�͊w�ׂ�w�Z�������v�C�u�������w�Z�œ�����O�̂��Ƃ������łȂ������v�C�u���Ԃ̎g�������S���Ⴄ�v�Ƃ����������B�������w�сC��������@����w�Z�ɕK�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B���������w�т́C�Ƃ��ɐ�������荇�����Ő��܂��̂ł���C��肠���R�~���j�e�B���`�����邱�Ƃ��w�Z�ɕK�v���낤�B
���̂悤�ɓ��Z�ł͊w�т̃R�~���j�e�B���`������Ă���B���t�͎q�ǂ��̊w�т���w�сC�R�~���j�e�B�ɉ����n��̕ی�҂���C���E��w�@�̃C���^�[���̉@������w�ԁB���̂悤�Ɋw�т��b�I�ȃl�b�g���[�N�ƍl���邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�B�܂��C���Z�̋��t�̋����̏�ł���Z�����C�ɂ����Ă��C��肠�����s���C�e�[�}�C�r�W���������L����Ă���B�u�Ȃ��m�[�`���C�����v�C�u����Ȏ��������ی�҂������Ƃ���Ɓv�C�u70�����ƂŎɑΉ��ł���̂��v�C�u���Ƃ���N���X�^�[�̖��v�Ƃ��������Ƃ����C�N�z�̐�����ăO���[�v�Ō�荇����B�����ɓ��Z�̃I���W�i���e�B�̌�����ƍl���Ă���B
�Ō�ɖq�c���͓��Z�̊w�Z���v��]���Ƃ������_���琮�����C���k�̐��������������Ă����_�C�w�Z����Ƃɂ��Ď����̌��t�Ō�邱�Ƃ��ł��鋳���E���k�������Ă����_�C�n��̕��̎Q�����������_���C���v�̉ߒ��Ō���ꂽ�ω��Ƃ��ĕ��܂����B
�����āC���؎����畟���w��w�@�ɂ����鋳�E��w�@�̑n�݂⋒�_�Z�ł��鎊�����w�Z���x���鋳�E��w�@�ł̎��g�݂ɂ��Ď��̂悤�ɕ�����܂����B
���N��3�N�ڂ��}���鋳�E��w�@�́C���̖����₠����C�@�\���ς�낤�Ƃ��Ă���B�]���̊J�����Ɋ�Â������{���ɑ��C��含���w�т̒��S�ɐ����������{�����K�v�ɂȂ�ƍl������B
���E��w�@�ɂ́C�w������̐i�w�Ҍ����ƌ��E���t������2�̃R�[�X������C�Ɨ������J���L���������g�܂�Ă��邱�Ƃ������B���E�Ƃ��Ă̈炿�C����p���̃T�C�N�����l����ƁC2�̃R�[�X�̗��ݍ������l����K�v������B
�����ŁC���E��w�@�ɂ́C���t�̐��U���B���x������������߂��Ă���B�w�Z�ł̐����C�܂�e�c���x���鋳�E��w�@�ɓ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��Ƃ͑�w�����ɂƂ��Ă��e�c�ɂȂ�̂ł���C���t�Ƒ�w�����ŁC�����\���������Ă�����̂����K�v������B
���؎��͈ȏ�̂悤�ɋ��E��w�@�̌���Ɖۑ�����������ŁC���E��w�@�ɂ�����ڕW�ݒ�ɂ��āC�����w�ɂ�����2002�N�̑�w�@���v�����ƂɁC���̂悤�ɕ��܂����B
�����w�̋��E��w�@�ł͂܂��C�@�����җ{�����S������E�{���E���H�I�w���͂̈琬�ցC�A�����l�̌��r���S����w�Z�Â���E�g�D���v�̂��߂̑�w�@�ցC�B��w�Ƌ���ψ���̖��A�g���痼�҂������������t����ցC�C�m���K���E�~�ϒ��S�̊w�K�ς���Љ�Q���^�̊w�K�ςւƂ������ڕW�̓]�����s��ꂽ�B�����āC�����̖ڕW�Ɍ����āC�w�Z����̃��Y���ɍ��킹������ے��̕Ґ��C�w�Z���_�𒆐S�Ƃ��鋦���̍\�z�C�w�Z�̕�����ۑ���w�Z�œ������t�Ƌ������ĉ��������w�@�̑n�݁C���H�����̏W�ςƋ��L��i�߂�l�b�g���[�N�̍\�z�C��w�����̋������i�߂�ꂽ�B
�����ɋ��t�̐�含�ɂ��Ă��������ꂽ�B�]���̈�t��ٌ�m�����f���Ƃ������E�ς���V���C�R���{���[�V�����̃v���Ƃ��ĊW�����d�������w�тւ̓]�����ڎw���ꂽ�B������������邽�߂ɁC�@�w�Z�̃��Y���ɂ����Ă���C�A�O�Ƃ̂Ȃ���̍L����̒��ōč\������C�B�w�Z�����_�Ƃ��钷���I�ȃv���W�F�N�g�Ƃ���45�P�ʂ��@�\����C�C�����ł̃v���_�N�g�ƃp�t�H�[�}���X��]������C�D�w�Z�̓����Ɍ������āC���H�̋��L��ʂ��ċ�������������g�D���v�C�E�Ȏ@�I���H�͂��琬���C�\������C�F�w�Z�̊O�ɑ��āC���H���W�ς��C���L���Ă�����l�b�g���[�N�C�Ƃ������v�f�������������ے����l�Ă��ꂽ�B
�ȏ�̓]�����o�Đ��܂ꂽ�����w�̋��E��w�@������̋��E��w�@�݂̍���ɗ^���鎦���Ƃ��ď��؎��͎��̂悤�ɕ��܂����B
����̋��E��w�@�Ƃ��ẮC�^���̉ۑ�̉��ŁC��u���鋳�t�̃X�g�[���[�C�g�D�̓W�J��]���̒��S�ɐ�����K�v�����邾�낤�B�{�w�͎��H�I�Ȏ���ƌ��̌X���W�̒��Ŕ|���鋳�t�̐�含�����o���C��ʉ��i���H���̍쐬�j�𑣂�����ے��Ɏ��g��ł���B�{�w�̋��E��w�@�ł�1�N��2�x�C���E���h�e�[�u����݂��C��荇���̏��ݒ肵�Ă���B���������Ȏ@�̃v���Z�X���̂��̂�����ے��ɑg�ݍ��܂�Ă���B�����ł͎��ȕ]���i���ȏȎ@�j����荇���C���ݕ]���i���ݏȎ@�j���o�邱�ƂŁC���I�ɍ��܂�C���t��g�D���������Ă������Ƃ�ڎw���Ă���B���������v���Z�X���C���t�Ƃ������Ǝ҂���C�����E�Ō�E�Љ��ً̈Ǝ҂ւƊg�債�C�܂��Ȏ@�̃X�p������X�́C��N�́C�\�N�̂Ƃ����悤�Ɋg�傷�邱�ƂŁC�Ȏ@�̎������܂�B
���E��w�@�̋���ے��ł́C�q�ǂ��̊w�сC���t�̊w�сC��w�����̊w�т����^�ʑ��̍\���������Ȃ���W�J���Ă����\�z�ɂȂ��Ă���B��w�̂e�c����C��w�@�S�̂̂e�c�ցC���E��w�@�S�̂ō��グ��e�c�ւƓW�J���Ă������Ƃ����҂����B���݁C�����̎��H���ǂ��ǂ݉����̂��C�ǂ��܂Ƃ߂Ă����̂��Ƃ������Ƃɂ����g��ł���B���̒��ŁC�r�W���������L���C�w�K��[�߁C�Ȏ@�̍��Ղ��c���悤�ɂ��Ă���B
���c�������́C���E�ے��̎��I����Ɋւ��镟���w����n��Ȋw���̎��g�݁C���Ɂu�����{���X�^���_�[�h�v�̍쐬�ɂ��Ď��̂悤�ɕ�����܂����B
�����w�ł́C�V�������t����݂̍���Ƃ��āC���Ɋw�Z�ɂ����鋦���̎����ƏȎ@�̐ςݏd�˂ɂ�錻�E����ɏd�_��u���Ă���B����������ɁC���t�̐��U�ɂ킽��͗ʌ`���Ɍ��т��C���E�Ƃ��Ċw�т����R�~���j�e�B���w�Z����ɔ|�������ۑ�ƂȂ��Ă���B���ɁC�w���̑����i�K����Տ��o����g�D���邱�Ƃ��ۑ�ƂƂ炦�Ă���B�����ŁC�����{���J���L�������̒��S�Ɂu������H����A/B/C�v�Ƃ������H�ƏȎ@����̂��Ƃ����ȖڌQ���ۂ��Ă���B��O�ɁC�����{���ے��S�̂ŁC�琬�����͂��`�E�I���E�L�q�E�]��������@���J�����邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă���C�u�����{���X�^���_�[�h�v�̊J���ƊW���Ă���B
���c����́C�ȏ�̂悤�ɕ����w�̋����{���ے��̕��������������̂��C�u�����{���X�^���_�[�h�v�̊J���Ɍ��������g�݂��Љ�܂����B
�u�����{���X�^���_�[�h�v�̐�s����Ƃ��āC�@�B�I�ȖڕW���͂Ɋ�Â��X�^���_�[�h����������B������������ł́C�ו������ꂽ�ڕW������Ă���C�������u���v��𗧂āC���Ƃ̗��ꂪ�q�ǂ��ɓǂݎ�����\�����H�v���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ�������̓I�ȖڕW����C�u���Ə���킫�܂��C��̓I�E�ϋɓI�ɋ�����K�ɂ����鎩�Ȃ̐E�ӂ��ʂ������Ƃ��ł���v�Ƃ�������ʓI�ȖڕW�܂ł��C����ɕ��ׂ��Ă���B���������ڕW��ԗ������Ƃ��Ă����t�Ƃ��Ă̗͗ʂ��`�������킯�ł͂Ȃ��B�\�͊ρC�w�K�ρC�]���ς���̌������o���X�^���_�[�h���l�Ă���K�v������B
�����ŁC�w�K������E�Ƃ��Ă̋��t�ɕK�v�Ȕ\�͊ρC�w�K�ρC�]���ς܂��ăX�^���_�[�h�����Ƃǂ��Ȃ�̂��B����Ɏ�����^������̂Ƃ��āC�u������H�����`�v�ɂ�����w�K�l��������������B
�u������H�����`�v�Ƃ́C���E������쓙�̌��C������K���܂Ȗڂł���B���́u������H�����`�v�̎��́C�@�J���ꂽ�����Љ�̎�́E�`���҂Ƃ��Ďs���Ƃ��Ċw�Ԃ��ƁC�A�T�����\�����Ȏ@����́C�ᔻ�I�v�l�͂�{�����ƁC�B�V��������̋��t�ƂȂ�Ⴂ����Ƃ��Ă̊w�т��o�����邱�Ƃł���B���̉Ȗڂɂ�����1�N�Ԃ�12�̃T�C�N���ɕ������C�e�T�C�N���Ń��|�[�g�Ƃ���ɑ���R�����g���J��Ԃ����B�����ł́C�V���А��̌�������H�L�^�̐ՂÂ��ƕ��́C�e�L�X�g�̌����Ȃǂ��s����B����烌�|�[�g�ƃR�����g��~�ς��āC�w�K�l��������Ă���B
�@���c����́C���̂悤�ɋ��E�Ȗڂ̋�̂�������Ȃ���C���̔w�i�ɂ���\�͊ρE�w�K�ρE�]���ςɂ��ĕ��܂����B
�܂��\�͊ς́COECD��DeSeCo�̃R���s�e���X�T�O�ɗ��r���Ă���B�w�K�ς́C���ӁE�\�z�E�\�z�E���s�E�\���Ƃ���5�̋ǖʂ��琬��T�C�N���������I�E�A���I�ɓW�J����悤�ɍl�Ă��Ă����B�]���ς́C��֓I�]���ialternative assessment�j�C�^���̕]���iauthentic assessment�j�ɗ��r���Ă���B���̕]�����@�Ƃ��Ă̓p�t�H�[�}���X�]����|�[�g�t�H���I�]�����̗p����C�w�K���@�Ƃ��Ď��ጤ����A�N�V�������T�[�`����������Ă���B�����w�ł́C�ȏ�̂悤�Ȕ\�͊ρE�w�K�ρE�]���ς̉��ŁC�����{�����s���Ă���B
�����w�ł́C�����{���X�^���_�[�h���Ă���ɂ�����C�u�������S���s���̑�\�Ƃ��āC�����E�ی�ҁE�n��Z���E���̐��E�Ƌ������C�Ȏ@�I�Ɋw�сC�s���Љ�ɑ��鉞���ӔC���ʂ������t����Ă�v�Ȃǂ̋����{����3�̎g���C�u�q�ǂ������̎v�l�Ɩ������𑣐i���邽�߂ɁC�l�X�ȕ����𗝉����p����v�Ƃ������w�����B�����ׂ�6�̖ڕW��ݒ肵���B������B�����邽�߂̃J���L�������̘g�g�݂Ƃ��āC�s���Ƃ��Ă̋��ʋ��{��C���ȌŗL�̓��e�ƕ��@�C���E�I���H�̃r�W�����Ƃ��������e���u�`�⎖�ጤ���C�w�K�l�����Ƃ��������@�ōs���悤�v����Ă���B
����炪�g�ɕt�������ǂ����́C���͂ȏ؋��ƂȂ�w�K���ʕ��i���̈���w�K�l���j�ɂ���ĕ]�����Ă���B�w�K�l���̕]���K���́C�Nj��̌p�����E�������E���s���E�d�w���E�e�[�}�̎���C����̍L����C���E�I���H�̃r�W�����Ƃ������_�ɋ��߂��Ă���B
�Ō�ɁC���c����͊w�K�l���ȊO�̋��͂ȏ؋��ƂȂ�w�K���ʕ��������ɑg�D���C�����]�����邽�߂̓��B�x�̋L�q�ƃ��[�u���b�N�������ɍ쐬����̂��Ƃ������ۑ�������܂����B
������́C�������w�Z�C���E��w�@�C�w���̂R�҂̔w��ɂ��鋤�ʂ���c�݂Ƃ��āu�Ȏ@�v���L�[���[�h�Ƃ���������܂����B
���������Ȏ@�̃v���Z�X�͊w�K�̒��ŁC���W�̗v�ł���CDeSeCo�̃L�[�E�R���s�e���V�[�ɂ����Ĉٕ����Ƃ̊ւ��̍��{�ɏȎ@�ireflection�j��u���Ă���悤�ɁC���㋳��̈�̖ړI�Ɉʒu�t�����Ă���B
�Ȏ@���v�ƂȂ��Ă���w�i���l����ƁC��������Y�ƍ\���̕ω��C�m����ՎЉ�̓����Ȃǂ���������B�����ł͒�^�I�Ȓm�̐��m�ȉ^�p�ł͂Ȃ��C�Ȏ@���E�\�Ƃ��ċ��߂��Ă���B�ߑ�Љ���̏o���_���痝�O�Ƃ��Čf���Ă������@�𗧖@����Ƃ������Ƃ͋ߑ�s���Љ�̗��O�ł���C����������ł���s���Ƃ��Ă̗͂��Ȏ@�ł���B
�ߑ�w�Z�͎s���̈琬�𗝔O�Ƃ��Čf���Ă����B����������͋���Ȑ��x�ƂȂ�C�ώ����C�W������D�悵�Ă����B�̐������ς��闝�O�Ƌ���̌���Ƃ̊ԂɃM���b�v������C�w�Z�����̖��Ƃ��ČJ��Ԃ���Ă����B
�ł͂Ȃ��w�Z�̗��O�͎�������Ȃ̂��B��ɂ́C���炪����ȎЉ�̂Ȃ��ŃV�X�e���Ƃ��āC�W�������ꂽ�葱���Ƃ��ċ@�\���C�̒��ł̔��f��}�~����\�������邱�Ƃ��������悤�B�Ȏ@�𐧌����C�W�J��j�~����\���Ƃ��āC�V�X�e���C�����́i�������E�j�C�l�̃A�C�f���e�B�e�B��3�̒�R������C���̑��d�\���̒��ŁC�Ȏ@�͐�������Ă���B
�Ⴆ�C�������w�Z�ł͏]���̊w�K����̓]���������C���t�E���k�̓M���b�v�������邾�낤�B�X�̒��ŌÂ����̂ƐV�������̂Ƃ̊Ԃ��a瀂�������B���x�́C�w�K�v���Z�X�ɑ����čl����ƁC�����ɋK�肳�ꂽ�葱���Ƃ��Ă̊w�т��w�Z�ōs���Ă���B�����ł́C�ԈႦ���ꍇ�C�v���Z�X���ᖡ��������C�������v���Z�X���o�����ق��������C�܂�C�}�j���A����ς����ق����悢�C�Ƃ��������Ɍ������Ă��܂��B���݂̊w�K�v���Z�X���̂��̂��C�Ȏ@��v�l��}�~����\��������Ă���B�܂��̌��^�C�T���^�̊w�K�ɂ����Ă����Ԃ̐���ȂǗl�X�Ȑ�����C��ʓI�Ȋw�Z�ł͈���x���낤�B�����ł��Ȏ@�͗}�~����Ă���B�����C���l�ȏ�ʂŏȎ@�͐�������Ă���̂�����ł���B
���́C�ȏ�̂悤�Ɋw�K�̗v�ł���Ȏ@�v���Z�X���j�Q����Ă��錻����������̂��C��������z���C�Ȏ@����͂�|�����H�Ƃ��ĕ����w����n��w���������w�Z�̎��H�������Ȃ��玟�̂悤�ɕ��܂����B
��̗�Ƃ��āC1�N���̗��Ȃ̎��Ƃ���������B�����ł́C�T��������C�����Ƃ��C�Ȏ@�I�Ȏv�l���\�������R�~���j�P�[�V�������Ґ������悤�C���ԕ�Łu�W�O�]�[�ǁv���̗p����Ă���B���Ȃ킿�C���k�̓O���[�v�Ŏ��������邪�C��ł͂��̃O���[�v����̂��C���k���ꂼ�ꂪ�ʂ̔ǂŎ��������̎��������B���̂Ƃ��C���ׂĂ̐��k�́C�������������Ƃ��ؓ����ĂČ�邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B�܂��C���̔ǂ̎����̉ߒ������ƂɂȂ�B������o�āC�Ăь��̎����O���[�v�ɖ߂�C���ꂼ�ꂪ�������������Ƃ����L����B���̂̂��C�������ᖡ���Ȃ����C�ŏI�I�ɂ̓��|�[�g���쐬����B���̃��|�[�g�ɂ����Ă��C�����̒T���̃v���Z�X��H��Ȃ�����J�����B
���̎��Ƃɂ͏d�w�\�����������C�Ȏ@�̃T�C�N������������Ă���B��̒P���Ōo���������Ƃ�Y�݂����|�[�g�ŏȎ@���C���̒P���Ƀ`�������W����Ƃ�����ɒP���Ԃł��Ȏ@���J��Ԃ��K�v������B���������T�C�N����������悤�ɔN�Ԃ́C3�N�Ԃ̃J���L��������g�ݑւ���K�v������B
�Ȏ@�̃T�C�N�����x���鎲�Ƃ��Đ���̕��݂�Օt����L�^���K�v�ƂȂ�B�������w�Z�ł́C���t�����������̒��Ŏ��H�E�Ȏ@�̐���̃T�C�N����҂�ł���B���E��w�@�ł��C���l�̍\���œW�J���Ă���B���ꂼ��̃R�~���j�e�B���L�^����Ďx�������Ă���B���H�E�Ȏ@����R�~���j�e�B�C������x�����w�@�C���������@�\�����߂��Ă���Ƃ�����B
�ȏ�4���̕҂̔��\�ɑ��C�R�����e�[�^�[�ł���Έ����́C�����̂悤�ɐ������܂����B
���ꂼ��̐搶����C�����w�����g��ł���w�Z�Â���⋳���{���ے��̉��v�ɂ��ĕ��������B�����͎��̍����w�тݏo�����߂́C�w�Z�̓��ݓI�Ș_������̐��x���v�ƌ����悤�B�����ł́C�q�ǂ��Ƌ��t�C��w����C�n��̊w�т̑����`���L�[���[�h�ɂȂ��Ă����B
���̏�ŐΈ����́C���ɁC���H�ɂ����ĖڕW�ƕ]���̃T�C�N���͓��݂��Ă�����̂ł���C�n���I�ȋ�����H�ɂ����ĖڕW���ǂ����m������C�q�ǂ������̐��ʂ��ǂ��]������Ă���̂���T��̂��C����ڕW�E�]���_�Ƃ����ϓ_������H�͂���Ƃ������Ƃ��Ƃ������ƁC���ɁC�]�������E��������̒��Ř_�����Ă����ڕW�E�]���_�������{���ے��Ƃ�������������ɓ����`�œK�p�ł��邩�ɂ��Č����I�Ɍ�������K�v������Ƃ������ƁC�Ƃ���2�̖��ӎ��������܂����B
����2�̖��ӎ�����C�Έ����͖q�c���ɑ��āC70�����Ƃɂ�����ڕW�̖��m���͋�̓I�ɂ͂ǂ��������Ƃ��w���Ă���̂��B�w�Z���v�̐����̔��f�͉����w�W�Ƃ���̂��B�����I�Ɏq�ǂ��ɂǂ������͂����C�ǂ��������ʂ��c�����̂��C�܂�������ǂ���̓I�ɕ]�����Ă���̂��C�Ƃ�����������܂����B
����ɑ��q�c�����玟�̂悤�ȉ�����܂����B
�������w�Z�ł́C�q�ǂ��̌�肪������悤�Ȋ�����ݒ肵�C�q�ǂ��ƑΘb���Ȃ���]�����Ă���B�w�Z���v�Ƃ��Ă̕]���������������H�̐ςݏd�˂���C�����W�]�ɗ������]�����ł���ƍl���Ă���B�w�Z�S�̂̕]���Ƃ��ẮC�q�ǂ��������ǂ̂悤�Ȍ�肪�ł���悤�ɂȂ����̂��C�ɏœ_�ĂĂ���B
�����āC���؎��ɑ��ẮC�q�ǂ��C���t�C��w�����̊w�тɑ����`���������ŁC�q�ǂ��̊w�тƐ��E�̊w�т̈Ⴂ�͂ǂ��ɂ���̂��C���t�̐����C�g�D�̐����ɂ����č��܂��Ă��鎿�Ƃ͉����C�Ƃ������₪����܂����B
����ɑ��C���؎�����͎��̂悤�ȉ�����܂����B
�m���E�Z�\�ł͂Ȃ��C���p�ɓ�����v�l�́E���f�͂�ڕW�Ƃ��]������ꍇ�C3�҂̊w�т͑����ȕ���������̂ł͂Ȃ����B�������z���C�V�������Ƃɒ��킷��Ƃ��������̃v���Z�X�͋��ʂ��Ă���B�܂��C���t��g�D�̎��̍��܂�͋�̕��C���Ȃ킿�C���t�����ۂɏ������������H���C�w�Z�ɂ����鋳�t�̊���C�Ƃ��������������邱�Ƃ���̎肾�낤�B
�܂��C���c����ɑ��ẮC���r���Ă����֓I�]���Ƃ����]���ς́C�X�^���_�[�h�Ɋ�Â��p�t�H�[�}���X�]���Ƃ͋������Ƃ�]���_�ƍl�����邪�C���̃M���b�v���ǂ����߂�̂��B���ꂩ��C�ɂ������w�K���ʕ��̕]����́C���H�I�w���͂Ƃ������́C��w���Ƃ��Ă̊w�K�\�͂ɂ�����鍀�ڂ̂悤�Ɍ�����B����͑S�̂̃J���L�������̒��łǂ������ʒu�Â��ɂ���̂��C�Ƃ������₪�Ȃ���܂����B
����ɑ��C���c����͎��̂悤�ɉ��܂����B
�m���ɃX�^���_�[�h��ݒ肷��Ƃ������z�Ƃ̊Ԃɍa�͂���B�������C�w�K���ʕ��ɉ��炩�̐���������̂͊m���ł���B�����Ă��ꂼ��̊w���ɔ��B�ۑ肪����B���������_�𑨂����鐅����[�u���b�N��͍����Ă���B�܂��C���Ƃ̎���ɑ��ẮC�p�t�H�[�}���X�̕��������K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B���̂����ŁC�p�t�H�[�}���X���̊��肪�K�v��������Ȃ��B
�Ō�ɁC���ɑ��āC�L�^�������Ƃ��ɁC���̐[�܂�C���܂�͉��ɂ���ĕۏႳ���̂��C�܂�,�u�Ȏ@�v�T�O�Ɓu����]���v�T�O�̈ٓ����ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��C�Ƃ������₪����܂����B
������́C���̂悤�ɉ�����܂����B
���H�L�^�́C�J���t�@�����X���d�˂ď�����邪�C���炩�ɔ��W�I�ȍ\�����Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���B���݁C�ᖡ����g�g�݂�͍����Ȃ�����g��ł���i�K�ł���C���H�̎��ƋL�^�̎��͘A�����Ȃ���i�ނ悤�C�T�|�[�g����d�g�݂Ƃ��čZ���̌���������W����悤�͍����Ă���B���Ƃ̎���ɂ��āC�]���̕]���́C���瑪��ɌX���C���f�҂̔��f���J�b�g����Ă����B����ɑ��Ȏ@�͑���I�ȍ������ɑ���ᔻ�Ƃ��Ē�N���ꂽ�B���H�̒��ł̏Ȏ@�͎��H�𑨂��Ȃ����C�]���̘g�g�݂��N���Ă����B���̂Ƃ��C���H�ɂƂǂ܂�̂ł͂Ȃ��C�Ȏ@���L�^�Ƃ��Ďc���C���ɂ���X�e�b�v���K�v���B���H�̒��ł̏Ȏ@�����L�ł���`�ɍđg�D�����邱�ƂŁC�]���Ƃ̖��ڂȂ�����肪�J����Ă���̂ł͂Ȃ����B
�ȏ�̋c�_�܂��������ŁC�t���A����́C�쐬���̃X�^���_�[�h�Ɋւ��ĕ����ڕW�Ȃ̂��C���B�ڕW�Ȃ̂���₤�����C�A�[�I�Ȋw�тɑ��鉉㈓I�Ȋw�т��ǂ��Ƃ炦�Ă���̂��Ƃ�������C�܂��C���E�����̊w�тƂ��āC��勳�Ȃɑ��鋳���̊w�т̐[�܂���ǂ��Ƃ炦��̂��Ƃ�������C�Ȏ@���������邱�Ƃɂ�茩���Ƃ������̂�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������ⓙ�����܂����B �����ɑ��C�Ȋw�̃v���Z�X���̂��̂��T���ƏȎ@�C�̌n���Ȃ̂ł���C�Ȋw�I�ȒT�����̂��̂ƏȎ@�͖������Ȃ��Ƃ��������Ȃ����ȂNJ����ȋc�_�ƂȂ�܂����B
�@�Ō�ɁC�����w�̎������w�����C���̂悤�ɖ{�����߂�����܂����B
��w�ɂ����Ă��ڕW�ƕ]���͖��ɂȂ��Ă���C��������z�����őn���I�Ȏ��H�ɖڕW�ƕ]�����ʒu�t���Ď��H�𑨂��Ȃ������Ƃ��K�v�ɂȂ�B���̂��ѕ����w�Ŗ{��J�����̂͂��肪�����C����Ƃ���낵�����肢�������B |
���ӁF��@���@��@�i
�i���s��w��w�@�j
|
|