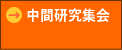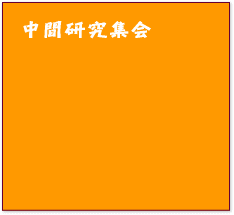index > 中間研究集会
|
|
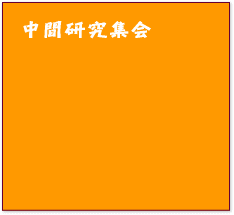
□2013年6月1日
教員養成における”質”保証の論点は何か?
□2012年6月9日
授業に活かす評価のあり方をめぐって
□2011年6月11日
教育目標・評価研究の20年を振り返る
□2010年5月22日
専門職として学び合うコミュニティを
支える評価の構造
□2007年6月16日
日本の学校接続の課題
―欧州の動向を踏まえて―
□2006年6月10日
糸賀一雄の魂と思想
□2005年7月9日
新しい世界の発見、新しい自分の発見
―『学力への挑戦』とその後―
□2003年5月10日
高等教育の人づくりと,企業社会の人づくり
―目標・評価論における,
教育学の固有性とはなにか―
□2001年4月28日
指導要録改訂で評価はどう変わるか
□1998年5月31日
第1部:教育課程改訂の彼方に21世紀の
評価研究をどのように展望するか
第2部:教育改革の展開に即して,二度に
わたる教育課程改訂の特性を明ら
かにする |

教育目標・評価研究の20年を振り返る
―『「評価の時代」を読み解く』(上)の検討を通して―
|
2011年6月11日
@一橋大学佐野書院
|
Ⅰ.教育方法学的アプローチ
報告者: 鋒 山 泰 弘
(追手門学院大学)
コメンテーター: 菊 地 愛 美
(一橋大学大学院・院生)
|
|
Ⅱ.社会的・政策的アプローチ
報告者: 長 谷 川 裕
(琉球大学)
コメンテーター: 呉 永 鎬
(一橋大学大学院・院生)
|
|
Ⅲ.歴史的アプローチ
報告者: 小 林 千 枝 子
(作新学院大学)
コメンテーター: 大 西 公 恵
(一橋大学大学院・院生)
後 藤 篤
(一橋大学大学院・院生)
|
|
司会:
木 村 元
(一橋大学)
山 田 哲 也
(一橋大学)
|
|

まず,久冨善之代表理事より,本書が教育目標・評価学会における20年間の研究の集大成であること,さらに上巻はその中核的な内容を扱っていることが確認され,今後の教育目標・評価研究における土台的な役割を持つことが示されました。
続いて,「第Ⅰ部 教育方法学的アプローチ」においては,鋒山会員による報告と菊地会員によるコメントがありました。はじめに鋒山会員からは,目標・評価研究の教育方法学的アプローチの進展と課題が,1990年代の学校における「学び」の問い直し状況を始点に報告されました。学校が教育内容・到達目標の「共通性」を追求してきたことへの批判と,受験競争の過熱が問題となる中で個々の教科教育における教育目標・評価研究がそれに対応することができたのかという反省から,子ども達の目標づくりへの「参加」,教育実践のプロセス,子どもの学びの質の評価という3点を対象とした研究が深められてきたことが整理されました。そして現在においては,子どもの目標づくりへの参加の手続き的保障,認識のダイナミズムを視野に入れた指導と評価,質の高い学びの成果を生み出すための評価方法の開発が深められており,具体的成果としては「真正の評価論」「パフォーマンス評価論」「ルーブリック」などの開発と研究の進展が見られていることが示されました。そうした蓄積の一方で,現代的な課題としては,各教科における「核となる教育内容」や子どもの「理解の質」の研究,「代行論」「参加論」双方の意義を踏まえた教師・子どもの「本質的な問い」の共有,教師の力量形成といった課題が浮かび上がることが指摘されました。
これに対し,菊地会員からのコメントでは,教育方法学的アプローチにおいて,①目標づくりの手続きに関する研究が手薄ではないかという指摘があったのち,②教育方法学的アプローチ独自の対象と目的とは何か,③真正性や有意味性を判断し学校教育に組み込むための基準の設定は可能か,④PISA型学力への日本の反応の背景には何があるのかという論点が提出されました。その後の応答及び議論において,①については,教育方法学という学問の性格とも大きく関わって,学習指導要領を前提とした方法の構築に傾斜しがちな状況が指摘されたものの,教師集団の自主的研究活動や目標づくりなどの蓄積に学ぶ点も多いことが確認されました。④については,総括議論においても論点となりましたが,鋒山会員からは「これまで日本において抽象的に議論されていた学力とその評価が,具体的な形式で表現・評価可能なものとして出されたこと」によるインパクトが語られました。日本における学力論議におけるある種の画期がPISAの登場によってもたらされたと見ることもできるようです。
フロアからは,教育方法学研究が陥りがちな実践のテクノロジーの複雑化という困難とともに,前提となる教育課題から乖離する側面があることが示され,その要因の一つとして,完全な教育方法を追求する傾向と,評価課題の前提にある本質的な問いの吟味の不十分さが指摘されました。具体的には,鋒山会員からも論点として挙げられていたように,パフォーマンス課題やルーブリックの開発が新たな格差の拡大をもたらす危険性や,パフォーマンス評価の活動主義的な引き取られ方などが示され,評価課題の提示の効果的なあり方の模索と教育目標研究の蓄積の必要性が確認されました。
「第Ⅱ部 社会的・政策的アプローチ」においては,長谷川会員による報告と呉会員によるコメントがありました。長谷川会員からは,「社会的・政策的アプローチ」をどのようなものとして捉えるのかが図示され,本アプローチが捉えようとする社会的関係性が確認されました。報告では特に「再帰的評価」に焦点化され,本学会における「教育評価」と「再帰的評価」の概念規定の研究の蓄積を踏まえつつ,
○教育評価:教育過程の遂行という関心に基づいてその過程をモニターすること
○第一次評価:教育過程を直接遂行するもの自身による,その教育過程に対する,その遂行上の関心に基づくモニタリング
○再帰的評価:教育過程の直接遂行者以外の者による,その教育過程やその結果に対する,その者にとっての関心に基づくモニタリング
という各概念の再定義が試みられました。教育内外の社会的な関係性に着目することで,社会に様々に存在する評価行為を整理する概念が改めて提起された報告でした。
一方,呉会員からのコメントは,教育目標・評価研究における社会的・政策的アプローチの射程と可能性を,学校制度における「平等」と「学力」をキーワードに探るものでした。社会的・政策的アプローチは,既存の「知識秩序」「生活秩序」「道徳秩序」を相対化する視点を含みもっており,教育目標がどのように定められ,学校知識がどのように選択され,その中のどの部分が評価の対象となっているのか/いたのかを検討することにより,それらの流動性・恣意性が浮き彫りになる,という呉会員による指摘は,本アプローチが教育領域における正統性を相対化する視点を提供できるという点を端的に示したコメントでした。
「第Ⅲ部 歴史的アプローチ」においては,小林会員による報告と大西会員,後藤会員によるコメントがありました。まず,小林会員からは第Ⅲ部の各章についての詳細なまとめとともに,「教育目標・評価研究における歴史研究あるいは教育史研究の役割はどういうものか」という大きな論点が提出されました。小林会員の執筆された第12章においては「到達度評価とはそもそも何だったのか」という現在の「目標に準拠した評価」との関係性が改めて問われ,また第14章「生活綴方に学ぶ『教育評価』の実際と可能性」においては,生活綴方と到達度評価,生活訓練それぞれとの関係性が問われました。ご報告において共通して強調されていたのは,「教育」の現実,「生きられた教育目標と評価の発掘」を促す方法論としての社会史の重要性とその方法的な困難さでしたが,それは同時に,描きだそうとする歴史の複雑さを反映するものであったとも思われます。
大西・後藤会員からのコメントでは,本書の第Ⅲ部の各章を具体的材料にしながら,「歴史的」研究という方法論のあり方を問うことを通して,これまでの教育目標・評価研究における歴史的アプローチの自省を促すものでした。特に本学会が,現代的な教育課題にいかに応えるかという即応的な課題に傾斜しがちであることと重ねて,歴史研究における解釈の問題が改めて議論されました。歴史研究と現代的な問題関心とのつながりは前提としながらも,自身の解釈の枠組みをいかに相対化して叙述していくのかという研究枠組み―歴史叙述の方法論――が問い直されました。後藤会員によるコメントでは,第14章での中内・平岡会員が提起する到達度評価を生活綴方の正当な嫡子とみるという「嫡子」論などを引き取りつつ,生活綴方における「リアリズム」が指している内実やこれまでの枠組みでは捉えきれなかった「生」についての認識を可能にする方法論の模索が課題として提出されました。
総括討論においては,司会の木村会員から議論の総括といくつかの論点提示がなされました。具体的には,教育目標・評価をめぐる教師の関わり方としての「代行論/参加論」をいかに位置づけるか,目標準拠という目標・評価論の正統性を自明のものとせず問い直すことが必要ではないか,既存の価値・枠組みに対する再帰的評価に対する本学会の応答はいかなるものか,教科教育学と教育方法学の自律性はどこに担保されるのか,グローバル化が進む21世紀の日本の教育状況において教育目標・評価研究の対応とその要因はいかなるものであったのか,歴史研究の方法論としての「解釈」の枠組みはいかに設定されるべきか,と言った様々な論点が提起されました。
それに対してて,フロアからは大きくは3点の議論が展開されました。
まず,教育評価史の整理の必要性が問われ,その際の時期区分についての課題が示されました。制度史か実践史か学説史か,あるいは民衆の評価観念による整理かといった具合に,教育目標・評価の歴史をどのように描いていくのかという問題提起がなされました。第Ⅲ部において議論になっていたような,到達度評価は歴史的にどのように位置づけられるべきかという点とも関わり,その課題の困難さが共有された一方で,この論点は,下記に示すような教育目標をいかに設定したり提示したりするのかという論点とも重なるものでした。
現代の「目標に準拠した評価」の一般的性格が,相対評価ないし集団に準拠した評価に対置されるものとして論じられているという現状が指摘され,それゆえに「ナショナルカリキュラムに準拠した評価」という政策的目標準拠評価が登場していることが指摘されました。つまり,目標に準拠した評価の多様性の整理と,目標の質の吟味の不足が指摘され,それらの峻別と克服の必要が提起されたことになります。さらに鋒山会員からは,相対評価を対抗物として措定した目標準拠型評価と,政策としての目標準拠型評価の峻別の必要と同時に,後者の評価が果たしてグローバル化する社会に応えられる評価足りえているのかという疑問が出されました。文科省・政策型の目標準拠と,学力論の明確化としての目標準拠評価との峻別は,教育目標設定の手続きに関する研究の蓄積が待たれていることを示唆しており,先の教育評価史の整理と同様,目標に準拠した評価の現代的な多様性を整理する概念の必要性が求められたと言えます。
また,教育目標の提示の仕方という点に関して,その目標像は教育過程の中における社会関係までも含めて論じられる必要があるのではないかという提起がなされました。教育内容・方法などを反映した目標像のみならず,それを規定している社会的・道徳的な関係をセットにして論じることで,教育目標の具体的な質にまで踏み込んだ教育目標・評価研究が展開されることを期待した論点でした。また,本書でも示されているように,教育の内容と活動とをひとつなぎにして捉え論じていくことの必要が再確認され,その方法論が模索された議論でした。
最後に,司会の山田会員から本集会のまとめとして次のように整理・確認がなされました。
①教育方法学的/社会的・政策的/歴史的アプローチが補完かつ緊張関係にもある。
②評価の再帰性は,国家による教育の在り方を問い直す契機になると同時に統制の手段ともなり得る。
③社会の複雑化に伴って教育目標もまた見えにくくなっており,教育目標が具体的内実を欠いた抽象的なもの,変容する社会を想定した構想となっている。
④上記と関わって,過去の日本の教育目標・評価研究は,国家との対抗関係の中で模索されてきたが,この20年間は,PISAなどに見られるようにグローバルスタンダードの重視および,それをもとにした保護者からの教育要求など,評価の再帰性が進んでいる。
⑤今後は,様々に生起する教育目標を,どういった図式で定義するのかということが求められ,かつ各目標に付随した価値を分析し再帰的に分析していくことが求められているだろう。
こうして,目標のあり方の模索という課題と向き合った本学会の20年間が整理されました。 |
|